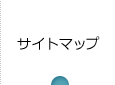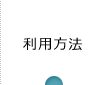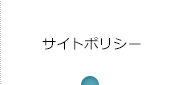タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
- OKAYAMA Share project ~おかやまをシェアしよう~ イベントレポート
- Social Good School !! 「Good」をもっと知ろう! イベントレポート
- 未来を生き抜く力を育む「野山の学校」開校
- (2013年11月6日)岡山発、新しい“協働”の形「災害時における 宗教施設のあり方を考えるセミナー」
- 農山村や暮らしとビジネスとの交流会 イベントレポート
- 子育て中親御さん、教育現場・対人サービス業の方へ
- 美作市で開催された地域活性化講演・発表会に参加しました!
- budding company fiesta
- 会議が変わると社会が変わる!? ファシリテーション講座に潜入してみた。
- 地域自主組織と小規模多機能自治を考える @地域力研修
持続可能な社会を考える 「豊かな海 守るため」
イベント・セミナーその他
今日は、こんにちは、ゆうあいセンターSDGs&CSR相談員 小桐です。
10月に入り、最初の投稿です。
今回は9月15日と9月23日に開催された山陽新聞連続シンポジウム「豊かな海 守るため」の事前ワークショップと本番のシンポジウムを通して、近いけどなかなか普段考えない海 瀬戸内海について情報を提供いたします。
私達が知らない間に、地球、瀬戸内海はどんどん変化していました。海の変化により私たちの食生活も色々と影響を受けていることが今回のシンポジウムを通して分かってきました。今後私たちは、海を守るためにどんなことが出来るのか考えてみたいと思います。
事前ワークショップが開催された9月15日にNHKの夜の番組「所さん事件ですよ」でちょうど日本の
海の変化について放送されました。日本の外洋の事を左記にご紹介し、次に本題の瀬戸内海について
考えていきたいと思います。
南の海沖縄では、絶滅危惧種ノアオウミガメが増えてきてその影響でさかながとれなくなっていると紹介されました。アオウミガメは、海草・海藻を食べます。そこは魚類の産卵場であり、CO2の吸収源でもあるのですが、アオウミガメの保護を実施したことで個体数が増え、23haもあった藻場が完全に消失。いまでは藻場を守るためにネットを張り巡らしカメが違づけないようにしているとのことです。オーストラリアでは繁殖のために6万匹が集まるような事態が報告されています。増えた原因は、昔からのたんぱく源であった亀を食べなくなったからという指摘が、岡山理科大の亀崎教授日本ウミガメ協議会前会長からありました。
これは、亀をたべるサメを駆逐したことも原因の一つと言われています。
また、水産庁水産振興アドバイザー 上田勝彦氏からは、日本の海の変化について、海水温度が上昇したことで魚の分布、移動が変わっている。山からの栄養塩基が針葉樹の植林により減ってきて貧栄養化している。水温上昇やアマモなどの減少により海が酸性化しているという指摘がありました。
海の海草・海藻が亡くなる状態を磯焼け と呼ぶそうです。神奈川県 城ヶ島では、あたり一面に生えていたカジメと言われる海藻がたった1年で丸坊主になったと漁師の方が証言されています。
原因は、温暖化でアイゴと いう南方系の魚が移動してきて、カジメを食べつくしているということです。アイゴは背びれには毒があり、食べるのには気をつけないといけない魚ですが、内臓などは美味で、今後は地元でとれる魚に物語をつけて食の喚起を図る必要があると発言されました。
ここからは、瀬戸内海に話を戻します。瀬戸内海でも海に変化が起きています。モデレーター 山陽新聞社 岡山さんが倉敷市児島地区の 第一田ノ浦吹上漁協の 岡組合長に取材した記事を紹介するところからシンポジウムが始まりました。
これまで獲れていた魚類が獲れなくなった。タコ、ゲタ(舌平目)、アナゴ、ママカリ、イイダコ。10倍の価格になったものもある。増えた魚もあるハモ、マダイ、アコウ(南方系)。チヌ(クロダイ)は、海苔の養殖に悪影響があると価値が下がり獲らなくなった。ハモは骨切りをしないといけない岡山では需要が少なく関西に販売している。 ここ5年間の海の変化が著しい。漁師の数は1/2になったのに、一人当たりの業漁獲量は2/3に落ちている。原因は、貧栄養化、温暖化があると思う。とれる魚も変わったという内容です。
シンポジウムパネラーの「おかとと」(岡山水産物流通促進協議会)事務局・長谷井商店取締役 中島 俊子さんからは、瀬戸内海で獲れて岡山で食される魚を地魚と呼んでいるが、 最近は魚を食べる回数が減っている。 食べても地魚ではなく他地域の食べやすい魚(サーモン、マグロなど)を多く食べている。
岡山中央卸売市場では、地魚の流通量は激減している。
そこで令和1年に 協議会を発足させ、漁師・漁連・漁協―市場―加工業者―販売店・飲食店―消費者を結んで情報発信、消費拡大、普及活動を開始した。岡山南高校の協力を得てお魚スタンプなども作ってもらいアピールしている。地魚のレシピや魚食文化の紹介や子ども食堂への提供なども行っている。
二人目のパネラー NPO法人里海づくり研究会議事務局長 田中 丈裕さんからは、世界や瀬戸内の海の変化について1950年代から将来予測も含めて解説がありました。
瀬戸内は、この50年間で大きく変わった、そして、最近5年はさらに変化し、世界でも異変が起きている。
1950年代までは、正常な海だった。1970年代は赤潮が発生し、プランクトンが有毒化することで瀕死の海と言われた。1973年に瀬戸内法の制定により、きれいな海(貧栄養化)が始まった。
また、1950年代~80年代までは、干拓により、干潟や藻場がどんどん減少していった。貝が少なくなり、水質が悪化した。 皮肉なことだが、富栄養化した海の最高の漁獲があったのは、1980年85万トンだった。それがきれいな海が実現したことで、2012年(平成24年)には38万トンまで落ちこんでいる。 1980~90年代は栄養塩基が減少し、海水温度が上昇し、貧酸素化の状況となった。2000年以降は加えて底質が悪化してきている。
現在、産業革命前と比較してCO2の濃度は1.5倍に、気象災害は5倍に増加している。30年後には、赤道付近には魚がいなくなることが予測されている。北上していく。酸素濃度が下がると大きな魚は生きられなくなる。日本近海でも平均水温は1.14℃上がっている、世界平均は100年で0.55℃の上昇となっている。
ここ3年では、サケ、サンマ、スルメイカ、サワラなどが獲れなくなった。従来の気候変動の減少だけでは説明できない現象が起きている。
全国各地の漁業関係者にアンケートを採ったところ、
・漁期が変化、魚の移動時期が変わった
・獲れていた魚が獲れなくなり、獲れていない魚が獲れるようになった
・複数の南方種の混在
岡山での変化は
・足切れダコ(3~4本ないもの)が多い日には40%もある⇒海中に餌がないため食べられる
・7種類獲れていたエビが獲れない
・ウミホタルが生きている魚を食べる
・ヒメハマトビムシがサワラの腹に食いつく
・富栄養化の現象もみられる オカメブンブク(ウニの仲間)大量発生、ヒゼンクラゲの発生
などの変化を報告されました。
今後の予測としては、
・海水温度の上昇、溶存酸素量の減少
・栄養塩基類の減少(チッソ、リン)
・海洋酸性化するとエビ、カニ、ウニの卵が孵化できない。
・PH8.1で海水は落ち着いているが、賛成になると炭酸カルシウムが形成されにくくなる。
・北の海は酸性化し、南の海は温暖化することになる
・底層の貧酸素化
生き物にとっては死活問題となる現象が複合的に発生することが分かります。
・海藻・海草などの生物が温暖化の体躯に有効だということが分かり、ブルーカーボンとして増やしていくことが重要
モデレーターのSDGsネットワークおかやま会長石原さんから「きれいな海は生産性が高い海というわけではないのか」という質問がありました。
田中さんは、世界3大漁場のひとつ三陸沖では、濁っている。生物量が多いという証拠。漁師は。見えすぎる海は魚がいなということを知っている。岡山では三大河川からの栄養塩基の流入が減っている。海に注ぐ水の到達方法は3種類。川、地下水、肥料水なので高度な処理でチッソ、リンを取り除くのは困る。
チッソ、リンは海の中で循環しており、そのスピードが物質を循環させている。藻場を取り戻すことが重要。
石原さんが、岡山県の藻場の変化について1950年代と2000年代の様子が分かる地図の資料を紹介し、藻場の減少を裏付ける結果を共有しました。海の生物や酸性化に効果のあるアマモ場の復活は昔のような面積に戻るかの質問に対して 田中氏さんからは、干拓された部分は戻ってこない。日生のようにアマモ場を増やす活動をすることで良い状態に近づくことはできると説明がありました。
岡山の東南端に位置する日生で、アマモを増やす研究活動をしている岡山学芸館高校の林 志龍さんからは、室内栽培でアマモを増やす研究について発表がありました。バクテリアの影響、種のおき方、リン酸によるもやし化への対応を研究している。マリンチャレンジというコンテストがあり、来年3月に中国地区の代表として研究を続け、発表する予定である。
モデレーターか意見を求められた田中氏(30年以上日生漁協と共にアマモの再生活動を続けている)からは、アマモの繁殖方法には3種類あり、移植する方法、種を取り撒く方法、苗の植え付け方法。現在は、効率の良い種取り、播種方法を採用しているが、40年前から技術が進化していない苗植え付け方法は、未確立していないので大変興味深い。確立すれば色々な場所で繁殖したものを集められるので、メリットはある。ただし、海洋汚染しないように従来のペーパーポポッドは使用しないようにするとフォローがありました。
田中氏からは、続いてアマモ場の変化について、解説がありました。1950年代は84,000haあったものが最低では、550haまえ減った。2015年には1876ha前戻ってきた。
アマモ場には、14種類の地球環境課を改善する効果がある。 カニやエビなどの産卵場であり、CO2吸収源である。干拓で水島800ha笠岡600ha1が失われたので、努力しても1950年代には戻らない、しかし全国的には回復については日生を筆頭に頑張っている。
話題は、豊かな海を取り戻すだけでなく、地元の豊かな海の幸を享受することに移りました。
再び「おかとと」 中島さんから岡山を代表する魚 ヒラについての話題提供がありました。
ヒラは、ニシン科の魚で 冬に脂がのって美味しいが、小骨が多いために日本では岡山県でしか食べられていない。味はとても良いので、「おかとと」としてヒラをアピールするのに魚編に岡山とかいて、ヒラという造字をつくり、商標登録を行った。 中国では高級料理として食されるだけに、コロナが落ち着いたらインバウンドに期待し、日本で岡山でしか食べられない高級魚の刺身をアピールしていきたい。県民でも食べる量が少なくなっているので、ヒラカツバーガー、ヒラ天、ヒラのアヒージョと煮つけ缶を発売したり、ヒラTシャツ、地魚のクッションを作ったり、さかなくんにも紹介をするなど各方面でアピールを行っている。
これらの活動は、令和の里うみづくりのモデル事業10件の中に選ばれている。
「岡山の豊かな海の保全と共に歩む魅力ある岡山の魚食文化」 をコンセプトに食と学のつながりを今後広く伝えていきたい。里海づくりが岡山の魚食文化の継承につながるように低利用、未利用魚の流通促進を図りたく、アマモ場に関したパンフレット作成や次年度以降で食と学の体験ツアーを実施する準備をしている。
事前ワークショップでも発言をいただいた「おかとと」 森下会長からは、地元で獲れる魚のおいしさや季節ごとに美味しい魚の紹介がありました。夏にはアコウ(キジハタ)の刺身やあら炊きが美味しい。
シャコは獲れなくなったが南方系のトゲシャコが獲れる。ワタリガニが減ったがタイワンガザミが獲れる。是非地元で獲れる魚を食べて欲しい。ハモ、ヒラ、スズキの低利用魚はお薦め。
最後に岡山さんが以下の様にまとめられました。
コロナが流行り、ロシアの進行があり、海外から多くの食を輸入している日本は、いかにリスクがあるか一段と感じる。食糧だけでなく、飼料も輸入している。これらが入らなくなることは食糧安全保障に直接かかわってくる。 日本は、魚食の文化、重要なたんぱく源だった。しかし、今は肉を食べて、魚を食べなくなっている。
昔から食べていて、身近に食べられているものの価値を改めて見直す必要があるのではないか。
(遠方の魚より地元の魚を食べるべきでは) アマモ場の復活は目の前の工場を再稼働させるようなことにつながるのでないか。
10月に入り、最初の投稿です。
今回は9月15日と9月23日に開催された山陽新聞連続シンポジウム「豊かな海 守るため」の事前ワークショップと本番のシンポジウムを通して、近いけどなかなか普段考えない海 瀬戸内海について情報を提供いたします。
私達が知らない間に、地球、瀬戸内海はどんどん変化していました。海の変化により私たちの食生活も色々と影響を受けていることが今回のシンポジウムを通して分かってきました。今後私たちは、海を守るためにどんなことが出来るのか考えてみたいと思います。
事前ワークショップが開催された9月15日にNHKの夜の番組「所さん事件ですよ」でちょうど日本の
海の変化について放送されました。日本の外洋の事を左記にご紹介し、次に本題の瀬戸内海について
考えていきたいと思います。
南の海沖縄では、絶滅危惧種ノアオウミガメが増えてきてその影響でさかながとれなくなっていると紹介されました。アオウミガメは、海草・海藻を食べます。そこは魚類の産卵場であり、CO2の吸収源でもあるのですが、アオウミガメの保護を実施したことで個体数が増え、23haもあった藻場が完全に消失。いまでは藻場を守るためにネットを張り巡らしカメが違づけないようにしているとのことです。オーストラリアでは繁殖のために6万匹が集まるような事態が報告されています。増えた原因は、昔からのたんぱく源であった亀を食べなくなったからという指摘が、岡山理科大の亀崎教授日本ウミガメ協議会前会長からありました。
これは、亀をたべるサメを駆逐したことも原因の一つと言われています。
また、水産庁水産振興アドバイザー 上田勝彦氏からは、日本の海の変化について、海水温度が上昇したことで魚の分布、移動が変わっている。山からの栄養塩基が針葉樹の植林により減ってきて貧栄養化している。水温上昇やアマモなどの減少により海が酸性化しているという指摘がありました。
海の海草・海藻が亡くなる状態を磯焼け と呼ぶそうです。神奈川県 城ヶ島では、あたり一面に生えていたカジメと言われる海藻がたった1年で丸坊主になったと漁師の方が証言されています。
原因は、温暖化でアイゴと いう南方系の魚が移動してきて、カジメを食べつくしているということです。アイゴは背びれには毒があり、食べるのには気をつけないといけない魚ですが、内臓などは美味で、今後は地元でとれる魚に物語をつけて食の喚起を図る必要があると発言されました。
ここからは、瀬戸内海に話を戻します。瀬戸内海でも海に変化が起きています。モデレーター 山陽新聞社 岡山さんが倉敷市児島地区の 第一田ノ浦吹上漁協の 岡組合長に取材した記事を紹介するところからシンポジウムが始まりました。
これまで獲れていた魚類が獲れなくなった。タコ、ゲタ(舌平目)、アナゴ、ママカリ、イイダコ。10倍の価格になったものもある。増えた魚もあるハモ、マダイ、アコウ(南方系)。チヌ(クロダイ)は、海苔の養殖に悪影響があると価値が下がり獲らなくなった。ハモは骨切りをしないといけない岡山では需要が少なく関西に販売している。 ここ5年間の海の変化が著しい。漁師の数は1/2になったのに、一人当たりの業漁獲量は2/3に落ちている。原因は、貧栄養化、温暖化があると思う。とれる魚も変わったという内容です。
シンポジウムパネラーの「おかとと」(岡山水産物流通促進協議会)事務局・長谷井商店取締役 中島 俊子さんからは、瀬戸内海で獲れて岡山で食される魚を地魚と呼んでいるが、 最近は魚を食べる回数が減っている。 食べても地魚ではなく他地域の食べやすい魚(サーモン、マグロなど)を多く食べている。
岡山中央卸売市場では、地魚の流通量は激減している。
そこで令和1年に 協議会を発足させ、漁師・漁連・漁協―市場―加工業者―販売店・飲食店―消費者を結んで情報発信、消費拡大、普及活動を開始した。岡山南高校の協力を得てお魚スタンプなども作ってもらいアピールしている。地魚のレシピや魚食文化の紹介や子ども食堂への提供なども行っている。
二人目のパネラー NPO法人里海づくり研究会議事務局長 田中 丈裕さんからは、世界や瀬戸内の海の変化について1950年代から将来予測も含めて解説がありました。
瀬戸内は、この50年間で大きく変わった、そして、最近5年はさらに変化し、世界でも異変が起きている。
1950年代までは、正常な海だった。1970年代は赤潮が発生し、プランクトンが有毒化することで瀕死の海と言われた。1973年に瀬戸内法の制定により、きれいな海(貧栄養化)が始まった。
また、1950年代~80年代までは、干拓により、干潟や藻場がどんどん減少していった。貝が少なくなり、水質が悪化した。 皮肉なことだが、富栄養化した海の最高の漁獲があったのは、1980年85万トンだった。それがきれいな海が実現したことで、2012年(平成24年)には38万トンまで落ちこんでいる。 1980~90年代は栄養塩基が減少し、海水温度が上昇し、貧酸素化の状況となった。2000年以降は加えて底質が悪化してきている。
現在、産業革命前と比較してCO2の濃度は1.5倍に、気象災害は5倍に増加している。30年後には、赤道付近には魚がいなくなることが予測されている。北上していく。酸素濃度が下がると大きな魚は生きられなくなる。日本近海でも平均水温は1.14℃上がっている、世界平均は100年で0.55℃の上昇となっている。
ここ3年では、サケ、サンマ、スルメイカ、サワラなどが獲れなくなった。従来の気候変動の減少だけでは説明できない現象が起きている。
全国各地の漁業関係者にアンケートを採ったところ、
・漁期が変化、魚の移動時期が変わった
・獲れていた魚が獲れなくなり、獲れていない魚が獲れるようになった
・複数の南方種の混在
岡山での変化は
・足切れダコ(3~4本ないもの)が多い日には40%もある⇒海中に餌がないため食べられる
・7種類獲れていたエビが獲れない
・ウミホタルが生きている魚を食べる
・ヒメハマトビムシがサワラの腹に食いつく
・富栄養化の現象もみられる オカメブンブク(ウニの仲間)大量発生、ヒゼンクラゲの発生
などの変化を報告されました。
今後の予測としては、
・海水温度の上昇、溶存酸素量の減少
・栄養塩基類の減少(チッソ、リン)
・海洋酸性化するとエビ、カニ、ウニの卵が孵化できない。
・PH8.1で海水は落ち着いているが、賛成になると炭酸カルシウムが形成されにくくなる。
・北の海は酸性化し、南の海は温暖化することになる
・底層の貧酸素化
生き物にとっては死活問題となる現象が複合的に発生することが分かります。
・海藻・海草などの生物が温暖化の体躯に有効だということが分かり、ブルーカーボンとして増やしていくことが重要
モデレーターのSDGsネットワークおかやま会長石原さんから「きれいな海は生産性が高い海というわけではないのか」という質問がありました。
田中さんは、世界3大漁場のひとつ三陸沖では、濁っている。生物量が多いという証拠。漁師は。見えすぎる海は魚がいなということを知っている。岡山では三大河川からの栄養塩基の流入が減っている。海に注ぐ水の到達方法は3種類。川、地下水、肥料水なので高度な処理でチッソ、リンを取り除くのは困る。
チッソ、リンは海の中で循環しており、そのスピードが物質を循環させている。藻場を取り戻すことが重要。
石原さんが、岡山県の藻場の変化について1950年代と2000年代の様子が分かる地図の資料を紹介し、藻場の減少を裏付ける結果を共有しました。海の生物や酸性化に効果のあるアマモ場の復活は昔のような面積に戻るかの質問に対して 田中氏さんからは、干拓された部分は戻ってこない。日生のようにアマモ場を増やす活動をすることで良い状態に近づくことはできると説明がありました。
岡山の東南端に位置する日生で、アマモを増やす研究活動をしている岡山学芸館高校の林 志龍さんからは、室内栽培でアマモを増やす研究について発表がありました。バクテリアの影響、種のおき方、リン酸によるもやし化への対応を研究している。マリンチャレンジというコンテストがあり、来年3月に中国地区の代表として研究を続け、発表する予定である。
モデレーターか意見を求められた田中氏(30年以上日生漁協と共にアマモの再生活動を続けている)からは、アマモの繁殖方法には3種類あり、移植する方法、種を取り撒く方法、苗の植え付け方法。現在は、効率の良い種取り、播種方法を採用しているが、40年前から技術が進化していない苗植え付け方法は、未確立していないので大変興味深い。確立すれば色々な場所で繁殖したものを集められるので、メリットはある。ただし、海洋汚染しないように従来のペーパーポポッドは使用しないようにするとフォローがありました。
田中氏からは、続いてアマモ場の変化について、解説がありました。1950年代は84,000haあったものが最低では、550haまえ減った。2015年には1876ha前戻ってきた。
アマモ場には、14種類の地球環境課を改善する効果がある。 カニやエビなどの産卵場であり、CO2吸収源である。干拓で水島800ha笠岡600ha1が失われたので、努力しても1950年代には戻らない、しかし全国的には回復については日生を筆頭に頑張っている。
話題は、豊かな海を取り戻すだけでなく、地元の豊かな海の幸を享受することに移りました。
再び「おかとと」 中島さんから岡山を代表する魚 ヒラについての話題提供がありました。
ヒラは、ニシン科の魚で 冬に脂がのって美味しいが、小骨が多いために日本では岡山県でしか食べられていない。味はとても良いので、「おかとと」としてヒラをアピールするのに魚編に岡山とかいて、ヒラという造字をつくり、商標登録を行った。 中国では高級料理として食されるだけに、コロナが落ち着いたらインバウンドに期待し、日本で岡山でしか食べられない高級魚の刺身をアピールしていきたい。県民でも食べる量が少なくなっているので、ヒラカツバーガー、ヒラ天、ヒラのアヒージョと煮つけ缶を発売したり、ヒラTシャツ、地魚のクッションを作ったり、さかなくんにも紹介をするなど各方面でアピールを行っている。
これらの活動は、令和の里うみづくりのモデル事業10件の中に選ばれている。
「岡山の豊かな海の保全と共に歩む魅力ある岡山の魚食文化」 をコンセプトに食と学のつながりを今後広く伝えていきたい。里海づくりが岡山の魚食文化の継承につながるように低利用、未利用魚の流通促進を図りたく、アマモ場に関したパンフレット作成や次年度以降で食と学の体験ツアーを実施する準備をしている。
事前ワークショップでも発言をいただいた「おかとと」 森下会長からは、地元で獲れる魚のおいしさや季節ごとに美味しい魚の紹介がありました。夏にはアコウ(キジハタ)の刺身やあら炊きが美味しい。
シャコは獲れなくなったが南方系のトゲシャコが獲れる。ワタリガニが減ったがタイワンガザミが獲れる。是非地元で獲れる魚を食べて欲しい。ハモ、ヒラ、スズキの低利用魚はお薦め。
最後に岡山さんが以下の様にまとめられました。
コロナが流行り、ロシアの進行があり、海外から多くの食を輸入している日本は、いかにリスクがあるか一段と感じる。食糧だけでなく、飼料も輸入している。これらが入らなくなることは食糧安全保障に直接かかわってくる。 日本は、魚食の文化、重要なたんぱく源だった。しかし、今は肉を食べて、魚を食べなくなっている。
昔から食べていて、身近に食べられているものの価値を改めて見直す必要があるのではないか。
(遠方の魚より地元の魚を食べるべきでは) アマモ場の復活は目の前の工場を再稼働させるようなことにつながるのでないか。

- OKAYAMA Share project ~おかやまをシェアしよう~ イベントレポート
誰もが社会を変えられる。 そんな可能性を、シェアしよう。
「OKAYAMA Share project」は、岡山..