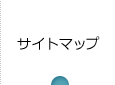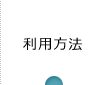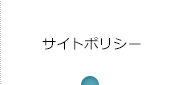タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
- OKAYAMA Share project ~おかやまをシェアしよう~ イベントレポート
- Social Good School !! 「Good」をもっと知ろう! イベントレポート
- 未来を生き抜く力を育む「野山の学校」開校
- (2013年11月6日)岡山発、新しい“協働”の形「災害時における 宗教施設のあり方を考えるセミナー」
- 農山村や暮らしとビジネスとの交流会 イベントレポート
- 子育て中親御さん、教育現場・対人サービス業の方へ
- 美作市で開催された地域活性化講演・発表会に参加しました!
- budding company fiesta
- 会議が変わると社会が変わる!? ファシリテーション講座に潜入してみた。
- 地域自主組織と小規模多機能自治を考える @地域力研修
持続可能な社会を考える 「食品ロス」その2
イベント・セミナーその他
今日は、こんにちは、ゆうあいセンターCSR相談員 小桐です。
今回は前回の事前ワークショップに続き、山陽新聞が開催する連続シンポジウム第3弾 「SDGs地域課題を探る」 2022年シリーズの第1回「食品ロス」 についての内容をご紹介します。
今回のシンポジウムのパネラーは下記の三氏です。
① 株式会社ハローズ 商品管理室長 太田 光一氏
② NPO法人フードバンク岡山 理事長 糸山 智栄氏
③ NPO法人ジャパンハーベスト理事長&フードシェアリングジャパン代表 成田 賢一氏
当日は3氏以外に事前ワークショップで発言された方々も登壇されました。前回でご紹介した おかやまエコマインドネットワーク、コノヒトカンプロジェクト&岡山高校スパイダーず、岡山大学田中さんと桐生さん(松井先生代読)は簡単に紹介します。詳しくはこちらをご覧ください。
http://okayama-share.jp/cgi/web/?c=social_kiji-2&pk=381
シンポジウムの総合司会を岡山高校 スパイダーずの4人が務めてくれました。
冒頭食品ロスの概要について 山陽新聞社 岡山氏(論説委員会主幹)より情報提供がありました。 日本は食糧の輸入率が世界で一番高く62%(カロリーベース)、内570万トンを食品ロスとして捨てている。(輸入して捨てる国) この廃棄による温室効果ガスの割合は8~10%、最近話題となっている航空機の運航により排出される量1%と比較すると大変大きな数字となっている。
同じくモデレーターのSDGsネットワークおかやま 石原会長からは、フードロスが関係するSDGsの目標についての説明がありシンポジウムがスタートしました。
目標12 つくる責任使う責任 12.3食品廃棄を一人当たり半減させ、生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 12.5廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により廃棄物の発生を大幅に削減する。
目標2 飢餓をゼロに 2.1 飢餓を無くし、特に貧困層ならびに幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分に得られるようにする。 2.2 5歳未満の子どもの発育障害、消耗症(2025年までの目標達成に)ならびに若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズに対処。
目標1 貧困を無くそう 1.2各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある全ての年齢、男性、女性、子供の割合を半減させる。
登壇者のトップとして ハローズ太田氏がハローズモデルと呼ばれる同社の活動ならびにこれから強化していきたい「コミュニティパントリー(地域食品庫)」についての説明がありました。
ハローズモデルは、食品を必要とされる団体が直接ハローズ各店舗に赴くことで賞味期限内の食品を無料で受け取る仕組みで、同業者や取引先にも広く進めておられ、第6回 食品産業もったいない大賞(2019)、 内閣府子どもの未来応援国民運動HP掲載(2020)に加え、食品ロス削減推進大賞受賞(2020)という受賞歴があります。この取り組みは、企業視点で見ると廃棄処分コストの削減にもつながり、双方にメリットのある取り組みでもあります。
困窮者を対象に、地域で行われる子ども食堂の活動では、30%ほどしか救済できていないので、そこを補う形としてピンポイントで食品を提供し役割を果たせる「地域食品庫」を広めたい。
「コミュニティパントリー(地域食品庫)」とは、聞きなれない言葉ですが、日本で初めてできた公共の冷蔵庫(岡山市北長瀬駅隣接)「コミュニティフリッジ」が商標登録されたために勝手に使えないとのことで、フィリピンで普及しているこの名称を使って進めていこうとしています。
「困窮者にピンポイントで食品を提供する仕組み」は既に北長瀬コミュニティフリッジで出来上がっていて、運搬は食品物流の日本アクセス、岡山水急 食品保管の冷蔵庫はフクシマガリレイが提供してくれます。
県外でもこの動きが始まっていて 愛媛県新居浜市と西条市で eえひめフードバンク笑顔、神石高原町(広島県)、あこう子ども食堂(兵庫県)、ジャパンフードバンクリンク:留学生対象(福山市)、オアシス丸亀(香川)がすでに実施。今後は3月6日から倉敷市、高松市 さくらや(制服リユースショップ)、福山中央ライオンズクラス シングルマザー対象、吉備中央町 フードシェアリングジャパン(提案中)などが展開予定。 困っている人しか鍵が開けられないとシステムなのでピンポイントでお助けができる。
ここからは、企業としてのフードロス削減の数値を紹介。5年間で0.25%削減が出来、金額は4億円、救われた食品の重量は400トン。おむすびの廃棄率4%が1%にまで削減できている。
先日消費者庁で話をしたが、現在販売金額40位のハローズより上位の企業37~38社はフードロス削減の取り組みが弱い。40位の企業が150トン1.5億円の提供をしているので、上位企業が取り組めば単純計算で6000トン、60億円の食品が有効に活用される。
「善きサマリア人の法」がない日本(受けわたした商品の責任は受け取った側にある。)最近ニュージーランドでも同じような法律が制定され、急速に広まった事実がある。これまで、フードバンク岡山と取り組む際には提供後の商品の責任はそちらで持って欲しいとの合意で行っており、これまで7年間提供してきてクレームはゼロ。簿価ゼロなので会社の損失もない。ネームバリューは上がるのみ。大手の取り組みを期待する。
次に 供給側と需要側の間を取り持ち、食品を届ける役割をされている フードシェアリングジャパン代表 成田 賢一氏 自己紹介では、イギリス人のジャーナリストが名付けてくれた「食料困窮活動家」(Food Poverty Activist)として活動。本業は、㈱ケンジャミンフランクリンで移動販売スーパーやベルネーゼ(レストラン)を営み、吉備中央町町会議員としても務めている。個人の活動として、令和3年度消費者庁食品ロス削減大賞 長官賞を受賞と紹介後、世界の食品ロスを有効活用する取り組みと自分の活動を紹介されました。
食品を提供する活動として、早朝より、事業者に引き取りに行き、必要とするところへ届け、9時には自社の商店を開店している。今日は、4時~ハローズ岡南店でパン引き取り、江崎店回り、真備に届けてきた。
フードバンク数は国内では151団体、イギリスは2000,フランス2180,ドイツ947ある、食品提供活動の名称も各国で様々なものが使われている。フードシェアリング、フードリカバリー、フードサルベージ、フードドライブ、フリーフリッジ、フードシェアリング、サポーターズフードバンクなど。イギリスではコミュニティフリッジの名称で500を超えて運営されている。日本ではそれが商標登録されていて、誰もが自由に使えなくなっていることを残念と感じる。(と、ハローズ 太田氏と異口同音の発言がありました)
オーストラリアでは、OZ(オズ)ハーベストが無料スーパーを運営している。 イギリスではサポーターズフードバンクという活動で、サッカープレミアリーグのサポーターが試合前に集めている。日本でも食品ロス削減活動をさらに広めたい。できる範囲や出来ることを取り組む。やればできる。
モデレーターの岡山氏は、「誰が食品を取りに行くのか?」がカギだったが、成田氏の配達活動を重要な存在と説明しました。続いて、事前ワークショップでも登壇した 倉敷市でネイルサロンを営みながら、コロナ禍で16の飲食店で余った食材を利用し、缶詰をつくり、提供している「コノヒトカン(肉・魚) プロジェクト」三好さんが活動を紹介しました。 貧困・孤立とフードロスを解消するために始めた活動です。
缶詰のレシピづくりに20名のシェフが協力してくれており、ロス食材を生かしシェフが料理をする。子どもたち自らが2合のご飯と混ぜ調理をする。食について考える機会を提供するという思いが詰まった缶詰です。35名の子どもに19合のご飯と10缶を提供したら完食をしてくれました。2021年は1000缶をつくり、2022年は2000個を目指すとしています。教材としての活用を合わせて行います。
続いて、最後のパネラー NPO法人フードバンク岡山 糸山 智栄氏の発表。20212年廃棄物工学研究所からの声掛けを機にスタート。 倉庫・事務所・個人宅配の3無い でスタート。生協からは年間260日野菜を中心に受取り、ハローズとの取組は当初店長会議で店長が持ち寄ったものをもらうことからスタートして、現在のハローズモデルに行きついています。
近いうちに瀬戸内食品ロス削減団というタイトルで、岡山でフードバンク活動をしている団体を紹介した書籍を発行予定。トラック協会から順正学園、農協、生協、森林組合、中学校、大学サークル、高校生学童保育支援などを紹介します。
これまで活動してきた中で、糸山さんが感じる“もやもや”は、タンパク質源がなかなか来ない。食べる人が栄養を考えて、自分で選べるようになると良い。ハローズ太田さんによると豆腐、納豆、青果が多くなる傾向。1日1団体の受付としているので、自社だけで不足する面もあるので、他スーパーにも声をかけている。マッチングに問題がどうしても生じてしまうとの話です。
・食品ロスのマッチングについて研究している岡山大学 桐生さんが研究を発表。(事前ワークショップでは、指導教官の松井先生が紹介)。食品ロスの提供先は、福祉施設(障がい、高齢、児童)よりも困窮世帯の方が、マッチング率が高くなると紹介しました。
・マッチングアップの方策として岡山氏から、量のマッチングだけでなく、質のマッチングが必要であること。太田氏からは渡す側から受け取った側に責任が転換する「良きサマリア人法」を市町村単位で条例をつくり、実施できれば良い。 成田氏からは、アイルランドのフードアプリでは、提供側が重量を表示し、需要側がそれを見て引き取りすることもあると紹介がありました。糸山氏からは、倉庫の整備やアプリ開発よりもコーディネイトする人に給料(アルバイト時給)が出れば、もっと広がっていくとの指摘がありました。
・事前ワークショップで食品ロス削減の啓蒙活動を紹介したエコマインドネットワーク 赤井さんは、出前講座で小学校や公民館で行っていること。そのために、啓蒙DVDを制作したこと、もったいないキッチン、0円キッチンなどの映画上映会も実施していることを発表しました。私たちは、賞味期限や消費期限に囚われすぎている。買い物で食品を選ぶ際は、棚に欠品があっても「食品ロスを出さない店」として評価すべき、DVDにもこの内容を盛り込んでいる。
赤井さんに続いて、食品ロス削減に取り組む団体の発表がありました。
・一宮高校ユネスコ部は、店での食べ残しを持ち帰るドギーバッグについて紹介。自己責任カードを用意して店側に提示すると良い。調査では店が持ち帰り容器を有料で販売しても90%の客は持ち帰ると答えた。 成田氏は、店側からの声掛けがあると良いとの意見も付け加えました。ドギーバッグの新名称を「モッテコ(mottECO)」に消費者庁が変更したとの太田氏の情報提供もありました。
・ハローズでは、おにぎりの納品回数を1日2回にしたことで、4%のロスが1%に削減できた。合わせて少量パックを販売し、ロスが出ない対策を実施。賞味期限についての割引販売では、1カ月を切ったら20%オフ、3週間で40%オフ、2週間前になると店頭から撤去という方法でロス削減策を実施。
・岡山高校スパイダーずは夏休みに学童保育で糸山さんと知り合い、動画を作成しオンラインイベント フードロス✕学童保で全国1200人の子ども達にフードロスを伝え、無くすための行動宣言を書いてもらったと報告がありました。フードロス映画の上映やコノヒトカンプロジェクトの広報を手伝っています。
・岡山大学食品ロス大作戦 田中 朱音さん 農水、環境、経産省や30自治体の食品ロスデータを集め、ヒヤリング調査を実施し、岡山県と岡山市にパブリックコメントを提出し、県とは意見交換も行った。
・指導教官の松井准教授からは、岡山県の食品ロスは8.9万トン/年 243トン/日。困窮者支援のボランティアに頼るだけでなく、余剰食品の割引販売を行う方法もある。姫路市ではタベスケというアプリを活用し、短時間で消費者が利用できるしくみがある。食品ロスは管理コストが発生し、受益者の費用負担が発生する。県民全員が参加できるようにすると共に、生活困窮者には無償提供するか寄付付きで負担を無くして食品が手に入るようにするという提案がありました。
パネラー、モデレーターのまとめとして
・コミュニティパントリーの普及拡大を図り、ひとり親世帯の生活困窮者でかつ親と同居する人への支援を強化したい。太田氏
・食べ残しをしない。友人に伝えて、情報活動を共有する。メディアに多く取り上げて欲しい。成田氏
・若い人たちの食品ロス削減の活動が心強い。トップランナー方式で良いことを広め、行政で取り上げて欲しい。糸山氏
・フードロスが共通言語となっている。若い人の取り組みと共に県民全員参加の機運を盛り上げていきたい。岡山は食品メーカーが多く、食品ロスが多い。PLO法の関係で食品ロスは発生する(善きサマリア人の法の条例制定などで)がなんとかしなければならない。食品ロス削減は、量と質のマッチングが必要。
岡山県がマッチングシステム構築の予算を2022年度に確保している、これを、マッチングアプリに使うだけでなく、管理するパートタイマーの費用にも充てて欲しい。
個人の購買時は、賞味期限や欠品に寛容になって欲しいと岡山氏が締めくくりました。
今回は前回の事前ワークショップに続き、山陽新聞が開催する連続シンポジウム第3弾 「SDGs地域課題を探る」 2022年シリーズの第1回「食品ロス」 についての内容をご紹介します。
今回のシンポジウムのパネラーは下記の三氏です。
① 株式会社ハローズ 商品管理室長 太田 光一氏
② NPO法人フードバンク岡山 理事長 糸山 智栄氏
③ NPO法人ジャパンハーベスト理事長&フードシェアリングジャパン代表 成田 賢一氏
当日は3氏以外に事前ワークショップで発言された方々も登壇されました。前回でご紹介した おかやまエコマインドネットワーク、コノヒトカンプロジェクト&岡山高校スパイダーず、岡山大学田中さんと桐生さん(松井先生代読)は簡単に紹介します。詳しくはこちらをご覧ください。
http://okayama-share.jp/cgi/web/?c=social_kiji-2&pk=381
シンポジウムの総合司会を岡山高校 スパイダーずの4人が務めてくれました。
冒頭食品ロスの概要について 山陽新聞社 岡山氏(論説委員会主幹)より情報提供がありました。 日本は食糧の輸入率が世界で一番高く62%(カロリーベース)、内570万トンを食品ロスとして捨てている。(輸入して捨てる国) この廃棄による温室効果ガスの割合は8~10%、最近話題となっている航空機の運航により排出される量1%と比較すると大変大きな数字となっている。
同じくモデレーターのSDGsネットワークおかやま 石原会長からは、フードロスが関係するSDGsの目標についての説明がありシンポジウムがスタートしました。
目標12 つくる責任使う責任 12.3食品廃棄を一人当たり半減させ、生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 12.5廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により廃棄物の発生を大幅に削減する。
目標2 飢餓をゼロに 2.1 飢餓を無くし、特に貧困層ならびに幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分に得られるようにする。 2.2 5歳未満の子どもの発育障害、消耗症(2025年までの目標達成に)ならびに若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズに対処。
目標1 貧困を無くそう 1.2各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある全ての年齢、男性、女性、子供の割合を半減させる。
登壇者のトップとして ハローズ太田氏がハローズモデルと呼ばれる同社の活動ならびにこれから強化していきたい「コミュニティパントリー(地域食品庫)」についての説明がありました。
ハローズモデルは、食品を必要とされる団体が直接ハローズ各店舗に赴くことで賞味期限内の食品を無料で受け取る仕組みで、同業者や取引先にも広く進めておられ、第6回 食品産業もったいない大賞(2019)、 内閣府子どもの未来応援国民運動HP掲載(2020)に加え、食品ロス削減推進大賞受賞(2020)という受賞歴があります。この取り組みは、企業視点で見ると廃棄処分コストの削減にもつながり、双方にメリットのある取り組みでもあります。
困窮者を対象に、地域で行われる子ども食堂の活動では、30%ほどしか救済できていないので、そこを補う形としてピンポイントで食品を提供し役割を果たせる「地域食品庫」を広めたい。
「コミュニティパントリー(地域食品庫)」とは、聞きなれない言葉ですが、日本で初めてできた公共の冷蔵庫(岡山市北長瀬駅隣接)「コミュニティフリッジ」が商標登録されたために勝手に使えないとのことで、フィリピンで普及しているこの名称を使って進めていこうとしています。
「困窮者にピンポイントで食品を提供する仕組み」は既に北長瀬コミュニティフリッジで出来上がっていて、運搬は食品物流の日本アクセス、岡山水急 食品保管の冷蔵庫はフクシマガリレイが提供してくれます。
県外でもこの動きが始まっていて 愛媛県新居浜市と西条市で eえひめフードバンク笑顔、神石高原町(広島県)、あこう子ども食堂(兵庫県)、ジャパンフードバンクリンク:留学生対象(福山市)、オアシス丸亀(香川)がすでに実施。今後は3月6日から倉敷市、高松市 さくらや(制服リユースショップ)、福山中央ライオンズクラス シングルマザー対象、吉備中央町 フードシェアリングジャパン(提案中)などが展開予定。 困っている人しか鍵が開けられないとシステムなのでピンポイントでお助けができる。
ここからは、企業としてのフードロス削減の数値を紹介。5年間で0.25%削減が出来、金額は4億円、救われた食品の重量は400トン。おむすびの廃棄率4%が1%にまで削減できている。
先日消費者庁で話をしたが、現在販売金額40位のハローズより上位の企業37~38社はフードロス削減の取り組みが弱い。40位の企業が150トン1.5億円の提供をしているので、上位企業が取り組めば単純計算で6000トン、60億円の食品が有効に活用される。
「善きサマリア人の法」がない日本(受けわたした商品の責任は受け取った側にある。)最近ニュージーランドでも同じような法律が制定され、急速に広まった事実がある。これまで、フードバンク岡山と取り組む際には提供後の商品の責任はそちらで持って欲しいとの合意で行っており、これまで7年間提供してきてクレームはゼロ。簿価ゼロなので会社の損失もない。ネームバリューは上がるのみ。大手の取り組みを期待する。
次に 供給側と需要側の間を取り持ち、食品を届ける役割をされている フードシェアリングジャパン代表 成田 賢一氏 自己紹介では、イギリス人のジャーナリストが名付けてくれた「食料困窮活動家」(Food Poverty Activist)として活動。本業は、㈱ケンジャミンフランクリンで移動販売スーパーやベルネーゼ(レストラン)を営み、吉備中央町町会議員としても務めている。個人の活動として、令和3年度消費者庁食品ロス削減大賞 長官賞を受賞と紹介後、世界の食品ロスを有効活用する取り組みと自分の活動を紹介されました。
食品を提供する活動として、早朝より、事業者に引き取りに行き、必要とするところへ届け、9時には自社の商店を開店している。今日は、4時~ハローズ岡南店でパン引き取り、江崎店回り、真備に届けてきた。
フードバンク数は国内では151団体、イギリスは2000,フランス2180,ドイツ947ある、食品提供活動の名称も各国で様々なものが使われている。フードシェアリング、フードリカバリー、フードサルベージ、フードドライブ、フリーフリッジ、フードシェアリング、サポーターズフードバンクなど。イギリスではコミュニティフリッジの名称で500を超えて運営されている。日本ではそれが商標登録されていて、誰もが自由に使えなくなっていることを残念と感じる。(と、ハローズ 太田氏と異口同音の発言がありました)
オーストラリアでは、OZ(オズ)ハーベストが無料スーパーを運営している。 イギリスではサポーターズフードバンクという活動で、サッカープレミアリーグのサポーターが試合前に集めている。日本でも食品ロス削減活動をさらに広めたい。できる範囲や出来ることを取り組む。やればできる。
モデレーターの岡山氏は、「誰が食品を取りに行くのか?」がカギだったが、成田氏の配達活動を重要な存在と説明しました。続いて、事前ワークショップでも登壇した 倉敷市でネイルサロンを営みながら、コロナ禍で16の飲食店で余った食材を利用し、缶詰をつくり、提供している「コノヒトカン(肉・魚) プロジェクト」三好さんが活動を紹介しました。 貧困・孤立とフードロスを解消するために始めた活動です。
缶詰のレシピづくりに20名のシェフが協力してくれており、ロス食材を生かしシェフが料理をする。子どもたち自らが2合のご飯と混ぜ調理をする。食について考える機会を提供するという思いが詰まった缶詰です。35名の子どもに19合のご飯と10缶を提供したら完食をしてくれました。2021年は1000缶をつくり、2022年は2000個を目指すとしています。教材としての活用を合わせて行います。
続いて、最後のパネラー NPO法人フードバンク岡山 糸山 智栄氏の発表。20212年廃棄物工学研究所からの声掛けを機にスタート。 倉庫・事務所・個人宅配の3無い でスタート。生協からは年間260日野菜を中心に受取り、ハローズとの取組は当初店長会議で店長が持ち寄ったものをもらうことからスタートして、現在のハローズモデルに行きついています。
近いうちに瀬戸内食品ロス削減団というタイトルで、岡山でフードバンク活動をしている団体を紹介した書籍を発行予定。トラック協会から順正学園、農協、生協、森林組合、中学校、大学サークル、高校生学童保育支援などを紹介します。
これまで活動してきた中で、糸山さんが感じる“もやもや”は、タンパク質源がなかなか来ない。食べる人が栄養を考えて、自分で選べるようになると良い。ハローズ太田さんによると豆腐、納豆、青果が多くなる傾向。1日1団体の受付としているので、自社だけで不足する面もあるので、他スーパーにも声をかけている。マッチングに問題がどうしても生じてしまうとの話です。
・食品ロスのマッチングについて研究している岡山大学 桐生さんが研究を発表。(事前ワークショップでは、指導教官の松井先生が紹介)。食品ロスの提供先は、福祉施設(障がい、高齢、児童)よりも困窮世帯の方が、マッチング率が高くなると紹介しました。
・マッチングアップの方策として岡山氏から、量のマッチングだけでなく、質のマッチングが必要であること。太田氏からは渡す側から受け取った側に責任が転換する「良きサマリア人法」を市町村単位で条例をつくり、実施できれば良い。 成田氏からは、アイルランドのフードアプリでは、提供側が重量を表示し、需要側がそれを見て引き取りすることもあると紹介がありました。糸山氏からは、倉庫の整備やアプリ開発よりもコーディネイトする人に給料(アルバイト時給)が出れば、もっと広がっていくとの指摘がありました。
・事前ワークショップで食品ロス削減の啓蒙活動を紹介したエコマインドネットワーク 赤井さんは、出前講座で小学校や公民館で行っていること。そのために、啓蒙DVDを制作したこと、もったいないキッチン、0円キッチンなどの映画上映会も実施していることを発表しました。私たちは、賞味期限や消費期限に囚われすぎている。買い物で食品を選ぶ際は、棚に欠品があっても「食品ロスを出さない店」として評価すべき、DVDにもこの内容を盛り込んでいる。
赤井さんに続いて、食品ロス削減に取り組む団体の発表がありました。
・一宮高校ユネスコ部は、店での食べ残しを持ち帰るドギーバッグについて紹介。自己責任カードを用意して店側に提示すると良い。調査では店が持ち帰り容器を有料で販売しても90%の客は持ち帰ると答えた。 成田氏は、店側からの声掛けがあると良いとの意見も付け加えました。ドギーバッグの新名称を「モッテコ(mottECO)」に消費者庁が変更したとの太田氏の情報提供もありました。
・ハローズでは、おにぎりの納品回数を1日2回にしたことで、4%のロスが1%に削減できた。合わせて少量パックを販売し、ロスが出ない対策を実施。賞味期限についての割引販売では、1カ月を切ったら20%オフ、3週間で40%オフ、2週間前になると店頭から撤去という方法でロス削減策を実施。
・岡山高校スパイダーずは夏休みに学童保育で糸山さんと知り合い、動画を作成しオンラインイベント フードロス✕学童保で全国1200人の子ども達にフードロスを伝え、無くすための行動宣言を書いてもらったと報告がありました。フードロス映画の上映やコノヒトカンプロジェクトの広報を手伝っています。
・岡山大学食品ロス大作戦 田中 朱音さん 農水、環境、経産省や30自治体の食品ロスデータを集め、ヒヤリング調査を実施し、岡山県と岡山市にパブリックコメントを提出し、県とは意見交換も行った。
・指導教官の松井准教授からは、岡山県の食品ロスは8.9万トン/年 243トン/日。困窮者支援のボランティアに頼るだけでなく、余剰食品の割引販売を行う方法もある。姫路市ではタベスケというアプリを活用し、短時間で消費者が利用できるしくみがある。食品ロスは管理コストが発生し、受益者の費用負担が発生する。県民全員が参加できるようにすると共に、生活困窮者には無償提供するか寄付付きで負担を無くして食品が手に入るようにするという提案がありました。
パネラー、モデレーターのまとめとして
・コミュニティパントリーの普及拡大を図り、ひとり親世帯の生活困窮者でかつ親と同居する人への支援を強化したい。太田氏
・食べ残しをしない。友人に伝えて、情報活動を共有する。メディアに多く取り上げて欲しい。成田氏
・若い人たちの食品ロス削減の活動が心強い。トップランナー方式で良いことを広め、行政で取り上げて欲しい。糸山氏
・フードロスが共通言語となっている。若い人の取り組みと共に県民全員参加の機運を盛り上げていきたい。岡山は食品メーカーが多く、食品ロスが多い。PLO法の関係で食品ロスは発生する(善きサマリア人の法の条例制定などで)がなんとかしなければならない。食品ロス削減は、量と質のマッチングが必要。
岡山県がマッチングシステム構築の予算を2022年度に確保している、これを、マッチングアプリに使うだけでなく、管理するパートタイマーの費用にも充てて欲しい。
個人の購買時は、賞味期限や欠品に寛容になって欲しいと岡山氏が締めくくりました。

- OKAYAMA Share project ~おかやまをシェアしよう~ イベントレポート
誰もが社会を変えられる。 そんな可能性を、シェアしよう。
「OKAYAMA Share project」は、岡山..