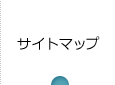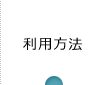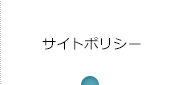タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
- OKAYAMA Share project ~おかやまをシェアしよう~ イベントレポート
- Social Good School !! 「Good」をもっと知ろう! イベントレポート
- 未来を生き抜く力を育む「野山の学校」開校
- (2013年11月6日)岡山発、新しい“協働”の形「災害時における 宗教施設のあり方を考えるセミナー」
- 農山村や暮らしとビジネスとの交流会 イベントレポート
- 子育て中親御さん、教育現場・対人サービス業の方へ
- 美作市で開催された地域活性化講演・発表会に参加しました!
- budding company fiesta
- 会議が変わると社会が変わる!? ファシリテーション講座に潜入してみた。
- 地域自主組織と小規模多機能自治を考える @地域力研修
山陽新聞連続シンポジウム 「エネルギーの地産地消について考える」レポート
イベント・セミナー環境
今日は、こんにちは、ゆうあいセンターCSR相談員 小桐です。
先日5月16日に開催された 山陽新聞社連続シンポジウム SDGs地域課題を探る の第2回目「エネルギーの地産地消」のご紹介です。詳細は、2021年5月29日の朝刊で報道されます。
ここでは、一足先にご紹介します。 発言が理解しやすいように一部表現を変えています。ご容赦ください。
当日は、コロナウイルス感染対策のため、オンラインで開催となりました。
1週間程度はその模様を動画で見ることができます。2時間みっちりのシンポジウムです。
https://c.sanyonews.jp/release/2021/04/20210409154620.html
このイベントは、SDGsネットワークおかやま 石原会長と山陽新聞社 編集委員室長 岡山 氏がモデレーターとして進行を務め、以下の3氏が地元でエネルギーの地産地消に関わる代表として参加しました。
津山商工会議所会頭・美作国電力社長 松田 欣也氏、岡山県西粟倉村地方創生特任参事 上山 隆浩氏、エネミラ ユースチーム 大同 唯和氏(操山高校)
シンポジウム開催にあたり 石原氏は、菅政権がこれまでの2030年 26% CO2削減(2013年比)を 46%まで減らすとして表明しており、人の暮らし、移動に必要なエネルギーをどう作り、どう使うかがこれから重要。
と話し、エネルギーに関するSDGs目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」のターゲットを紹介しました。
目標達成の期限である2030年までに
①クリーンに安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを保障する
② 世界の再生可能エネルギーを大幅に増やす。
③ エネルギーミックスによって、その効率を倍増させる。
④ 世界の協力によって①②を進めるとともにクリーンエネルギ―の技術やインフラの投資を増やす
⑤ 特に後開発途上国、小島嶼国、内陸国へのエネルギー提供ができるように技術開発と投資をする
岡山氏からは、連続シンポジウム前回シリーズと本シリーズの関連の紹介と主旨を語りました。
東京一極集中を避けて、いかに地方が持続可能になるかを考えた。地域の経済循環を高めることが、持続可能性を高めることにつながる。エネルギーが消費支出のポイント。外国に流れるお金をいかに地元で回るようにするか。新たな発想の転換につなげていきたい。
最初のパネラーは、認定NPO法人おかやまエネルギーの未来を考える会(以下エネミラ) ユースチームに所属する高校生 大同さん。 (以下大同Pと表記、他のパネラーは苗字Pで表記、モデレーターはMで表記)。
「若者の声を聞いてください」と自分たちの活動を紹介しました。
・市民共同発電所の設置など、再生可能エネルギー導入拡大にむけた活動を行っている。
・ユースチームは、2019年12月に結成され、中学生~大学生迄が参加している。発足のきっかけは、その前月に岡山で開催された全国市民共同発電所フォーラムに若者が参加したことだった。
エネルギーや気候変動問題に興味を持ち、大学生メンバーがイニシアティブを取って行動し始めた。
・再エネ100%の千葉商科大学への訪問や、岡山で期待される「ソーラーシェアリング」(農地に太陽光パネルを設置し、農業と発電の両方を行う)、西粟倉村の水力発電、バイオマス発電の視察も行い、勉強中。
・参加することで知識が広がり、行動に結び付きやすいが、学校教育現場はどういう状況かの疑問が湧き、岡山市内の中学校にアンケートを実施。
・回答のあった12校中5校は、太陽光パネルあるも実際は3か所のみ稼働。エネルギーや温暖化に関する総合学習や探究活動を行っているのは、3校だった。
・今年3月は「岡山の中高生で考える温暖化の今と未来」のセミナーを開催し、専門家よりオンラインで再エネの事を学び、長野県の高校生が関わった話も聞くことができた。
・2030年までにどうなっているべきか、何ができるかについても意見交換をし、ロードマップを作成。
・電気は「買うより創る時代」と分かった。 エネルギーは経済に直結。農地・耕作放棄地の再生と発電、太陽光パネル・太陽熱温水器の共同購入や中高校舎の未利用の屋根に太陽光パネルを設置などが貢献する。
・再エネ対策の実施やエネルギーシフトは生活を豊かにするという認識をもっと広める必要があると感じている。
・現状を知り、興味を持ってもらうために中高生向けのイベントが必要と考えている。
松田Pからは、若い人の意識が高い。ひとりひとりの意識を変えるための教育・啓蒙が重要。太陽光パネル設置に関しては、山林の乱開発に繋がらないようにしないといけない。などのフォローがありました。
2人目のパネラーは、西粟倉村の上山P
地域資源を活用した循環と地方創生を合わせて取り組んでいるとして内容の紹介がありました。
同村は、森林率が93%、内84%が人工林で占められている。50年放置された森に手を入れながら、50年間育て利用する百年の森構想をベースに、様々なプロジェクトを立ち上げ産業として整備し、お金の地域循環に取り組んでいる。用材に使えない木は20~30%。これを薪・チップにして木質バイオマスの熱エネルギーとして活用。地域熱供給システムを作りパイプラインで供給。村の3温泉施設は薪ボイラの燃料としても利用。このほか、
小型木質バイオマス自立発電も行っている。ウナギの養殖で冷水の温度を上げる利用も行っている。
このエネルギー活用により、木材の年間1800万円ほどのお金が地域で回っている。
ローカルベンチャー企業もどんどん増えて、2013年 8億円が2020年 21億円にも成長した。新規雇用創出221人。人口にも影響が出て、その減少幅を100人ほど食い止めている。30~40代と子どもの人口が増えている。「生きるを楽しむ」人が増え、持続性、経済性も高まっている。
昨年、視察をした大同Pからは、新しい事業もスタートしていてすごいと感じる。
松田Pからは、地域の資源・財産を増やすことが重要。エネルギーも生み出している。雇用、起業の内容が素晴らしい。地域内にお金が残っている。
県北では、人口流出が続く中1億円のローカルベンチャー100社が100億円の企業1社を誘致するよりも効果が高い。
岡山Mからは、島根県にある一般社団法人 持続可能な地域社会総合研究所 所長 藤山 浩氏が西粟倉村の取り組みを褒めているの情報提供。
石原Mからは、自立発電は、送電線が切れても孤立せず、災害対応にもつながる。バイオマス発電が村の中心?の質問には、現状水力発電の収入がバイオマス発電の収入より多く、収益を地域に還元しているとの回答がありました。
パネラー3人目は、美作電力の松田P。事業の説明をされました。2018年に津山市を中心に17団体で母体を形成し、エネルギーの地域循環の仕組みをつくっていく目的で設立。対象地域は、美作エリア 3市5町2村
エネルギーに使うお金が地域外に350億円流れている。これは、岡山北部エリアのGDPでいうと4.2%にあたる。この流れを変えようと2030年までに20億円の売り上げを目指している。地域還元に1%を使うと1億1600万円の経済効果が出ることが分かっている。
3期目は、売上1億7900万円 9452MWHの発電を行った。スーパーマルイ6店舗の屋根にオフグリッドの太陽光パネルを設置し、PPA(電力販売計画)を結び電力供給を3月から開始した。今後高騰が予想荒れる再エネ賦課金の影響を受けない。地域でできる電源調達のことをアピールすべくイベントを計画したがコロナ禍で中止となった。今後、環境教育・意識啓蒙が必要と考えている。
この発表を受けて、上山Pから自治体と美作国電力の包括連携協定サービスを締結したことで、キャッシュアウト(漏れバケツ)を減らすことが出来る。地域の中で20%のお金が4回転するのと80%のお金が4回転するのでは相当差が開く。労働分配率が高くなる。エネルギーでの経済循環が一番規模が大きく、効果が出ると考えていると発言がありました。
大同Pは、美作国電力の存在は知っていたが、地域とのつながりや仕組みの事は知らなかった。
付け加えとして松田Pから、計画は順調、今は17の個々の企業・団体の支援で成り立っているが、今後シミ人にもオープンにして、広く告知する予定と説明がありました。
この後は石原Mからテーマを出して、議論を深めていきました。
Ⅰ.教育の事
事前ワークショップでは、環境についての知識を得るための教育不足が挙げられ、再エネ価格の高さ、安定供給などについて教えられる専門的な人を増やす必要があるという意見が出た。
これについて、大同Pは、学校では全員が授業を受けることの意味がある。現状を知ることは重要。環境に関して興味を持つきっかけ作りで学校教育に取り入れて欲しい。専門の先生はいない。外部講師に依頼する。教師が教える必要がなく、生徒が地域の人と協力して学び教師に教えることで良い。地域との橋渡し役で機能してくれればよい、オンラインで地域外の人からも教えてもらうことができる。
・松田Pからは、岡山県の企業がどう考えるか?企業で教育をすれば家庭の教育で考えることにつながる。津山商工会議所では「ローカルファースト」による持続可能な地域経済循環型の大切さを学んでいる。
・家庭で親とエネルギーの話をするかの質問に大同Pは、自分は話をするけど、関わっていない人はそれができない。親の知識が問われる。若者から親を教育する方向性が考えられる。
・西粟倉村では、児童生徒にどんな教育を行っているか?について上山Pは、環境だと制約がある。いかに楽しく学ぶか 教師ではなく生徒が主体的に学ぶ。村には環境教育を行う一般社団法人があり、学校と家庭の間に立って取り組みをする活動をしている。
・岡山Mからは、真庭市中和小の教育では、木質バイオマスボイラが地域にあり、エネルギーの事と地域循環の事を学んでいるとの紹介がありました。
Ⅱ.新型コロナウイスルの感染拡大で緊急事態宣言が出されたwithコロナの時代 はエネルギーにどう関係するか?
・上山P:自分でエネルギーを創り出すことが重要になってきている。気候変動への対応のために今までの安定は続かないかもしれない。個人・地域のレジリエンスがエネルギーについても高める必要がある。
・松田P:エネルギーは、買うから創る の転換が始まっている。再エネ賦課金の上昇で電力単価は上がっている。オフグリッドPPAモデルをマルイ6店舗で実験を開始した。91万KWHを創ることにしている。
石原M:コロナの影響で家庭電力の消費は増えた、電気自動車普及で電力ニーズも増える。一方移動の減少などでCO2排出は減った。しかし、ゴミが増える。 災害支援にも地域を超えていけないという影響が出ている。
このような状況下で
Ⅲ.エネルギーシフトの対応について 国や県など行政に対する意見は?
・大同P:高校生としての思いは、目標数字はあっても、具体的な内容が伝わらない。何をどうする、どのようにするかのスキームを積極的に提示すべき、それがあれば市民にも伝わる。
・高校生としての政治へのアプローチは?
大同P;海外と日本は違う。学校でストライキはできない。日本では、政治に対しての興味が低い。教育の在り方にも問題があり、家庭や学校の場で環境やエネルギーに関して知る機会が少ない。
・松田P:国に対して発言したい。自然エネルギーエネルギー支援施策が分かりにくい。伝わって来ない。民間企業は自らがアンテナを高くしておかないと情報が入ってこない。市民にも伝わらない。
エネルギーシフトのアピールについては、マルイフードフェスタや地域循環バス5台に5つのSDGsテーマを書いたラッピングバスを走らせている。美作国電力を使ったライトアップを計画していたが、今回のコロナ禍で中止となった。津山市とはマルイと連携して、子育て・定住支援 2つのプランの包括協定を結びサービスを提供する。
企業も地元の電力を使って欲しい。
・上山P:地域としては事業の費用対効果(BVC)についての見直しをして欲しい。小さな中山間地は自然エネルギーのポテンシャルは高いが効果が少ないと思われがち。低炭素とレジリエンスを高めるには中山間地への支援を手厚くして欲しい。3年では自立は難しい。カーボンオフセットを取り入れるべき。山を切り開いて、太陽光パネルを付けるというようなことへの支援はないだろう。必要・十分な要素を踏まえた指標で判断して欲しい。
Ⅳ.事業者や企業、家庭で取り組めることは?
・松田P:機会があることが重要。昔は意識もしなかったゴミ分別が今は当たりまえ。マルイは計量してごみを出している。リサイクルする際もその資源の再利用料も計測。社員の意識変化は家庭にも影響する。さh会貢献の数値化がでると家庭にも良い影響がある。
・上山P:中山間地の山主は、都会などに住む地域部外者が多い。もっと山に興味を持って欲しい。利用したいが権利がなく、相続問題で管理放棄されると手入れができなくて困る。山の利活用をやりたい人はいるので、シェアリングして活動ができる。雇用にもつながるので資源管理の重要性を認識して欲しい。
・大同P:学校でゴミ分別を意識すると家庭での行動にも繋がる。2030年、2050年は自分達が社会の中心となっている。今の大人は2050年に無関心。今が将来につながることを認識して欲しい。
Ⅴ.2030年には、46%のCO2削減を達成しなければいけない、気候変動に大きな影響が出る。パネラーが
考える未来像は?
・松田P:未来を生きる人のしあわせ・豊かさの価値観が変わってもしっかり未来世代のためにつながることを考えたい。
・上山P:心の豊かさが見える社会になって欲しい。多様な人たちが集まって住んで、年齢を重ねても地域の誰かとつながっている心の指標。
・大同P:2030年、2050年に後悔しないためのできることを今から行っていき、その次の世代へバトンタッチが出来たらよい。
・石原M:今日はエネルギーの地産地消に関しての取り組みの紹介と問題点の共有をした。解決策はみんなで考え行動にしたい。
・岡山M:本日のまとめ 昭和・平成は大量生産・大量消費の時代だった。これは、化石燃料がベースとなっていた。今、それが行き詰まり、エネルギー問題となっている。政府は、2030年温室効果ガス 26%(2013年比)削減目標を46%削減に増やす発言をした。環境問題は、これまで規制が中心だった、今後は経済問題になる。エネルギー代が外国に流れる「漏れバケツ」を減らす。ローカルファーストと
先日5月16日に開催された 山陽新聞社連続シンポジウム SDGs地域課題を探る の第2回目「エネルギーの地産地消」のご紹介です。詳細は、2021年5月29日の朝刊で報道されます。
ここでは、一足先にご紹介します。 発言が理解しやすいように一部表現を変えています。ご容赦ください。
当日は、コロナウイルス感染対策のため、オンラインで開催となりました。
1週間程度はその模様を動画で見ることができます。2時間みっちりのシンポジウムです。
https://c.sanyonews.jp/release/2021/04/20210409154620.html
このイベントは、SDGsネットワークおかやま 石原会長と山陽新聞社 編集委員室長 岡山 氏がモデレーターとして進行を務め、以下の3氏が地元でエネルギーの地産地消に関わる代表として参加しました。
津山商工会議所会頭・美作国電力社長 松田 欣也氏、岡山県西粟倉村地方創生特任参事 上山 隆浩氏、エネミラ ユースチーム 大同 唯和氏(操山高校)
シンポジウム開催にあたり 石原氏は、菅政権がこれまでの2030年 26% CO2削減(2013年比)を 46%まで減らすとして表明しており、人の暮らし、移動に必要なエネルギーをどう作り、どう使うかがこれから重要。
と話し、エネルギーに関するSDGs目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」のターゲットを紹介しました。
目標達成の期限である2030年までに
①クリーンに安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを保障する
② 世界の再生可能エネルギーを大幅に増やす。
③ エネルギーミックスによって、その効率を倍増させる。
④ 世界の協力によって①②を進めるとともにクリーンエネルギ―の技術やインフラの投資を増やす
⑤ 特に後開発途上国、小島嶼国、内陸国へのエネルギー提供ができるように技術開発と投資をする
岡山氏からは、連続シンポジウム前回シリーズと本シリーズの関連の紹介と主旨を語りました。
東京一極集中を避けて、いかに地方が持続可能になるかを考えた。地域の経済循環を高めることが、持続可能性を高めることにつながる。エネルギーが消費支出のポイント。外国に流れるお金をいかに地元で回るようにするか。新たな発想の転換につなげていきたい。
最初のパネラーは、認定NPO法人おかやまエネルギーの未来を考える会(以下エネミラ) ユースチームに所属する高校生 大同さん。 (以下大同Pと表記、他のパネラーは苗字Pで表記、モデレーターはMで表記)。
「若者の声を聞いてください」と自分たちの活動を紹介しました。
・市民共同発電所の設置など、再生可能エネルギー導入拡大にむけた活動を行っている。
・ユースチームは、2019年12月に結成され、中学生~大学生迄が参加している。発足のきっかけは、その前月に岡山で開催された全国市民共同発電所フォーラムに若者が参加したことだった。
エネルギーや気候変動問題に興味を持ち、大学生メンバーがイニシアティブを取って行動し始めた。
・再エネ100%の千葉商科大学への訪問や、岡山で期待される「ソーラーシェアリング」(農地に太陽光パネルを設置し、農業と発電の両方を行う)、西粟倉村の水力発電、バイオマス発電の視察も行い、勉強中。
・参加することで知識が広がり、行動に結び付きやすいが、学校教育現場はどういう状況かの疑問が湧き、岡山市内の中学校にアンケートを実施。
・回答のあった12校中5校は、太陽光パネルあるも実際は3か所のみ稼働。エネルギーや温暖化に関する総合学習や探究活動を行っているのは、3校だった。
・今年3月は「岡山の中高生で考える温暖化の今と未来」のセミナーを開催し、専門家よりオンラインで再エネの事を学び、長野県の高校生が関わった話も聞くことができた。
・2030年までにどうなっているべきか、何ができるかについても意見交換をし、ロードマップを作成。
・電気は「買うより創る時代」と分かった。 エネルギーは経済に直結。農地・耕作放棄地の再生と発電、太陽光パネル・太陽熱温水器の共同購入や中高校舎の未利用の屋根に太陽光パネルを設置などが貢献する。
・再エネ対策の実施やエネルギーシフトは生活を豊かにするという認識をもっと広める必要があると感じている。
・現状を知り、興味を持ってもらうために中高生向けのイベントが必要と考えている。
松田Pからは、若い人の意識が高い。ひとりひとりの意識を変えるための教育・啓蒙が重要。太陽光パネル設置に関しては、山林の乱開発に繋がらないようにしないといけない。などのフォローがありました。
2人目のパネラーは、西粟倉村の上山P
地域資源を活用した循環と地方創生を合わせて取り組んでいるとして内容の紹介がありました。
同村は、森林率が93%、内84%が人工林で占められている。50年放置された森に手を入れながら、50年間育て利用する百年の森構想をベースに、様々なプロジェクトを立ち上げ産業として整備し、お金の地域循環に取り組んでいる。用材に使えない木は20~30%。これを薪・チップにして木質バイオマスの熱エネルギーとして活用。地域熱供給システムを作りパイプラインで供給。村の3温泉施設は薪ボイラの燃料としても利用。このほか、
小型木質バイオマス自立発電も行っている。ウナギの養殖で冷水の温度を上げる利用も行っている。
このエネルギー活用により、木材の年間1800万円ほどのお金が地域で回っている。
ローカルベンチャー企業もどんどん増えて、2013年 8億円が2020年 21億円にも成長した。新規雇用創出221人。人口にも影響が出て、その減少幅を100人ほど食い止めている。30~40代と子どもの人口が増えている。「生きるを楽しむ」人が増え、持続性、経済性も高まっている。
昨年、視察をした大同Pからは、新しい事業もスタートしていてすごいと感じる。
松田Pからは、地域の資源・財産を増やすことが重要。エネルギーも生み出している。雇用、起業の内容が素晴らしい。地域内にお金が残っている。
県北では、人口流出が続く中1億円のローカルベンチャー100社が100億円の企業1社を誘致するよりも効果が高い。
岡山Mからは、島根県にある一般社団法人 持続可能な地域社会総合研究所 所長 藤山 浩氏が西粟倉村の取り組みを褒めているの情報提供。
石原Mからは、自立発電は、送電線が切れても孤立せず、災害対応にもつながる。バイオマス発電が村の中心?の質問には、現状水力発電の収入がバイオマス発電の収入より多く、収益を地域に還元しているとの回答がありました。
パネラー3人目は、美作電力の松田P。事業の説明をされました。2018年に津山市を中心に17団体で母体を形成し、エネルギーの地域循環の仕組みをつくっていく目的で設立。対象地域は、美作エリア 3市5町2村
エネルギーに使うお金が地域外に350億円流れている。これは、岡山北部エリアのGDPでいうと4.2%にあたる。この流れを変えようと2030年までに20億円の売り上げを目指している。地域還元に1%を使うと1億1600万円の経済効果が出ることが分かっている。
3期目は、売上1億7900万円 9452MWHの発電を行った。スーパーマルイ6店舗の屋根にオフグリッドの太陽光パネルを設置し、PPA(電力販売計画)を結び電力供給を3月から開始した。今後高騰が予想荒れる再エネ賦課金の影響を受けない。地域でできる電源調達のことをアピールすべくイベントを計画したがコロナ禍で中止となった。今後、環境教育・意識啓蒙が必要と考えている。
この発表を受けて、上山Pから自治体と美作国電力の包括連携協定サービスを締結したことで、キャッシュアウト(漏れバケツ)を減らすことが出来る。地域の中で20%のお金が4回転するのと80%のお金が4回転するのでは相当差が開く。労働分配率が高くなる。エネルギーでの経済循環が一番規模が大きく、効果が出ると考えていると発言がありました。
大同Pは、美作国電力の存在は知っていたが、地域とのつながりや仕組みの事は知らなかった。
付け加えとして松田Pから、計画は順調、今は17の個々の企業・団体の支援で成り立っているが、今後シミ人にもオープンにして、広く告知する予定と説明がありました。
この後は石原Mからテーマを出して、議論を深めていきました。
Ⅰ.教育の事
事前ワークショップでは、環境についての知識を得るための教育不足が挙げられ、再エネ価格の高さ、安定供給などについて教えられる専門的な人を増やす必要があるという意見が出た。
これについて、大同Pは、学校では全員が授業を受けることの意味がある。現状を知ることは重要。環境に関して興味を持つきっかけ作りで学校教育に取り入れて欲しい。専門の先生はいない。外部講師に依頼する。教師が教える必要がなく、生徒が地域の人と協力して学び教師に教えることで良い。地域との橋渡し役で機能してくれればよい、オンラインで地域外の人からも教えてもらうことができる。
・松田Pからは、岡山県の企業がどう考えるか?企業で教育をすれば家庭の教育で考えることにつながる。津山商工会議所では「ローカルファースト」による持続可能な地域経済循環型の大切さを学んでいる。
・家庭で親とエネルギーの話をするかの質問に大同Pは、自分は話をするけど、関わっていない人はそれができない。親の知識が問われる。若者から親を教育する方向性が考えられる。
・西粟倉村では、児童生徒にどんな教育を行っているか?について上山Pは、環境だと制約がある。いかに楽しく学ぶか 教師ではなく生徒が主体的に学ぶ。村には環境教育を行う一般社団法人があり、学校と家庭の間に立って取り組みをする活動をしている。
・岡山Mからは、真庭市中和小の教育では、木質バイオマスボイラが地域にあり、エネルギーの事と地域循環の事を学んでいるとの紹介がありました。
Ⅱ.新型コロナウイスルの感染拡大で緊急事態宣言が出されたwithコロナの時代 はエネルギーにどう関係するか?
・上山P:自分でエネルギーを創り出すことが重要になってきている。気候変動への対応のために今までの安定は続かないかもしれない。個人・地域のレジリエンスがエネルギーについても高める必要がある。
・松田P:エネルギーは、買うから創る の転換が始まっている。再エネ賦課金の上昇で電力単価は上がっている。オフグリッドPPAモデルをマルイ6店舗で実験を開始した。91万KWHを創ることにしている。
石原M:コロナの影響で家庭電力の消費は増えた、電気自動車普及で電力ニーズも増える。一方移動の減少などでCO2排出は減った。しかし、ゴミが増える。 災害支援にも地域を超えていけないという影響が出ている。
このような状況下で
Ⅲ.エネルギーシフトの対応について 国や県など行政に対する意見は?
・大同P:高校生としての思いは、目標数字はあっても、具体的な内容が伝わらない。何をどうする、どのようにするかのスキームを積極的に提示すべき、それがあれば市民にも伝わる。
・高校生としての政治へのアプローチは?
大同P;海外と日本は違う。学校でストライキはできない。日本では、政治に対しての興味が低い。教育の在り方にも問題があり、家庭や学校の場で環境やエネルギーに関して知る機会が少ない。
・松田P:国に対して発言したい。自然エネルギーエネルギー支援施策が分かりにくい。伝わって来ない。民間企業は自らがアンテナを高くしておかないと情報が入ってこない。市民にも伝わらない。
エネルギーシフトのアピールについては、マルイフードフェスタや地域循環バス5台に5つのSDGsテーマを書いたラッピングバスを走らせている。美作国電力を使ったライトアップを計画していたが、今回のコロナ禍で中止となった。津山市とはマルイと連携して、子育て・定住支援 2つのプランの包括協定を結びサービスを提供する。
企業も地元の電力を使って欲しい。
・上山P:地域としては事業の費用対効果(BVC)についての見直しをして欲しい。小さな中山間地は自然エネルギーのポテンシャルは高いが効果が少ないと思われがち。低炭素とレジリエンスを高めるには中山間地への支援を手厚くして欲しい。3年では自立は難しい。カーボンオフセットを取り入れるべき。山を切り開いて、太陽光パネルを付けるというようなことへの支援はないだろう。必要・十分な要素を踏まえた指標で判断して欲しい。
Ⅳ.事業者や企業、家庭で取り組めることは?
・松田P:機会があることが重要。昔は意識もしなかったゴミ分別が今は当たりまえ。マルイは計量してごみを出している。リサイクルする際もその資源の再利用料も計測。社員の意識変化は家庭にも影響する。さh会貢献の数値化がでると家庭にも良い影響がある。
・上山P:中山間地の山主は、都会などに住む地域部外者が多い。もっと山に興味を持って欲しい。利用したいが権利がなく、相続問題で管理放棄されると手入れができなくて困る。山の利活用をやりたい人はいるので、シェアリングして活動ができる。雇用にもつながるので資源管理の重要性を認識して欲しい。
・大同P:学校でゴミ分別を意識すると家庭での行動にも繋がる。2030年、2050年は自分達が社会の中心となっている。今の大人は2050年に無関心。今が将来につながることを認識して欲しい。
Ⅴ.2030年には、46%のCO2削減を達成しなければいけない、気候変動に大きな影響が出る。パネラーが
考える未来像は?
・松田P:未来を生きる人のしあわせ・豊かさの価値観が変わってもしっかり未来世代のためにつながることを考えたい。
・上山P:心の豊かさが見える社会になって欲しい。多様な人たちが集まって住んで、年齢を重ねても地域の誰かとつながっている心の指標。
・大同P:2030年、2050年に後悔しないためのできることを今から行っていき、その次の世代へバトンタッチが出来たらよい。
・石原M:今日はエネルギーの地産地消に関しての取り組みの紹介と問題点の共有をした。解決策はみんなで考え行動にしたい。
・岡山M:本日のまとめ 昭和・平成は大量生産・大量消費の時代だった。これは、化石燃料がベースとなっていた。今、それが行き詰まり、エネルギー問題となっている。政府は、2030年温室効果ガス 26%(2013年比)削減目標を46%削減に増やす発言をした。環境問題は、これまで規制が中心だった、今後は経済問題になる。エネルギー代が外国に流れる「漏れバケツ」を減らす。ローカルファーストと

- OKAYAMA Share project ~おかやまをシェアしよう~ イベントレポート
誰もが社会を変えられる。 そんな可能性を、シェアしよう。
「OKAYAMA Share project」は、岡山..