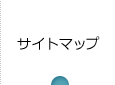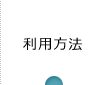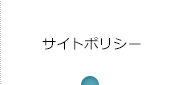タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
- OKAYAMA Share project ~おかやまをシェアしよう~ イベントレポート
- Social Good School !! 「Good」をもっと知ろう! イベントレポート
- 未来を生き抜く力を育む「野山の学校」開校
- (2013年11月6日)岡山発、新しい“協働”の形「災害時における 宗教施設のあり方を考えるセミナー」
- 農山村や暮らしとビジネスとの交流会 イベントレポート
- 子育て中親御さん、教育現場・対人サービス業の方へ
- 美作市で開催された地域活性化講演・発表会に参加しました!
- budding company fiesta
- 会議が変わると社会が変わる!? ファシリテーション講座に潜入してみた。
- 地域自主組織と小規模多機能自治を考える @地域力研修
SDGsフォーラム2020IN 岡山大学の紹介
イベント・セミナーその他
こんにちは、ゆうあいセンターの小桐です。 今日は、2月23日に行われたSDGsイベントをご紹介します。このイベントは、岡山市、岡山市教育委員会、岡山大学、岡山経済同友会、岡山ESDSDGsネットワークおかやま推進協議会の主催で行われました。岡山でSDGsの普及を推進する「SDGsネットワークおかやま」も協力団体として参加、石原会長がパネルディスカッションの進行役と子供に関する分科会の進行役を共同代表として務めました。
岡山大学創立五十周年記念館をメイン会場に開催され、300名ほどが参加したと報告されました。岡山大学、経済同友会の挨拶に続き、SDGs講演とおかやま協働のまちづくり賞の表彰式の他、YOUTH VOICES(岡山の若手のSDGsの取り組みや前日のイベント報告)、続いて午後からの分科会に向けて6進行団体より、パネルディスカッション形式で検討テーマの紹介がありました。以上午前中は盛りだくさんの内容でした。午後からは、6会場に分かれ、分科会での検討、最後に全体会で締めくくりました。
SDGs認知度調査で岡山県が全国1位だったとの報告がありました。経済団体、自治体含めたパートナーシップの由縁といわれていました。
基調講演では、広島大学 吉田和弘 教育開発国際研究センター長 「SDG4(教育)からみるSDGsの世界と岡山への期待」というテーマで話されました。国際開発の歴史(ユネスコ憲章、世界人権宣言、リオサミット、MDGs→SDGs)と世界の教育の歴史の説明をされました。2015年時点で世界で学校にいけない子供の人数が6000万人、SDGsでは、教育がすべてのカギとなっている。国内には世界の10%のユネスコスクールがあり、取り組みを進めている。日本の成功事例のポイントを世界に、相手に合わせて発信する必要があると結ばれました。
YOUTH VOICESでは、MY SDGsからOUR SDGsへと男女1名ずつの大学生、高校生が登壇。岡山JKnoteでの外国人労働者と料理を通じた交流・日本語教室の開催、フェアトレード商品の学習、販売などを通して、知ることで消費行動を変えていく取り組みの説明がありました。大学生からは、知って活動する人、知らずに活動をしない人の境界を少なくすることへの提言がありました。
協働のまちづくり表彰では、テーマが「すべての人に健康とやさしさを」で応募、審査が行われ、中区「なかまちーず」(なかくのなかまでなかくのまちづくり)の地域保健医療福祉連携活動が大賞、入選に「注文を間違えるレストラン;ルネストラン:認知症の方をやさしく支えられる地高校生を育てよう」、おかえり子供食堂カフェふらっと、とみやま助け合い隊、地域丸ごと健康づくりの活動が入賞しました。
個々の取り組みは、下記サイトをご覧ください。
http://www.okayama-tbox.jp/kyoudou/pages/18247
午後の分科会概要の紹介です。
1.「災害に備える ~だれもおきざりにしないために・どんな人にもやさしい避難所運営から考える~」(SDGsの目標11より) 被災し、避難所生活をしなければいけない事態になった時のことを考えて、ハード、ソフトの両面を考えていかなければならいない。真備地区で防災や復興支援に取り組む磯 打(香川大学地域強靭化研究センター准教授)さんが進行をされ、斎藤容子(関西学院大学災害復興制度研究所指定研究員)、避難所生活を体験された方、保健・公民館関係者からの話題提供がありました。
発表後に4人のキーワードを共有し、「伝える・協働・女性リーダー」、「自ら考え行動できる子供を育てたい」「信じて まかせる 勇気」「避難所運営に女性リーダーを」 1930年代の避難所と現在の状況が変わっていないと写真の比較で浮かび上がった事実もありました。 避難所では、誰も取り残さないように、皆に役割を与え、分担することが大切。これらの内容が全体会の報告でも共有されました。 特に避難所の運営は、男性が中心だが、女性の方が細かなニーズをもっており、女性リーダーの活躍が今後必要との声が印象的でした。
2.「多文化共生 ~地域に外国人市民が日本語を学び文化にふれる場を~」(SDGsの目標4より)
中東(岡山大学大学院社会科学研究科准教授)、岡山学芸館高等学校多文化共生ゼミ、城之内((一社)岡山に夜間中学校をつくる会理事長)、グェン キム リー(ベトナム出身、岡山大学経済学部生)の皆さんが話題提供をされました。リーさんが岡山に在住するベトナムからの労働者の声を伝えていました。日本語が勉強したいが、ボランティアさんの日本語は方言やスピード、日本語能力の問題で、日本語検定に直接参考とはなりにくい現実がある。また、岡山市では、外国人向けイベントが少なく、一緒に学べる地域での交流の場を求める声がある。
まとめとして、外国人むけの日本語教育は、ボランティアに頼っている現状があり、公的な支援が必要。ともに暮らす地域住民としてできることを考える。行政専門家との協力が必要などの意見が共有されました。
3.「自然と人の共生 ~森川里海のめぐみを2030へ~」(SDGsの目標14、15より)
三宅 (浅口市寄島漁業協同組合代表理事組合長)、小林(アユモドキを守る会)、山陽女子中学校・高等学校地歴部、里山保全活動団体・環境行政・公民館関係者などが参加し、6グループに分かれて、ワールドカフェスタイルでキーワードを挙げて議論しました。そこからのまとめとして、
・「教育」:学校、家庭、地域で教育をすることで、気づきの機会を提供し、環境を意識するようになることで、ポジティブに行動ができるようになる。
・時間と空間の広がりを持つ。働きかけをすることで、解決に向かうことが期待される。
・若い世代は2030年になると社会人として自分で行動できるようになる。 以上のように若い世代の行動をサポートする方向性が確認されました。
4.「再生可能エネルギー100%をめざして ~エネルギーの選択~」(SDGsの目標7より)
3名の方に話題提供いただき進行しました。中国四国地方環境事務所広島事務所長原田氏より、環境省が進める地域循環共生圏の創造と再生可能エネルギーについて。再エネの導入拡大による地域経済循環を創出するというものです。自治体出資のある地域新電力事業の紹介や横浜市と東北の12町村が連携した地域循環共生圏の協定の紹介などがありました。
持続可能なエネルギーと地域活性を結びつける西粟倉村の事例を同村の上山参事から、地域の木材資源や水資源の有効活用に関しての紹介、大学の自然エネルギー100%を目指す活動を推進する京都大学大学院 塚本悠平氏が事例や活動を紹介しました。千葉商科大学は既に自然エネルギー100%を達成している。龍谷大学にも、自然エネルギーの自家発電設備を整えている。
その後、参加者同士で意見交換を行い、分科会のまとめとして、以下の内容が発表されました。
・家庭や企業が契約している電力を再生可能エネルギー比率の高い電力会社に変更する。
・ライフスタイルを変更し、冷暖房など電力を使わないスタイルへシフトしていく。
5.「貧困と不平等、暴力をなくし、子どもたちが夢を抱き、何度でも挑戦できるおかやま地域を実現するために」(SDGsの目標1、10より)
3人の登壇者の発表概要です。
西﨑(NPO法人子どもシェルターモモ専務理事):家庭で暮らせなくなったこどもの緊急避難シェルターとして、教育虐待や家庭内暴力の被害を受けたこどもを受け入れているが、人手不足・資金不足の問題を常に抱えている。シングル家庭が増えることが予想される将来、支援を続けることは不可能。子どもを取り残さず夢を抱かせるには、より多くの資金、より多様な人手が必要。
中山(NPO法人あかね代表理事) :不登校・引きこもりの若者・子どもとその家族を支援。一般的に中学卒業や高校中退を機に公的な支援が途切れてしまうが、あかねでは年齢の切れ目を設けず、幅広い年齢層の人を受け入れている。し岡山市をはじめ全国での不登校児は増加しているのが現状岡山市は、小学生の不登校児数全国ワースト1位であるが、その認知度はかなり低い。学校以外の居場所を提供する民間団体の数も、資金不足のため減少し続けている。公的枠組みや、思いを持っている人を経済的に支える仕組みが不可欠。
小畠(NPO法人かものはしプロジェクト広報・ファンドレイジング):子どもが売られる問題をなくすために2002年から活動している。カンボジアで事業を始め、現在はインドで活動している。カンボジアでは、子どもの人身売買という問題の構造を把握し、対症療法ではなく根本原因にアプローチすることで問題解決に至った。寄付金総額の約7割が、一般のサポーター会員から月々少額を募っている寄付による。
次に、岡山の子ども支援に取り組む組織同士とそれを応援する人をつなぐ仕組みについて会場で検討をしました。
現状:子どもを支えるための様々なNPOがあるも、個々の組織がバラバラに寄付を集めることで結果的に寄付の奪い合いとなってしまっている。 解決のために、そこで、個々の組織を連結させ、合同の寄付受皿として「おかやま子ども基金(仮)」をつくることが提案されました。まず支援アライアンスの形成を行い、ファシリテーター役を担う。資金の使い道と配分の透明性を確保し、広報を行う。ふるさと納税と子ども基金の連携、寄付者へ分かりやすく効果を伝えること、資金を生み出す仕組みをつくる。この話し合いにより、個々のNPOのみが責任を負うのではなく、みんなの責任として取り組もうという気運が高まりました。
6.「まだ食べられるのに捨てるの?もったいない!~食品ロスを減らすために私たちができること
進行役をフードロス削減の啓蒙活動を熱心に行われている赤井(おかやまエコマインドネットワーク理事)さんが務め、以下3氏の話題提供が行われました。松井(岡山大学大学院環境生命科学研究科准教授)、三宅(生活協同組合おかやまコープ常務理事)、垣内(cafe&barどぅーず代表、岡山県喫茶飲食生活衛生同業組合副理事長) 発表後に、2つの課題についてグループに分かれて検討しました。①2030年にフードロスを50%削減するには ②食べ物に対して感謝の念・思いが伝わりにくい「フードロス」に代わるポジティブネーミング。
①については、消費者、流通業者、行政、社会制度などそれぞれのステークホルダーの立場からできることを抽出しました。予約販売、フェア、冷蔵庫のチェック、公民館でフードバンクのしくみの紹介、食品ロス削減のポイントなどの意見が出ました。②については、シンショクヒン、Re食品、エシカル食品、もったいない食品などのアイデアが出されました。
市民の間でも確実にSDGsの取り組みが定着し、認知が広まっています。自分事にして考え、できることから始めることが大切です。SDGsに関して知るには ゆうあいセンター 無料の講座やSDGsの情報コアーナー、相談窓口に気軽にご相談ください。
岡山大学創立五十周年記念館をメイン会場に開催され、300名ほどが参加したと報告されました。岡山大学、経済同友会の挨拶に続き、SDGs講演とおかやま協働のまちづくり賞の表彰式の他、YOUTH VOICES(岡山の若手のSDGsの取り組みや前日のイベント報告)、続いて午後からの分科会に向けて6進行団体より、パネルディスカッション形式で検討テーマの紹介がありました。以上午前中は盛りだくさんの内容でした。午後からは、6会場に分かれ、分科会での検討、最後に全体会で締めくくりました。
SDGs認知度調査で岡山県が全国1位だったとの報告がありました。経済団体、自治体含めたパートナーシップの由縁といわれていました。
基調講演では、広島大学 吉田和弘 教育開発国際研究センター長 「SDG4(教育)からみるSDGsの世界と岡山への期待」というテーマで話されました。国際開発の歴史(ユネスコ憲章、世界人権宣言、リオサミット、MDGs→SDGs)と世界の教育の歴史の説明をされました。2015年時点で世界で学校にいけない子供の人数が6000万人、SDGsでは、教育がすべてのカギとなっている。国内には世界の10%のユネスコスクールがあり、取り組みを進めている。日本の成功事例のポイントを世界に、相手に合わせて発信する必要があると結ばれました。
YOUTH VOICESでは、MY SDGsからOUR SDGsへと男女1名ずつの大学生、高校生が登壇。岡山JKnoteでの外国人労働者と料理を通じた交流・日本語教室の開催、フェアトレード商品の学習、販売などを通して、知ることで消費行動を変えていく取り組みの説明がありました。大学生からは、知って活動する人、知らずに活動をしない人の境界を少なくすることへの提言がありました。
協働のまちづくり表彰では、テーマが「すべての人に健康とやさしさを」で応募、審査が行われ、中区「なかまちーず」(なかくのなかまでなかくのまちづくり)の地域保健医療福祉連携活動が大賞、入選に「注文を間違えるレストラン;ルネストラン:認知症の方をやさしく支えられる地高校生を育てよう」、おかえり子供食堂カフェふらっと、とみやま助け合い隊、地域丸ごと健康づくりの活動が入賞しました。
個々の取り組みは、下記サイトをご覧ください。
http://www.okayama-tbox.jp/kyoudou/pages/18247
午後の分科会概要の紹介です。
1.「災害に備える ~だれもおきざりにしないために・どんな人にもやさしい避難所運営から考える~」(SDGsの目標11より) 被災し、避難所生活をしなければいけない事態になった時のことを考えて、ハード、ソフトの両面を考えていかなければならいない。真備地区で防災や復興支援に取り組む磯 打(香川大学地域強靭化研究センター准教授)さんが進行をされ、斎藤容子(関西学院大学災害復興制度研究所指定研究員)、避難所生活を体験された方、保健・公民館関係者からの話題提供がありました。
発表後に4人のキーワードを共有し、「伝える・協働・女性リーダー」、「自ら考え行動できる子供を育てたい」「信じて まかせる 勇気」「避難所運営に女性リーダーを」 1930年代の避難所と現在の状況が変わっていないと写真の比較で浮かび上がった事実もありました。 避難所では、誰も取り残さないように、皆に役割を与え、分担することが大切。これらの内容が全体会の報告でも共有されました。 特に避難所の運営は、男性が中心だが、女性の方が細かなニーズをもっており、女性リーダーの活躍が今後必要との声が印象的でした。
2.「多文化共生 ~地域に外国人市民が日本語を学び文化にふれる場を~」(SDGsの目標4より)
中東(岡山大学大学院社会科学研究科准教授)、岡山学芸館高等学校多文化共生ゼミ、城之内((一社)岡山に夜間中学校をつくる会理事長)、グェン キム リー(ベトナム出身、岡山大学経済学部生)の皆さんが話題提供をされました。リーさんが岡山に在住するベトナムからの労働者の声を伝えていました。日本語が勉強したいが、ボランティアさんの日本語は方言やスピード、日本語能力の問題で、日本語検定に直接参考とはなりにくい現実がある。また、岡山市では、外国人向けイベントが少なく、一緒に学べる地域での交流の場を求める声がある。
まとめとして、外国人むけの日本語教育は、ボランティアに頼っている現状があり、公的な支援が必要。ともに暮らす地域住民としてできることを考える。行政専門家との協力が必要などの意見が共有されました。
3.「自然と人の共生 ~森川里海のめぐみを2030へ~」(SDGsの目標14、15より)
三宅 (浅口市寄島漁業協同組合代表理事組合長)、小林(アユモドキを守る会)、山陽女子中学校・高等学校地歴部、里山保全活動団体・環境行政・公民館関係者などが参加し、6グループに分かれて、ワールドカフェスタイルでキーワードを挙げて議論しました。そこからのまとめとして、
・「教育」:学校、家庭、地域で教育をすることで、気づきの機会を提供し、環境を意識するようになることで、ポジティブに行動ができるようになる。
・時間と空間の広がりを持つ。働きかけをすることで、解決に向かうことが期待される。
・若い世代は2030年になると社会人として自分で行動できるようになる。 以上のように若い世代の行動をサポートする方向性が確認されました。
4.「再生可能エネルギー100%をめざして ~エネルギーの選択~」(SDGsの目標7より)
3名の方に話題提供いただき進行しました。中国四国地方環境事務所広島事務所長原田氏より、環境省が進める地域循環共生圏の創造と再生可能エネルギーについて。再エネの導入拡大による地域経済循環を創出するというものです。自治体出資のある地域新電力事業の紹介や横浜市と東北の12町村が連携した地域循環共生圏の協定の紹介などがありました。
持続可能なエネルギーと地域活性を結びつける西粟倉村の事例を同村の上山参事から、地域の木材資源や水資源の有効活用に関しての紹介、大学の自然エネルギー100%を目指す活動を推進する京都大学大学院 塚本悠平氏が事例や活動を紹介しました。千葉商科大学は既に自然エネルギー100%を達成している。龍谷大学にも、自然エネルギーの自家発電設備を整えている。
その後、参加者同士で意見交換を行い、分科会のまとめとして、以下の内容が発表されました。
・家庭や企業が契約している電力を再生可能エネルギー比率の高い電力会社に変更する。
・ライフスタイルを変更し、冷暖房など電力を使わないスタイルへシフトしていく。
5.「貧困と不平等、暴力をなくし、子どもたちが夢を抱き、何度でも挑戦できるおかやま地域を実現するために」(SDGsの目標1、10より)
3人の登壇者の発表概要です。
西﨑(NPO法人子どもシェルターモモ専務理事):家庭で暮らせなくなったこどもの緊急避難シェルターとして、教育虐待や家庭内暴力の被害を受けたこどもを受け入れているが、人手不足・資金不足の問題を常に抱えている。シングル家庭が増えることが予想される将来、支援を続けることは不可能。子どもを取り残さず夢を抱かせるには、より多くの資金、より多様な人手が必要。
中山(NPO法人あかね代表理事) :不登校・引きこもりの若者・子どもとその家族を支援。一般的に中学卒業や高校中退を機に公的な支援が途切れてしまうが、あかねでは年齢の切れ目を設けず、幅広い年齢層の人を受け入れている。し岡山市をはじめ全国での不登校児は増加しているのが現状岡山市は、小学生の不登校児数全国ワースト1位であるが、その認知度はかなり低い。学校以外の居場所を提供する民間団体の数も、資金不足のため減少し続けている。公的枠組みや、思いを持っている人を経済的に支える仕組みが不可欠。
小畠(NPO法人かものはしプロジェクト広報・ファンドレイジング):子どもが売られる問題をなくすために2002年から活動している。カンボジアで事業を始め、現在はインドで活動している。カンボジアでは、子どもの人身売買という問題の構造を把握し、対症療法ではなく根本原因にアプローチすることで問題解決に至った。寄付金総額の約7割が、一般のサポーター会員から月々少額を募っている寄付による。
次に、岡山の子ども支援に取り組む組織同士とそれを応援する人をつなぐ仕組みについて会場で検討をしました。
現状:子どもを支えるための様々なNPOがあるも、個々の組織がバラバラに寄付を集めることで結果的に寄付の奪い合いとなってしまっている。 解決のために、そこで、個々の組織を連結させ、合同の寄付受皿として「おかやま子ども基金(仮)」をつくることが提案されました。まず支援アライアンスの形成を行い、ファシリテーター役を担う。資金の使い道と配分の透明性を確保し、広報を行う。ふるさと納税と子ども基金の連携、寄付者へ分かりやすく効果を伝えること、資金を生み出す仕組みをつくる。この話し合いにより、個々のNPOのみが責任を負うのではなく、みんなの責任として取り組もうという気運が高まりました。
6.「まだ食べられるのに捨てるの?もったいない!~食品ロスを減らすために私たちができること
進行役をフードロス削減の啓蒙活動を熱心に行われている赤井(おかやまエコマインドネットワーク理事)さんが務め、以下3氏の話題提供が行われました。松井(岡山大学大学院環境生命科学研究科准教授)、三宅(生活協同組合おかやまコープ常務理事)、垣内(cafe&barどぅーず代表、岡山県喫茶飲食生活衛生同業組合副理事長) 発表後に、2つの課題についてグループに分かれて検討しました。①2030年にフードロスを50%削減するには ②食べ物に対して感謝の念・思いが伝わりにくい「フードロス」に代わるポジティブネーミング。
①については、消費者、流通業者、行政、社会制度などそれぞれのステークホルダーの立場からできることを抽出しました。予約販売、フェア、冷蔵庫のチェック、公民館でフードバンクのしくみの紹介、食品ロス削減のポイントなどの意見が出ました。②については、シンショクヒン、Re食品、エシカル食品、もったいない食品などのアイデアが出されました。
市民の間でも確実にSDGsの取り組みが定着し、認知が広まっています。自分事にして考え、できることから始めることが大切です。SDGsに関して知るには ゆうあいセンター 無料の講座やSDGsの情報コアーナー、相談窓口に気軽にご相談ください。

- OKAYAMA Share project ~おかやまをシェアしよう~ イベントレポート
誰もが社会を変えられる。 そんな可能性を、シェアしよう。
「OKAYAMA Share project」は、岡山..