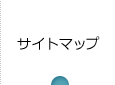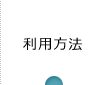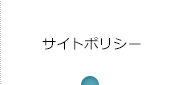タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
- OKAYAMA Share project ~おかやまをシェアしよう~ イベントレポート
- Social Good School !! 「Good」をもっと知ろう! イベントレポート
- 未来を生き抜く力を育む「野山の学校」開校
- (2013年11月6日)岡山発、新しい“協働”の形「災害時における 宗教施設のあり方を考えるセミナー」
- 農山村や暮らしとビジネスとの交流会 イベントレポート
- 子育て中親御さん、教育現場・対人サービス業の方へ
- 美作市で開催された地域活性化講演・発表会に参加しました!
- budding company fiesta
- 会議が変わると社会が変わる!? ファシリテーション講座に潜入してみた。
- 地域自主組織と小規模多機能自治を考える @地域力研修
地域に根ざしたライフスタイルを考える
イベント・セミナーまち・むら
こんにちは、ゆうあいセンター CSR担当の小桐です。
今回は、9月3日に開催された 山陽新聞社 連続シンポジウム:令和時代の地域をつくるの第2回「地域に根ざしたライフスタイル」の概要を報告させて頂きます。 既に、山陽新聞9月4日にはシンポジウムの概要が掲載されており、詳細は9月15日に新聞で掲載されますが、一足先に編集した内容をお読みください。
今回は、第1部で雑誌ソトコト編集長指出 一正氏の講演(話題提供)に続き、第2部でSDGsネットワークおかやま会長の石原氏と山陽新聞社編集者室長の岡山氏の進行でパネルディスカッションが行われました。
パネラーは、指出氏の他に、岡山県在住の3名の方です。太田真庭市長、山陽大学 地域マネジメント学部 白井教授、美作市 上山地区に暮らす森林ボランティアという肩書で登壇された梅谷 奈々氏です。
< 講演テーマ:「わたしたちは地方で幸せを見つける」 ~関係人口のつくり方~ >
指出氏は現在、ソトコトの編集長の他、内閣府や国土交通省など政府の4つの検討委員会の委員をされており、週2日は東京、残りの5日間は国内の様々な中山間地にて講演や地域住民との交流・学習会などをされています。
岡山との関係も深く、真庭市の政策アドバイザーも務めておられます。
同氏が提唱し、実践されている「関係人口」。島根、静岡、奈良県などで多くの地域プロジェクトに携わった経験と実績が地方創生に関する国策となり、委員として活躍される由縁です。
指出氏の視点は、地域の自然環境や歴史、文化、そこに住む人の暮らしの魅力。同氏曰く「地域の解像度を上げる」です。地域の魅力は、「ちがい」(ディファレンス)だと 普通にあるけどそこにしかないもの。そこにスポットを当てることでその町がとても魅力的な地域になり、人々が地域の未来を考え始める事につながると。
では、「関係人口」とは何か? 観光以上移住未満でその地域を訪れる都会の人たち(若者が多い)の人口です。彼らは、都会で仕事をしながらも地方にも興味がある人達。=ふるさと難民と自分たちを呼ぶそうです。
講演タイトルの「関係人口のつくり方」について以下の事例を紹介されました
①「地域を編集する」というタイトルで高知県の四万十源流の津野町で真冬の2月の塾を開催したところ自費で若者20名が参加。講座が終了し「ディレクター」の称号を貰い、地元の人たちと一緒にまちの未来を考えるようになった。講座終了後も通ってきている。
②島根は日本でいち早く過疎が始まった県。今後は、都会からの移住・定住人口が減ると予測。そこで「移住しなくても地域の事を考える講座」を開講。既に5期80人を超えた講座の参加者の内20名がIターンで定住をしている。自分たちで仕事をみつけている。休耕田を池に変え、リュウキン(1匹数万円の金魚)を育てている若者も出ている。
③奈良県 下北山村 東京で働く20~30代の若者を呼び、村の詳細な情報を敢えて伝えずに魅力探しをしてもらった。自分たちで発見した魅力が元となり、村をどんどん好きになっていく。東京へ戻っても村の事を考え、再びやって来る。村人たちも、「ほったらかし家」というゲストハウスを準備、3年が経過し、現在は他にもコアワーキングスペースが出来ていて、女性5人が在住。 木を売る商売を始めたり、新しい仕事を作っている。村長を囲み村の未来を語り合う場も出来ており、『若い人が村を歩くようになった』と住民たちはその変化に驚き、村長は村人に褒められている。
④奈良県 天川(てんかわ)村 1500人の村。参加者がセミナーの御礼として、プロジェクトをしたいと一晩だけの「スナックミルキー」を開店した。 名古屋から来た若い女性2名が名古屋の酒を熱燗をつけ村人を数人もてなしていた。しるこサンドがメインのあて。7時開店、10時ころになると地元、洞川(どろかわ)温泉で働く人たちがスナックを訪れ総勢80名にもなった。カップルの温泉客も楽しそうと飛び入り、たまたま誕生日プレゼントの旅行だったが急遽隣の豆腐屋からバースデー豆腐取り寄せ、バースデーケーキとして皆で誕生日を祝った。 天川では年1回のスナックミルキーだが、2人は他の地区でもスナックミルキーを開店、天川の魅力が人を呼び、あちこちの人が天川にやってきている。若い人たちの口コミの強さが現れていて、関係人口がどんどん広がっている。
⑤福井県 大野市 水を食べるレストラン。 水が豊かな同地区は、上水道利用はわずか20%。地元に住む9人が町を面白くしたいと活動を始めた。プロジェクト名「ミズカラ」(自ら・水から) 関係人口50名に案内状を出し、水だけでなく、全て地元食材を使ったメニューを考えて提供。 前菜は朱塗りのお膳に、地元朴ノ木の葉、板谷楓の葉を皿にして前菜を盛りつけした。.メインディッシュは、地元の清流に棲むアジメドジョウのフリット(揚げもの)。これまでの日本料理でなく、編集したところが素晴らしい。「今いる場所を最高に幸せに感じる」
ソトコトで前菜の写真をWEBにアップしたら、インスタグラム社から日本の美しさを紹介した写真として是非、表彰させてほしいと言ってきた。
地元の良さを知る人が地元を新しい観点で見直し、おもてなしで創った創作料理。 地元の良さが存分に溢れた熱波は(1枚の写真)世界に広がる。ローカルがローカルを褒め合うことがインターナショナルにつながる。
まとめ:「地域を編集する」ことで人口は減っても、関係人口は増える。若者に地元の素晴らしさを発見して貰えば良い。町を幸せにする人とそれを面白いと思い来る人が増える。そして、関係人口が増えるためには、.「関係案内人」の存在が不可欠。地域の人の関係が分かるとプロジェクト活動が広がり易い。
関係人口を増やすには、 ①関係案内所(場所や空間・人)が必要 ②未来を作っている手応えがあると良い。
③自分事として楽しいことが大事。 心の過疎から、本当の過疎は始まる。3か月先の未来を考える事が大事。
< パネルディスカッション 素晴らしきローカルライフ >
前回の振返り:京都大学 広井教授によるAI予測では、2019年東京一都市集中型➔2025~27までに地方分散型に(他極集中)なり、さらに2034~37で地方分散にならないと持続不可能となった。それを受けて、パネルディスカッションを開始。
石原氏より、基調講演は多くのキーワードが話された。関係人口、地域の豊かさ、真実は足元に、地域を編集すると面白いと感じる、ふるさと難民、若者も地域も育つ、地域の活性化、弱い処が「関わり代」のある事
○中山間地 美作市上山暮らしの梅谷 奈々さんは講演をどう感じたか?
梅谷氏:『アジメドジョウのフリッター、関係案内人の事が印象に残った。』に続き、自己紹介。東日本大震災をきっかけにボランティアをはじめ、一次産業に興味を持ち、女性7名で、林業に関わる与作ならぬ「ヨサコ」を立ち上げた。その後結婚し移住。自分が暮らす上山地区は160人の内40人が移住者、自分もその一人で棚田再生や築40年の古民家を改装してゲストハウスを運営する。地元上山地区は、不便。しかし、大切にしたいものが身近にすべてある。家族、仲間、自然など価値観を共有できるので幸せ。
○「真庭ライフスタイル」という言葉をよく使っている真庭市は、何を目指そうとしているのか?
太田市長:効率化、拡大、物質的繁栄を求めてきた現代社会、これからどうなのか? 人口が減っていく中でどの様に安全・安心で暮らすことが出来るか? ゆとりある町づくりが必要と考えている。 日本では、地震は1704年以降頻繁に起きている、都市集中型は不安。真庭市には、エネルギ-や産業の基盤となっている林業がある。 市の役割は、市民の幸せづくりと地域の魅力、地域の価値を上げる条件整備会社と考えている。このほか、バイオマス事業や旧9町村のそれぞれの取組を紹介。
○真庭が進めている大きな柱の一つがエネルギーの地産地消。その意味は?
白井教授:自立共生(自分で出来る事+助け合い)と関係人口の関わりが地域づくりに重要だと感じた。関係人口の考え方は素晴らしい。社会課題を解決して地域づくりをすすめるためには、環境、経済も併せて考える必要がある。その一つの要素として「再生可能エネルギー」を位置付けている。
それを受けて 太田市長:真庭市はエネルギーの自立を目指し木材を使っている。33%が木質バイオマス発電、太陽光+小水力発電も併せている。 小推力発電は、地域の経済として、10万円ほどの稼ぎだが、例えば蒜山の伝統文化大宮踊りを残す資金となっている。 石油を使った暮らしは、お金が地域の外へ出ていく、新技術でこれまで針葉樹中心だったバイオマス発電を広葉樹も燃料に出来るようにしていくつもり。
○石原氏:本日の議論を深めるために、事前にSDGsネットワークおかやまで質問を色々と考えた。『人口減少の中、少ない労力で社会システムを作るにはどうすると良いか?』
指出氏:テレワーク+ローカルライフが考えられるが、今後注目されるのは、若い世代におけるサブスクリプション(定額制)。 都会や興味のある場所など「移動」に関して一定額を支払うことでいくつかの場所に泊まり放題のシステムが確立しており、増加する事が考えられる。AIの普及で、仕事はAIに任せ、本来人間がすべきことをやれるようになる。そのために、自分がやりたい事を見つけておく必要がある。何がしたいのか?
・農業の未来を考え、地元を好きになることは重要。
・教育は変わるべき 今は消費者ばかり増やしている。生産者が増えないといけない。人に頼るだけの消費者生活は恰好悪い。
・真庭市は世界に通用する日本のまち。訪問したアイスランドでは地熱発電を進めている。地元が得意な方向で自立できるエネルギー政策を実施している。
○岡山氏:農業に関して、真庭市アグリネットを紹介してほしい。
太田氏:豊かさは、地に足を付けて生きる事。 地元のお年寄りが、自分の楽しみで育てた野菜を、道の駅や、大阪、滋賀の真庭市のアンテナショップ真庭市場で販売している。それが生きがいや小遣い稼ぎになっている。健康にもつながっている。農業は認知症の予防になると言われており、健康寿命が延びる。
梅谷氏:棚田と家庭菜園で食を賄っているが、農業だけでは、経済的自立は無理、古民家の管理人や色々な仕事の組み合わせで生活している。
白井氏:スマート農業で田植えや草刈機をAIで行うことが可能となる。小規模農業は気候変動の影響を受けやすい、地域とのつながりを見直し、多様な農業のやり方を考える必要がある。
太田氏:久世地区では、生ごみと糞尿からバイオマス発電と液肥づくりを行っている。液肥を使った作物は味が良い。レタスがブランドとなっている。今後5年くらいで市内全域にもこの仕組みを広げ、低コストの農業を目指したい。
○地元の経済循環を考える時、消費者はどこで買い物をすべきか?
岡山氏:買い物と地元でのお金の循環について、調査したデータがある。地元の中小の店で買うほど地域でお金が回る、76%が市内・県内にお金が留まる。全国チェーンの大型店では、県内には34%しかお金が還元されない。
白井氏:電気も再生可能エネルギーを地元で利用できるようにしてほしい。岡山では撰び代が無い。
太田氏:現状、中国電力が色々な調整を行っており、再生可能エネルギーだけ突出するとブラックアウトになる。根本的なところが変わらないと難しい現状だ。
○石原氏:日本全国均一でないローカルライフを成立させるためには何が 必要か。
指出氏:自治体のトップがカギ。住民は、まちがどう進もうとしているかを知ることが重要だ。まちのHPを見て働きかけることも重要。地元のコミュニティレベルで良いので働きかけるとガラッと変わる。これまでの居場所づくりから、まちづくりに関わる人(シビックエンゲージメント)が大切。
石原氏:岡山NPOセンターでは、自治体の選挙の度に首長候補の方に公開質問を実施している。
○石原氏:今後、価値観を変えるためにやったら良いことはどんな事?
指出氏:自分の「まち」が良いと思うこと、そして発言し、言い続ける事で「まち」は変わる。卑下する必要はない。
○石原氏:ライフスタイルが多様化し、 コミュニティも変化している、 総中流社会が終焉を迎える中、どのようにライフスタイルを考えていくか?
梅谷氏:子供が生まれ、より良いものを残していきたいという思いが強くなった。
白井氏:自立共生の一歩手前に半自立半共生が考えられる。エネルギーについては太陽光の活用などもある。
太田氏:主権者(住民)も地域の未来を考えるべき。特に食とエネルギーについて。自立性のない社会構造を変える必要がある。
以上のような話しが展開されました。まちの未来は自分の未来ととらえて、今、自分に何が出来るかを考え、一歩踏み出すことが重要です。買い物の仕方でまちを、社会を変える事も可能です。
今回は、9月3日に開催された 山陽新聞社 連続シンポジウム:令和時代の地域をつくるの第2回「地域に根ざしたライフスタイル」の概要を報告させて頂きます。 既に、山陽新聞9月4日にはシンポジウムの概要が掲載されており、詳細は9月15日に新聞で掲載されますが、一足先に編集した内容をお読みください。
今回は、第1部で雑誌ソトコト編集長指出 一正氏の講演(話題提供)に続き、第2部でSDGsネットワークおかやま会長の石原氏と山陽新聞社編集者室長の岡山氏の進行でパネルディスカッションが行われました。
パネラーは、指出氏の他に、岡山県在住の3名の方です。太田真庭市長、山陽大学 地域マネジメント学部 白井教授、美作市 上山地区に暮らす森林ボランティアという肩書で登壇された梅谷 奈々氏です。
< 講演テーマ:「わたしたちは地方で幸せを見つける」 ~関係人口のつくり方~ >
指出氏は現在、ソトコトの編集長の他、内閣府や国土交通省など政府の4つの検討委員会の委員をされており、週2日は東京、残りの5日間は国内の様々な中山間地にて講演や地域住民との交流・学習会などをされています。
岡山との関係も深く、真庭市の政策アドバイザーも務めておられます。
同氏が提唱し、実践されている「関係人口」。島根、静岡、奈良県などで多くの地域プロジェクトに携わった経験と実績が地方創生に関する国策となり、委員として活躍される由縁です。
指出氏の視点は、地域の自然環境や歴史、文化、そこに住む人の暮らしの魅力。同氏曰く「地域の解像度を上げる」です。地域の魅力は、「ちがい」(ディファレンス)だと 普通にあるけどそこにしかないもの。そこにスポットを当てることでその町がとても魅力的な地域になり、人々が地域の未来を考え始める事につながると。
では、「関係人口」とは何か? 観光以上移住未満でその地域を訪れる都会の人たち(若者が多い)の人口です。彼らは、都会で仕事をしながらも地方にも興味がある人達。=ふるさと難民と自分たちを呼ぶそうです。
講演タイトルの「関係人口のつくり方」について以下の事例を紹介されました
①「地域を編集する」というタイトルで高知県の四万十源流の津野町で真冬の2月の塾を開催したところ自費で若者20名が参加。講座が終了し「ディレクター」の称号を貰い、地元の人たちと一緒にまちの未来を考えるようになった。講座終了後も通ってきている。
②島根は日本でいち早く過疎が始まった県。今後は、都会からの移住・定住人口が減ると予測。そこで「移住しなくても地域の事を考える講座」を開講。既に5期80人を超えた講座の参加者の内20名がIターンで定住をしている。自分たちで仕事をみつけている。休耕田を池に変え、リュウキン(1匹数万円の金魚)を育てている若者も出ている。
③奈良県 下北山村 東京で働く20~30代の若者を呼び、村の詳細な情報を敢えて伝えずに魅力探しをしてもらった。自分たちで発見した魅力が元となり、村をどんどん好きになっていく。東京へ戻っても村の事を考え、再びやって来る。村人たちも、「ほったらかし家」というゲストハウスを準備、3年が経過し、現在は他にもコアワーキングスペースが出来ていて、女性5人が在住。 木を売る商売を始めたり、新しい仕事を作っている。村長を囲み村の未来を語り合う場も出来ており、『若い人が村を歩くようになった』と住民たちはその変化に驚き、村長は村人に褒められている。
④奈良県 天川(てんかわ)村 1500人の村。参加者がセミナーの御礼として、プロジェクトをしたいと一晩だけの「スナックミルキー」を開店した。 名古屋から来た若い女性2名が名古屋の酒を熱燗をつけ村人を数人もてなしていた。しるこサンドがメインのあて。7時開店、10時ころになると地元、洞川(どろかわ)温泉で働く人たちがスナックを訪れ総勢80名にもなった。カップルの温泉客も楽しそうと飛び入り、たまたま誕生日プレゼントの旅行だったが急遽隣の豆腐屋からバースデー豆腐取り寄せ、バースデーケーキとして皆で誕生日を祝った。 天川では年1回のスナックミルキーだが、2人は他の地区でもスナックミルキーを開店、天川の魅力が人を呼び、あちこちの人が天川にやってきている。若い人たちの口コミの強さが現れていて、関係人口がどんどん広がっている。
⑤福井県 大野市 水を食べるレストラン。 水が豊かな同地区は、上水道利用はわずか20%。地元に住む9人が町を面白くしたいと活動を始めた。プロジェクト名「ミズカラ」(自ら・水から) 関係人口50名に案内状を出し、水だけでなく、全て地元食材を使ったメニューを考えて提供。 前菜は朱塗りのお膳に、地元朴ノ木の葉、板谷楓の葉を皿にして前菜を盛りつけした。.メインディッシュは、地元の清流に棲むアジメドジョウのフリット(揚げもの)。これまでの日本料理でなく、編集したところが素晴らしい。「今いる場所を最高に幸せに感じる」
ソトコトで前菜の写真をWEBにアップしたら、インスタグラム社から日本の美しさを紹介した写真として是非、表彰させてほしいと言ってきた。
地元の良さを知る人が地元を新しい観点で見直し、おもてなしで創った創作料理。 地元の良さが存分に溢れた熱波は(1枚の写真)世界に広がる。ローカルがローカルを褒め合うことがインターナショナルにつながる。
まとめ:「地域を編集する」ことで人口は減っても、関係人口は増える。若者に地元の素晴らしさを発見して貰えば良い。町を幸せにする人とそれを面白いと思い来る人が増える。そして、関係人口が増えるためには、.「関係案内人」の存在が不可欠。地域の人の関係が分かるとプロジェクト活動が広がり易い。
関係人口を増やすには、 ①関係案内所(場所や空間・人)が必要 ②未来を作っている手応えがあると良い。
③自分事として楽しいことが大事。 心の過疎から、本当の過疎は始まる。3か月先の未来を考える事が大事。
< パネルディスカッション 素晴らしきローカルライフ >
前回の振返り:京都大学 広井教授によるAI予測では、2019年東京一都市集中型➔2025~27までに地方分散型に(他極集中)なり、さらに2034~37で地方分散にならないと持続不可能となった。それを受けて、パネルディスカッションを開始。
石原氏より、基調講演は多くのキーワードが話された。関係人口、地域の豊かさ、真実は足元に、地域を編集すると面白いと感じる、ふるさと難民、若者も地域も育つ、地域の活性化、弱い処が「関わり代」のある事
○中山間地 美作市上山暮らしの梅谷 奈々さんは講演をどう感じたか?
梅谷氏:『アジメドジョウのフリッター、関係案内人の事が印象に残った。』に続き、自己紹介。東日本大震災をきっかけにボランティアをはじめ、一次産業に興味を持ち、女性7名で、林業に関わる与作ならぬ「ヨサコ」を立ち上げた。その後結婚し移住。自分が暮らす上山地区は160人の内40人が移住者、自分もその一人で棚田再生や築40年の古民家を改装してゲストハウスを運営する。地元上山地区は、不便。しかし、大切にしたいものが身近にすべてある。家族、仲間、自然など価値観を共有できるので幸せ。
○「真庭ライフスタイル」という言葉をよく使っている真庭市は、何を目指そうとしているのか?
太田市長:効率化、拡大、物質的繁栄を求めてきた現代社会、これからどうなのか? 人口が減っていく中でどの様に安全・安心で暮らすことが出来るか? ゆとりある町づくりが必要と考えている。 日本では、地震は1704年以降頻繁に起きている、都市集中型は不安。真庭市には、エネルギ-や産業の基盤となっている林業がある。 市の役割は、市民の幸せづくりと地域の魅力、地域の価値を上げる条件整備会社と考えている。このほか、バイオマス事業や旧9町村のそれぞれの取組を紹介。
○真庭が進めている大きな柱の一つがエネルギーの地産地消。その意味は?
白井教授:自立共生(自分で出来る事+助け合い)と関係人口の関わりが地域づくりに重要だと感じた。関係人口の考え方は素晴らしい。社会課題を解決して地域づくりをすすめるためには、環境、経済も併せて考える必要がある。その一つの要素として「再生可能エネルギー」を位置付けている。
それを受けて 太田市長:真庭市はエネルギーの自立を目指し木材を使っている。33%が木質バイオマス発電、太陽光+小水力発電も併せている。 小推力発電は、地域の経済として、10万円ほどの稼ぎだが、例えば蒜山の伝統文化大宮踊りを残す資金となっている。 石油を使った暮らしは、お金が地域の外へ出ていく、新技術でこれまで針葉樹中心だったバイオマス発電を広葉樹も燃料に出来るようにしていくつもり。
○石原氏:本日の議論を深めるために、事前にSDGsネットワークおかやまで質問を色々と考えた。『人口減少の中、少ない労力で社会システムを作るにはどうすると良いか?』
指出氏:テレワーク+ローカルライフが考えられるが、今後注目されるのは、若い世代におけるサブスクリプション(定額制)。 都会や興味のある場所など「移動」に関して一定額を支払うことでいくつかの場所に泊まり放題のシステムが確立しており、増加する事が考えられる。AIの普及で、仕事はAIに任せ、本来人間がすべきことをやれるようになる。そのために、自分がやりたい事を見つけておく必要がある。何がしたいのか?
・農業の未来を考え、地元を好きになることは重要。
・教育は変わるべき 今は消費者ばかり増やしている。生産者が増えないといけない。人に頼るだけの消費者生活は恰好悪い。
・真庭市は世界に通用する日本のまち。訪問したアイスランドでは地熱発電を進めている。地元が得意な方向で自立できるエネルギー政策を実施している。
○岡山氏:農業に関して、真庭市アグリネットを紹介してほしい。
太田氏:豊かさは、地に足を付けて生きる事。 地元のお年寄りが、自分の楽しみで育てた野菜を、道の駅や、大阪、滋賀の真庭市のアンテナショップ真庭市場で販売している。それが生きがいや小遣い稼ぎになっている。健康にもつながっている。農業は認知症の予防になると言われており、健康寿命が延びる。
梅谷氏:棚田と家庭菜園で食を賄っているが、農業だけでは、経済的自立は無理、古民家の管理人や色々な仕事の組み合わせで生活している。
白井氏:スマート農業で田植えや草刈機をAIで行うことが可能となる。小規模農業は気候変動の影響を受けやすい、地域とのつながりを見直し、多様な農業のやり方を考える必要がある。
太田氏:久世地区では、生ごみと糞尿からバイオマス発電と液肥づくりを行っている。液肥を使った作物は味が良い。レタスがブランドとなっている。今後5年くらいで市内全域にもこの仕組みを広げ、低コストの農業を目指したい。
○地元の経済循環を考える時、消費者はどこで買い物をすべきか?
岡山氏:買い物と地元でのお金の循環について、調査したデータがある。地元の中小の店で買うほど地域でお金が回る、76%が市内・県内にお金が留まる。全国チェーンの大型店では、県内には34%しかお金が還元されない。
白井氏:電気も再生可能エネルギーを地元で利用できるようにしてほしい。岡山では撰び代が無い。
太田氏:現状、中国電力が色々な調整を行っており、再生可能エネルギーだけ突出するとブラックアウトになる。根本的なところが変わらないと難しい現状だ。
○石原氏:日本全国均一でないローカルライフを成立させるためには何が 必要か。
指出氏:自治体のトップがカギ。住民は、まちがどう進もうとしているかを知ることが重要だ。まちのHPを見て働きかけることも重要。地元のコミュニティレベルで良いので働きかけるとガラッと変わる。これまでの居場所づくりから、まちづくりに関わる人(シビックエンゲージメント)が大切。
石原氏:岡山NPOセンターでは、自治体の選挙の度に首長候補の方に公開質問を実施している。
○石原氏:今後、価値観を変えるためにやったら良いことはどんな事?
指出氏:自分の「まち」が良いと思うこと、そして発言し、言い続ける事で「まち」は変わる。卑下する必要はない。
○石原氏:ライフスタイルが多様化し、 コミュニティも変化している、 総中流社会が終焉を迎える中、どのようにライフスタイルを考えていくか?
梅谷氏:子供が生まれ、より良いものを残していきたいという思いが強くなった。
白井氏:自立共生の一歩手前に半自立半共生が考えられる。エネルギーについては太陽光の活用などもある。
太田氏:主権者(住民)も地域の未来を考えるべき。特に食とエネルギーについて。自立性のない社会構造を変える必要がある。
以上のような話しが展開されました。まちの未来は自分の未来ととらえて、今、自分に何が出来るかを考え、一歩踏み出すことが重要です。買い物の仕方でまちを、社会を変える事も可能です。

- OKAYAMA Share project ~おかやまをシェアしよう~ イベントレポート
誰もが社会を変えられる。 そんな可能性を、シェアしよう。
「OKAYAMA Share project」は、岡山..