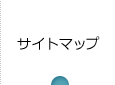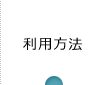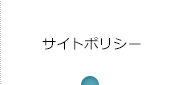タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
- OKAYAMA Share project ~おかやまをシェアしよう~ イベントレポート
- Social Good School !! 「Good」をもっと知ろう! イベントレポート
- 未来を生き抜く力を育む「野山の学校」開校
- (2013年11月6日)岡山発、新しい“協働”の形「災害時における 宗教施設のあり方を考えるセミナー」
- 農山村や暮らしとビジネスとの交流会 イベントレポート
- 子育て中親御さん、教育現場・対人サービス業の方へ
- 美作市で開催された地域活性化講演・発表会に参加しました!
- budding company fiesta
- 会議が変わると社会が変わる!? ファシリテーション講座に潜入してみた。
- 地域自主組織と小規模多機能自治を考える @地域力研修
「SDGsを身近に8 岡山でのSDGsのイベント報告④」
イベント・セミナーその他真庭市
こんにちは、ゆうあいセンターCSR相談員 小桐です。
今回は、2019年3月10日に真庭市で行われたSDGsイベントの第5回目 「多彩な真庭を次世代につなぐ」を紹介します。
このイベントは、SDGs未来都市のひとつである真庭市が主催で行われました。
会場となった、勝山文化センターには、真庭市と「SDGsパートナーシップ宣言」を行い、真庭市が認めら企業や団体のSDGsへの取組が紹介されていました。これまでに、地元の企業を中心に20団体がパートナーに、8団体がSDGs普及啓発活動支援事業参加団体として登録されています。
第1部では、地元で活動する3団体の発表がありました。
「丸太棒の復活」~勝山のまちづくりを次世代が復活~
かつてあった地元の銘菓「丸太棒」を復活させる取り組みをしながら、勝山のまちづくりを次世代へ引き継ごうとするプロジェクトです。
暖簾の町勝山は、古い街並みにそれぞれの屋号をデザインした暖簾が掛かっています。昔ながらの風情は、訪れる人を魅了しますが、勝山には宿泊施設が殆どなく、街の活性化には更なる努力が必要な段階です。地元に住む子育て世代は、地元で集まりたくても夜に開いている店が無く、親交を深める機会を見つけるのも大変でした。
そこで、勝山まちなみ会議 代表の行藤氏を中心にして、住む人、訪れる人にさらなる魅力の提供をしようと以下の取組が行われています。一つは、勝山の街並みを活かした宿泊施設、外国からのインバウンド客は日本の古い街並みにとても魅力を感じるそうで、歴史を活かした古民家のゲストハウスの研究をスタートさせています。
また、勝山の街並みに屋台13台をならべた「勝山まちなみバル」では、地元の人500人が集い大盛況でした。
ひなまつりマルシェでは20店舗が出展、地元に賑わいが押し寄せています。今の食だけでなく、伝統への思いも強く、昭和54年に途絶えた幻の銘菓丸太棒を復活させようと異世代の交流が始まりました。レシピが残っておらず、そのことが却って人と人をつなぐ良いきかっかけになりました。昔の味を知る人々は、年齢的にも60代以上の人です。子育て世代の親や祖父母の年齢。かつての味や外観、触感を思い出す世代と形にする世代の協働作業が続きました。まだ、完成はしていないとの事で、今後も交流による復活スト-リーは続きます。
SDGsの目標で最初に思いつくのは、「目標11住み続けられるまちづくりを」です。
「旅人食堂と外国人シェアハウスで世界と真庭をつなぐ」
次に登場したのは、韓国出身の姜さん。妻の帰国出産がきっかけで日本へ移り、縁が有って真庭市北房地区に地域おこし協力隊として「北房サイクリングマップ」の制作を行いました。
姜氏は、真庭市に訪れる外国人が活躍できる「インターナショナルシェアハウス」を企画・実現しています。
この事業は、「旅人食堂」というもので、訪れた外国人が、自国の料理を作って地元の人をもてなすものです。国際交流、食文化の交流に繋がっています。真庭市は色々な魅力があるけれどまだまだ外国人には無名、インバウンドの1%しか真庭には来ないとの事です。シェアリングエコノミープラットフォームを目指して活動を続けています。
「ジビエカーで地域を結び、産業を興す」
最後に登場したのは、ジビエ関係者の面々 全国で2番目のジビエカー(移動式野生動物解体処理車)の納品をした長野トヨタの担当者、地元猟友会の山本会長、ジビエレシピを考案する地元真庭高校久世校地の生徒がが登壇しました。当日は会場の外でジビエカーも公開され多くの人が見学をしていました。
イノシシやシカは、捕殺してすぐに解体しないと臭いがするとのことで、この移動車は今後、獣害の多い真庭市では活躍しそうです。 このジビエカーは安心・安全の食肉処理がきちんとデータとして残るように、カメラが3台、煮沸機を積み内装はオールステンレスで清潔を保つ工夫が随所にされています。近年シカは増える一方ですが、銃の免許を持った猟師は減る一方との事で、今後若い世代の活躍が来されます。真庭高校では、ジビエレシピを開発し、食品関連企業がジビエ商品の製造をしてくれるのを期待しています。
バイオマスタウン真庭の創造に長年係わって来られた21世紀真庭塾のメンバーランデス㈱大月会長は、1993年から誇りある・笑顔ある真庭を目指して、地元のお宝の掘り起こしを長年行ってこられました。街づくり、ゼロエミッション、自然との共生を真庭塾の部会で研究してこられました。里山資本主義で真庭市の取組が紹介されることでこれまでの活動が間違っていなかったことが証明されました。
長年の研究・活動で「9産業と技術革新の基盤づくり」を実現した21世紀の真庭塾のメンバーは今の真庭を20年前からバックキャスティングしてきました。
当日の参加者の半分が真庭市の住民の方達ですが、誇りに感じられることが多かったのではないかと感じました。
第2部では、太田真庭市長と俳優でかつ㈱リバースプロジェクトの代表で「人類が地球に生き残るためにどうすべきか」を事業化している伊勢谷 友介氏の対談が行われました。
対談のテーマは「多彩で豊かな真庭のくらし」。冒頭司会者から両名に対し、普段の生活に当てはめてSDGsを語ってほしいとのお題が出されました。
太田市長は、自宅横に畑を作っていること、肥料は真庭市久世地区で行われている回収生ごみから作った液肥を使っている事の紹介がありました。上京の際には、手製の野菜を持って、官庁や国会議員を訪問する話がありました。 一方伊勢谷氏は、マンションのベランダで、生ごみコンポストを使っている。電気は自然エネルギーと契約をしていると言われました。リバースプロジェクトは衣食住だけでなく、芸術、教育、ソーシャルグッドとなるような生き方や、企業のあり方を提案する啓蒙活動を実践されており、生き方自体もその活動二沿ったものとなっています。当日の会場には、伊勢谷ファンと思しき若い女性が多く参加していました、彼女たちは、SDGsの言葉は知らなくても「リバースプロジェクト」の活動は良く知っていました。持続可能なくらしへの共感がSDGsという言葉と結びつく このイベントが持つ新たな役割を感じました。
伊勢谷氏は、SDGsは脳からの指令だと感じていると発言。私たちのいまの暮らしは地球2.9個が必要。エコロジカルフットプリントを1個に戻す暮らしをしないといけないと力説。今の暮らしは、未来から借りを作って行っている。大量生産、大量消費はダサイ、私たちががん細胞であることを認識すべきと言われました。
今後、SDGsの達成のために必要な視点はという質問について
太田市長の答えは、「市民の視点」が重要。100年前に一番貧しい国と言われたフィンランドは今や「豊かなくらしの出来る国に変化している」人口が減ることへの対策も進んでおり、欧州の小国を見習う必要がある。先進国の中で、若年層の死因で自殺が一番多いのは日本。一方暮らしの満足度は54位と低い。満足度を上げるには、自分で職業選択が出来るようにならないといけない。その為に必要なのは、工作室を各小学校に作る事といわれました。
伊勢谷氏は、「宇宙人の視点が重要だと」強調されました。欧州小国は、すでに変化が始まっている。持続可能な生き方・暮らし方について自分の国はどうあるべきかを問い直しており、既に動き始めている。教育・医療を無償化している、そうする社会は変わっていく。自分の暮らしの在り方を考えると日本の政治の在り方の変化を生む。(ここまでは言われませんが、そのニュアンスは大いにありました。イタリアは直接民主主義の方向へ動き始めている。自分の国はどうあるべきかを問い直す必要がある。これからは学歴社会でなくなるといわれました。
これから挑戦してみたいことについて、伊勢谷氏は、新しいプロジェクトとしてルークス(スクールの反対読み)を立ち上げる。リベラルアーツとして普遍性×先端性を考える教育。なぜ、生きているか? 個人の命、その存在自体がありがとうと言われるようになるための教育。動物の中で、人間しかできない事は、死後を考えて行動すること。
太田市長は真庭市という自然豊かな地域で、人のつながりを生かして、次世代を担う事が出来る人材が育つ環境を整えたいと結ばれました。
SDGsはこれまでの資本主義、国や企業、個人の価値観で至らなかった事によって起こった問題を見つめ直し、みんなで気づき、できるところから変えて行きましょう。「誰一人も取り残さずに」という世界共通プロジェクトです。どこまで自分事としてとらえることが出来るかがポイント。自分と周囲の関係者だけの幸せを望んで進んできた時代のつけが現状です。
自分自身の価値観をもう一度見直すところからSDGs目標実現への一歩が始まると感じたフォーラムでした。
今回は、2019年3月10日に真庭市で行われたSDGsイベントの第5回目 「多彩な真庭を次世代につなぐ」を紹介します。
このイベントは、SDGs未来都市のひとつである真庭市が主催で行われました。
会場となった、勝山文化センターには、真庭市と「SDGsパートナーシップ宣言」を行い、真庭市が認めら企業や団体のSDGsへの取組が紹介されていました。これまでに、地元の企業を中心に20団体がパートナーに、8団体がSDGs普及啓発活動支援事業参加団体として登録されています。
第1部では、地元で活動する3団体の発表がありました。
「丸太棒の復活」~勝山のまちづくりを次世代が復活~
かつてあった地元の銘菓「丸太棒」を復活させる取り組みをしながら、勝山のまちづくりを次世代へ引き継ごうとするプロジェクトです。
暖簾の町勝山は、古い街並みにそれぞれの屋号をデザインした暖簾が掛かっています。昔ながらの風情は、訪れる人を魅了しますが、勝山には宿泊施設が殆どなく、街の活性化には更なる努力が必要な段階です。地元に住む子育て世代は、地元で集まりたくても夜に開いている店が無く、親交を深める機会を見つけるのも大変でした。
そこで、勝山まちなみ会議 代表の行藤氏を中心にして、住む人、訪れる人にさらなる魅力の提供をしようと以下の取組が行われています。一つは、勝山の街並みを活かした宿泊施設、外国からのインバウンド客は日本の古い街並みにとても魅力を感じるそうで、歴史を活かした古民家のゲストハウスの研究をスタートさせています。
また、勝山の街並みに屋台13台をならべた「勝山まちなみバル」では、地元の人500人が集い大盛況でした。
ひなまつりマルシェでは20店舗が出展、地元に賑わいが押し寄せています。今の食だけでなく、伝統への思いも強く、昭和54年に途絶えた幻の銘菓丸太棒を復活させようと異世代の交流が始まりました。レシピが残っておらず、そのことが却って人と人をつなぐ良いきかっかけになりました。昔の味を知る人々は、年齢的にも60代以上の人です。子育て世代の親や祖父母の年齢。かつての味や外観、触感を思い出す世代と形にする世代の協働作業が続きました。まだ、完成はしていないとの事で、今後も交流による復活スト-リーは続きます。
SDGsの目標で最初に思いつくのは、「目標11住み続けられるまちづくりを」です。
「旅人食堂と外国人シェアハウスで世界と真庭をつなぐ」
次に登場したのは、韓国出身の姜さん。妻の帰国出産がきっかけで日本へ移り、縁が有って真庭市北房地区に地域おこし協力隊として「北房サイクリングマップ」の制作を行いました。
姜氏は、真庭市に訪れる外国人が活躍できる「インターナショナルシェアハウス」を企画・実現しています。
この事業は、「旅人食堂」というもので、訪れた外国人が、自国の料理を作って地元の人をもてなすものです。国際交流、食文化の交流に繋がっています。真庭市は色々な魅力があるけれどまだまだ外国人には無名、インバウンドの1%しか真庭には来ないとの事です。シェアリングエコノミープラットフォームを目指して活動を続けています。
「ジビエカーで地域を結び、産業を興す」
最後に登場したのは、ジビエ関係者の面々 全国で2番目のジビエカー(移動式野生動物解体処理車)の納品をした長野トヨタの担当者、地元猟友会の山本会長、ジビエレシピを考案する地元真庭高校久世校地の生徒がが登壇しました。当日は会場の外でジビエカーも公開され多くの人が見学をしていました。
イノシシやシカは、捕殺してすぐに解体しないと臭いがするとのことで、この移動車は今後、獣害の多い真庭市では活躍しそうです。 このジビエカーは安心・安全の食肉処理がきちんとデータとして残るように、カメラが3台、煮沸機を積み内装はオールステンレスで清潔を保つ工夫が随所にされています。近年シカは増える一方ですが、銃の免許を持った猟師は減る一方との事で、今後若い世代の活躍が来されます。真庭高校では、ジビエレシピを開発し、食品関連企業がジビエ商品の製造をしてくれるのを期待しています。
バイオマスタウン真庭の創造に長年係わって来られた21世紀真庭塾のメンバーランデス㈱大月会長は、1993年から誇りある・笑顔ある真庭を目指して、地元のお宝の掘り起こしを長年行ってこられました。街づくり、ゼロエミッション、自然との共生を真庭塾の部会で研究してこられました。里山資本主義で真庭市の取組が紹介されることでこれまでの活動が間違っていなかったことが証明されました。
長年の研究・活動で「9産業と技術革新の基盤づくり」を実現した21世紀の真庭塾のメンバーは今の真庭を20年前からバックキャスティングしてきました。
当日の参加者の半分が真庭市の住民の方達ですが、誇りに感じられることが多かったのではないかと感じました。
第2部では、太田真庭市長と俳優でかつ㈱リバースプロジェクトの代表で「人類が地球に生き残るためにどうすべきか」を事業化している伊勢谷 友介氏の対談が行われました。
対談のテーマは「多彩で豊かな真庭のくらし」。冒頭司会者から両名に対し、普段の生活に当てはめてSDGsを語ってほしいとのお題が出されました。
太田市長は、自宅横に畑を作っていること、肥料は真庭市久世地区で行われている回収生ごみから作った液肥を使っている事の紹介がありました。上京の際には、手製の野菜を持って、官庁や国会議員を訪問する話がありました。 一方伊勢谷氏は、マンションのベランダで、生ごみコンポストを使っている。電気は自然エネルギーと契約をしていると言われました。リバースプロジェクトは衣食住だけでなく、芸術、教育、ソーシャルグッドとなるような生き方や、企業のあり方を提案する啓蒙活動を実践されており、生き方自体もその活動二沿ったものとなっています。当日の会場には、伊勢谷ファンと思しき若い女性が多く参加していました、彼女たちは、SDGsの言葉は知らなくても「リバースプロジェクト」の活動は良く知っていました。持続可能なくらしへの共感がSDGsという言葉と結びつく このイベントが持つ新たな役割を感じました。
伊勢谷氏は、SDGsは脳からの指令だと感じていると発言。私たちのいまの暮らしは地球2.9個が必要。エコロジカルフットプリントを1個に戻す暮らしをしないといけないと力説。今の暮らしは、未来から借りを作って行っている。大量生産、大量消費はダサイ、私たちががん細胞であることを認識すべきと言われました。
今後、SDGsの達成のために必要な視点はという質問について
太田市長の答えは、「市民の視点」が重要。100年前に一番貧しい国と言われたフィンランドは今や「豊かなくらしの出来る国に変化している」人口が減ることへの対策も進んでおり、欧州の小国を見習う必要がある。先進国の中で、若年層の死因で自殺が一番多いのは日本。一方暮らしの満足度は54位と低い。満足度を上げるには、自分で職業選択が出来るようにならないといけない。その為に必要なのは、工作室を各小学校に作る事といわれました。
伊勢谷氏は、「宇宙人の視点が重要だと」強調されました。欧州小国は、すでに変化が始まっている。持続可能な生き方・暮らし方について自分の国はどうあるべきかを問い直しており、既に動き始めている。教育・医療を無償化している、そうする社会は変わっていく。自分の暮らしの在り方を考えると日本の政治の在り方の変化を生む。(ここまでは言われませんが、そのニュアンスは大いにありました。イタリアは直接民主主義の方向へ動き始めている。自分の国はどうあるべきかを問い直す必要がある。これからは学歴社会でなくなるといわれました。
これから挑戦してみたいことについて、伊勢谷氏は、新しいプロジェクトとしてルークス(スクールの反対読み)を立ち上げる。リベラルアーツとして普遍性×先端性を考える教育。なぜ、生きているか? 個人の命、その存在自体がありがとうと言われるようになるための教育。動物の中で、人間しかできない事は、死後を考えて行動すること。
太田市長は真庭市という自然豊かな地域で、人のつながりを生かして、次世代を担う事が出来る人材が育つ環境を整えたいと結ばれました。
SDGsはこれまでの資本主義、国や企業、個人の価値観で至らなかった事によって起こった問題を見つめ直し、みんなで気づき、できるところから変えて行きましょう。「誰一人も取り残さずに」という世界共通プロジェクトです。どこまで自分事としてとらえることが出来るかがポイント。自分と周囲の関係者だけの幸せを望んで進んできた時代のつけが現状です。
自分自身の価値観をもう一度見直すところからSDGs目標実現への一歩が始まると感じたフォーラムでした。

- OKAYAMA Share project ~おかやまをシェアしよう~ イベントレポート
誰もが社会を変えられる。 そんな可能性を、シェアしよう。
「OKAYAMA Share project」は、岡山..