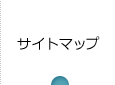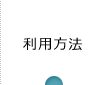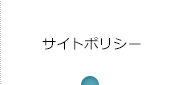タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
- OKAYAMA Share project ~おかやまをシェアしよう~ イベントレポート
- Social Good School !! 「Good」をもっと知ろう! イベントレポート
- 未来を生き抜く力を育む「野山の学校」開校
- (2013年11月6日)岡山発、新しい“協働”の形「災害時における 宗教施設のあり方を考えるセミナー」
- 農山村や暮らしとビジネスとの交流会 イベントレポート
- 子育て中親御さん、教育現場・対人サービス業の方へ
- 美作市で開催された地域活性化講演・発表会に参加しました!
- budding company fiesta
- 会議が変わると社会が変わる!? ファシリテーション講座に潜入してみた。
- 地域自主組織と小規模多機能自治を考える @地域力研修
「SDGsを身近に6 岡山でのSDGsのイベント報告②」
イベント・セミナーその他
こんにちは、ゆうあいセンターCSR相談員 小桐です。
今回は、2019年2月18日に岡山で行われたSDGsイベントの第2回目 「中小企業のためのSDGs勉強会」を紹介します。
このイベントは、主催NPO法人岡山NPOセンター・CSR報告書を読む会 で共催として、SDGsネットワークおかやま、社会的責任向上のめのNPO/NGOネットワーク(NNネット)、一般社団法人CSOネットワーク、IHOE〔人と組織と地球のための国際研究所〕の4団体が協力をして下さいました。
第1部ゲスト企業からの話題提供は 横浜市で1881年(明治14年)創業 創業137年の株式会社 大川印刷 大川社長でした。同社は、資本金 2,000万円、従業員36名(2018年11月現在)のまさに地場の小企業です。
大川社長は、2005年自社の社会的使命を「Social Printing Company(社会的印刷会社)」と位置づけ環境に関する事業活動を本格的に展開されてきました。
背景に同年に横浜型地域貢献企業認定制度がスタートしたことに有ります。この制度は、大川社長も参加されていた横浜青年会議所が中心となり、「しあわせの選択」=(「こころの豊かさ」を尺度とした新しい時代にふさわしい価値基準「横浜スタンダード」)という言葉を運営テーマとして、マニフェストを作成しました。
市民・企業・行政が心をひとつにしてこころの豊かさを構築するために 横浜スタンダード推進協議会、横浜企業支援財団、横浜市立大学が中心となって連携し、構築したもので、現在横浜市に制度として認定され今日に至っています。
現在大川印刷では、印刷事業における年間のCO2全量を予めオフセットするゼロカーボンプリント」を日本で唯一展開されています。同社の事業は、環境省 中小企業版2度目標・RE100の設定支援事業に採択されており、2018年再生可能エネルギー100%宣言、今年度中に達成を目指して活動中です。
環境経営を推し進める中、2015年にSDGsに出会い、売上の低迷に対し、新たな事業分野開拓の必要性を感じていたことや日本経団連がSociety 5.0の実現を通じたSDGsの達成を柱として企業行動憲章を改定したこと(2017年)。持続可能な調達「ISO20400」が発行(2017年)されたこと、SRI(社会責任投資)、ESG投資(環境・社会・企業統治)が拡大し、非財務情報開示の要請や調達先、取引先に求められてきている等、社会的背景も考慮にいれて、SDGsを経営に導入されました。
8年前から、社員全員参加の経営計画を策定されていて、この計画にSDGsを上手く取り入れました。
印刷会社の特性を生かし、自社独自のSDGsの目標を印刷したメモパッドの裏にうまくいっていること、うまくいっていないこと、やりたいことを書いて重要課題のマトリックス表を作成しました。
その結果7つのプロジェクトチームが発足し事業に取り組んでいます。品質保証チームや環境チームは通年の取組になっています。
大川社長は、「本業(ビジネス)を通じたCSRこそが王道」という考え方を持っておられ、SDGsの目標は「自社がビジネスとして取り組むべき課題が整理されている」ために、無理なく身の丈に合った取り組みができるので、継続できる。そして、2030年まで見据えた経営計画ができると感じられています。
印刷の紙にはFSC®森林認証紙を全体の62%使用(2018年度12月時点)、インクも持続可能な調達として石油を全く含まないインキを使用し7割の印刷物を製造しています。さらに、従来型と比べ70%以上消費電力をカットできる「LED UV印刷機」や太陽光発電装置の導入により、CO2の排出負荷を下げると共に、カーボンオフセットを行い(自社の排出したCO2に相当するCO2削減プロジェクトより購入し相殺する)、CO2排出ゼロ印刷を実現しています。
その結果、上場企業4社を含む新規顧客の獲得、2018年度は49社の獲得が出来、第2回ジャパンSDGsアワード SDGsパートナーシップ賞(特別賞)を受賞されました。 SDGs経営がまさに上手くいっている事例と言えます。
第2部では、公共調達に関する調査報告をCSOネットワーク 長谷川雅子様よりご紹介いただきました。
1.公共調達調査では、持続可能な社会づ売りの為には、当然持続可能な生産・消費パターンの確立が不可欠で公共調達はそこに大きなインパクトを与える。世界ではEU公共調達指令などが発効され、環境、社会に配慮する事が求められるようなっている。一方、日本の自治体では、いまだに競争が原則なっている。1999年地方自治法が改正され、「総合評価方式」が導入されるようになったにも関わらずまだ、環境・社会・経済を包括した取り組みは殆ど成されていない現状である。
そんな中、SDGsモデル都市のひとつである岡山市は総合評価方式を頻繁に実施している。環境負荷削減、地域防災協力を評価している。女性が輝く男女共同参画事業所認証を取得した企業には、建設工事の入札参加審査における格付けも決定時に加算するなどをしている。低金利融資制度や岡山市ホワイト+企業表彰にもいても加算されるようになっている。 岡山県でも岡山市と同様に環境、防災の取り組みを評価すると共に、入札の精神性の際に障がい者雇用、若年技術者雇用、女性技術者雇用、育児介護休業規定が加点項目となっている。横浜市の地域貢献型企業認証制度は先を一歩行くものである。
その後パネルディスカッションが行われ、横浜型地域貢献企業認定制度から学ぶべきポイントについて話題提供とディスカッションが行われました。
同制度は、地域を志向するCSRに取り組む企業を公的機関が認定するもので、産官学の5者が制度を運営しています。中小企業診断士等の評価員が訪問し確認後、外部専門家の認定委員会で決定され、2年間認められます。
CSRの考え方を理解し、利害関係者に対して戦略的な取組をしている。社内マネジメントを実施してPDCAサイクルを適切に運用している。地元横浜を意識したCSR活動を展開している。正し、同じことの繰り返しだけをしていては更新されません。
企業の社会的責任はCSR、NPO/NGOが果たすべき責任はNSR 自治体が果たすべき責任は、LGSR それぞれが持続可能な社会、地域づくりに向けて個々の責任を果たすと同時に連携していくことが重用として会を締めくくりました。
アンケートでは、「地域で頑張っている中小企業を応援してもらいたい」「人札制度を広域で共有できるようにする」「岡山市の歳出費 1274億円は驚いた」などの意見がありました。数多くのSDGsに関する情報に触れることで個人、団体が連携しやすくなるのではないかと感じた勉強会でした。
今回は、2019年2月18日に岡山で行われたSDGsイベントの第2回目 「中小企業のためのSDGs勉強会」を紹介します。
このイベントは、主催NPO法人岡山NPOセンター・CSR報告書を読む会 で共催として、SDGsネットワークおかやま、社会的責任向上のめのNPO/NGOネットワーク(NNネット)、一般社団法人CSOネットワーク、IHOE〔人と組織と地球のための国際研究所〕の4団体が協力をして下さいました。
第1部ゲスト企業からの話題提供は 横浜市で1881年(明治14年)創業 創業137年の株式会社 大川印刷 大川社長でした。同社は、資本金 2,000万円、従業員36名(2018年11月現在)のまさに地場の小企業です。
大川社長は、2005年自社の社会的使命を「Social Printing Company(社会的印刷会社)」と位置づけ環境に関する事業活動を本格的に展開されてきました。
背景に同年に横浜型地域貢献企業認定制度がスタートしたことに有ります。この制度は、大川社長も参加されていた横浜青年会議所が中心となり、「しあわせの選択」=(「こころの豊かさ」を尺度とした新しい時代にふさわしい価値基準「横浜スタンダード」)という言葉を運営テーマとして、マニフェストを作成しました。
市民・企業・行政が心をひとつにしてこころの豊かさを構築するために 横浜スタンダード推進協議会、横浜企業支援財団、横浜市立大学が中心となって連携し、構築したもので、現在横浜市に制度として認定され今日に至っています。
現在大川印刷では、印刷事業における年間のCO2全量を予めオフセットするゼロカーボンプリント」を日本で唯一展開されています。同社の事業は、環境省 中小企業版2度目標・RE100の設定支援事業に採択されており、2018年再生可能エネルギー100%宣言、今年度中に達成を目指して活動中です。
環境経営を推し進める中、2015年にSDGsに出会い、売上の低迷に対し、新たな事業分野開拓の必要性を感じていたことや日本経団連がSociety 5.0の実現を通じたSDGsの達成を柱として企業行動憲章を改定したこと(2017年)。持続可能な調達「ISO20400」が発行(2017年)されたこと、SRI(社会責任投資)、ESG投資(環境・社会・企業統治)が拡大し、非財務情報開示の要請や調達先、取引先に求められてきている等、社会的背景も考慮にいれて、SDGsを経営に導入されました。
8年前から、社員全員参加の経営計画を策定されていて、この計画にSDGsを上手く取り入れました。
印刷会社の特性を生かし、自社独自のSDGsの目標を印刷したメモパッドの裏にうまくいっていること、うまくいっていないこと、やりたいことを書いて重要課題のマトリックス表を作成しました。
その結果7つのプロジェクトチームが発足し事業に取り組んでいます。品質保証チームや環境チームは通年の取組になっています。
大川社長は、「本業(ビジネス)を通じたCSRこそが王道」という考え方を持っておられ、SDGsの目標は「自社がビジネスとして取り組むべき課題が整理されている」ために、無理なく身の丈に合った取り組みができるので、継続できる。そして、2030年まで見据えた経営計画ができると感じられています。
印刷の紙にはFSC®森林認証紙を全体の62%使用(2018年度12月時点)、インクも持続可能な調達として石油を全く含まないインキを使用し7割の印刷物を製造しています。さらに、従来型と比べ70%以上消費電力をカットできる「LED UV印刷機」や太陽光発電装置の導入により、CO2の排出負荷を下げると共に、カーボンオフセットを行い(自社の排出したCO2に相当するCO2削減プロジェクトより購入し相殺する)、CO2排出ゼロ印刷を実現しています。
その結果、上場企業4社を含む新規顧客の獲得、2018年度は49社の獲得が出来、第2回ジャパンSDGsアワード SDGsパートナーシップ賞(特別賞)を受賞されました。 SDGs経営がまさに上手くいっている事例と言えます。
第2部では、公共調達に関する調査報告をCSOネットワーク 長谷川雅子様よりご紹介いただきました。
1.公共調達調査では、持続可能な社会づ売りの為には、当然持続可能な生産・消費パターンの確立が不可欠で公共調達はそこに大きなインパクトを与える。世界ではEU公共調達指令などが発効され、環境、社会に配慮する事が求められるようなっている。一方、日本の自治体では、いまだに競争が原則なっている。1999年地方自治法が改正され、「総合評価方式」が導入されるようになったにも関わらずまだ、環境・社会・経済を包括した取り組みは殆ど成されていない現状である。
そんな中、SDGsモデル都市のひとつである岡山市は総合評価方式を頻繁に実施している。環境負荷削減、地域防災協力を評価している。女性が輝く男女共同参画事業所認証を取得した企業には、建設工事の入札参加審査における格付けも決定時に加算するなどをしている。低金利融資制度や岡山市ホワイト+企業表彰にもいても加算されるようになっている。 岡山県でも岡山市と同様に環境、防災の取り組みを評価すると共に、入札の精神性の際に障がい者雇用、若年技術者雇用、女性技術者雇用、育児介護休業規定が加点項目となっている。横浜市の地域貢献型企業認証制度は先を一歩行くものである。
その後パネルディスカッションが行われ、横浜型地域貢献企業認定制度から学ぶべきポイントについて話題提供とディスカッションが行われました。
同制度は、地域を志向するCSRに取り組む企業を公的機関が認定するもので、産官学の5者が制度を運営しています。中小企業診断士等の評価員が訪問し確認後、外部専門家の認定委員会で決定され、2年間認められます。
CSRの考え方を理解し、利害関係者に対して戦略的な取組をしている。社内マネジメントを実施してPDCAサイクルを適切に運用している。地元横浜を意識したCSR活動を展開している。正し、同じことの繰り返しだけをしていては更新されません。
企業の社会的責任はCSR、NPO/NGOが果たすべき責任はNSR 自治体が果たすべき責任は、LGSR それぞれが持続可能な社会、地域づくりに向けて個々の責任を果たすと同時に連携していくことが重用として会を締めくくりました。
アンケートでは、「地域で頑張っている中小企業を応援してもらいたい」「人札制度を広域で共有できるようにする」「岡山市の歳出費 1274億円は驚いた」などの意見がありました。数多くのSDGsに関する情報に触れることで個人、団体が連携しやすくなるのではないかと感じた勉強会でした。

- OKAYAMA Share project ~おかやまをシェアしよう~ イベントレポート
誰もが社会を変えられる。 そんな可能性を、シェアしよう。
「OKAYAMA Share project」は、岡山..