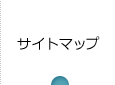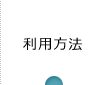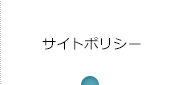タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
地域で活躍する人材を育てるには
地域課題・社会課題子ども
こんにちは、ゆうあいセンター CSR担当ならびにSDGsネットワークおかやまの事務局 小桐です。
今回は、山陽新聞社が昨年より、「令和時代の地域をつくる」として実施してきた、 連続シンポジウム の最終回 第5回 地域学のススメの概要を紹介します。
同シンポジウムの概要は、すでに9月20日の新聞記事にて紹介されています。また、詳報は10月11日の同紙に掲載されますので、ここでは、このシンポジウム開催に協力して開催された(主催:SDGsネットワークおかやま)事前ワークショップと当日のシンポジウムのつながりや当日のパネラーの発言などを紹介します。
なお、このシンポジウムでは毎回終了後にテーマに関して宣言文を採択してアピールしています。
今回は、最終回であるため、前4回の議論も統合する形での宣言文が発表される予定です。こちらも10月11日の山陽新聞でご確認ください。
コロナウイルスの影響で本来2月に開催されるシンポジウムが半年近く延びました。この間山陽新聞社と当日のモデレーターを務めるSDGsネットワークおかやまでは、開催までに事前検討の場を持ちました。
直前のワークショップでは、当日登壇されたパネラーのうち3名が参加されました。
地域学の実践現場の津山東高校 久常主幹教諭、松田 津山商工会議所会頭、中学・高校生と多世代の交流を支援するNPO法人だっぴ 柏原代表。 モデレーターは、当日と同じく、SDGsネットワークおかやま 石原会長と山陽新聞社 岡山編集員室長です。
このイベントには、教育関係者や企業、医療福祉、学生、NPO法人など幅広い参加がありました。
最初に、「高校生が地域で学ぶ意義」と題して学生が地域に出向き社会に関わり合いながら地域課題を解決することで地域への愛着や地域づくりを次世代人材の育成につながるとのことが話されました。
次に松田氏より産業や教育を地域で循環させることの重要性や地域と企業、大学などを含めてつながることが地域の持続可能性につながることなどが話されました。
柏原氏からは、だっぴの取組から学校へ関わる大学生がいることや地域の大人が足りないこと、中間支援の団体の必要性などが話されました。
話題提供を踏まえて各市町で誰(どんな組織)が関わるべきなのか?それはなぜか?をグループごとに意見交換しました。地域コーディネイターの重要性やお互いの関係性で補える資金調達、地域の大人との連携などが話されました。最後に石原氏より第5回シンポジウムに向けての論点整理として地域での人材育成ビジョンの共有や継続するための資源やお金を含めた仕組みづくりなどがあるとのまとめがあり閉会しました。
このワークショップの参加者のアンケートでは、学校が地域の大人を必要としていると思わなかった。やコミュニティの重要性に気づき、地域コミュニティをつくりたいのでアドバイスや支援が欲しいとの意見がありました。
シンポジウム当日の構成は、
基調講演で大正大学 浦崎教授が、「次世代の育成は地元のチーム化から」というテーマで事例を交えながらお話になりました。
今は、社会発展段階を数字でいうならば、Society3.0の工業社会を経て、4.0の情報社会に位置付けられる。(一部5.0 に突入している部分もあります。)
※総務省の定義
Society 5.0で実現する社会は、IoT(Internet of Things)で全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、これらの課題や困難を克服します。また、人工知能(AI)により、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服されます。社会の変革(イノベーション)を通じて、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合あえる社会、一人一人が快適で活躍できる社会。※
日本が国として成功したのは、3.0工業社会 この時代は、規格品を大量に生産する分業社会であり、求められたのは、均一な規格。個性は封印された時代。
しかし、4.0ネット・情報社会の今は、新しい価値創造が求められる時代。多様性が重視され、自分らしく、流動性が大きく、対話性・協力性が大きく求められ、反対に公助依存は小さくなっている。
農耕社会は、2.0 これは、土地に縛られる先祖伝来の生き方、今はそれが大きく変化しつつある。これまでの生まれ育った地域で生きていくから、よそ者、若者、ばか者が集まって、新しく地域を作る傾向が強くなっている。3人集まれば文殊の知恵。そして、このような社会背景を受けて教育も新しくなった。
個々人が、個別に最適な学びをして、地域課題を解決する。 ふるさと学習を通して、自分らしく社会に参加する時代。どのように社会、世界と関わり、より良い人生を送るかである。
そのために、興味がある分野の「専門性を高める」教育・学習が全国様々な高校で始まっている。
事例1:札幌市立藻岩高校 https://www.moiwa-h.sapporo-c.ed.jp/
では、3年間で教育、カリキュラム改革を行った。結果、高校生自身が勝手に動き出し、署名を集め、小学校跡の体育館を存続させるような行動に結びついている。 思い付き、提案、仮設の検証など、課題を解決するために欠かせないステップを、体験を通して学んでいる。
※大正大学では、雑誌 「地域人」を毎月発行し、地域で活躍する多くの人々から得た、前向きで積極的な"生"の情報を新鮮なまま提供しています。また、さまざまな取り組みや先進事例を解説、論説を加え紹介しています。ビジネスや生活に役立つことはもちろん、地域創生のテキストとしても活用していただけるような情報提供を目指しています。
バックナンバーの概要ならびに購入は以下のサイトです。
https://chiikijin.chikouken.org/chiikijin
56号では、地域が作るみんなの小学校というテーマで その中に浦崎教授の「高校連携で始まる人材循環」という記事が掲載されています。
事例2:岐阜県飛騨市 飛騨市学園ビジョン:目指す未来の創り手像 「志を語り合いしなやかに挑み続ける飛騨びと」
飛騨市学園構想 SUPER COMMUNITY CAMPUS PROJECTは、保育園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・家庭・地域が総がかりで、予測困難な時代を生きる子どもたちに、「幸福な人生と持続可能な社会の創り手となる力」を育もうというものです。その「願いや目標」を共有するためにリーフレットを作成したとあります。思い、その背景とともに、期待する人間像が描かれています。
https://www.city.hida.gifu.jp/uploaded/life/20111_33176_misc.pdf
事例3:大学生による、「高校を人材流失装置にしないために」シンポジウム。
東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科の有志による学生団体「SCH東北(SCH = Super Community High schoolの略称)」が主催して毎年行っている、教育系のイベントです。
高校・行政・民間などのセクターを越えたネットワークを形成し、地域と高校生の未来を切り開くアイデアを、参加者の方々と一緒に考えるもので、今年で6年目を迎えました。
https://www.tuad.ac.jp/2020/01/84195/
このイベントでは、20~30年後の社会、地域を考え、それぞれに地域をどうしていけばよいかの意見を出し合います。多様な主体の参加があり、その結果「自分の役割が認識できる」そうです。
未来が見えてくるので、スクールミッション「新しい時代の高校像」も見える。
未来から現在を見て、分断・孤立している人々に社会的な包摂を考えます。
この3事例の紹介後に、岡山での地域や人づくりの現状はどうかとの分析をされました。
人づくりの土壌は全国トップクラス。地域づくりの土壌も上位クラス。ただ、人づくりと地域づくりのつながりが弱いのが弱点。
人づくりと地域づくりを連携した横浜市 青葉区では、学生たちがシニア世代(引きこもりがち)にスマホの操作講座を行い、大好評。それぞれに、助けられている取組となっているとのことです。
後半のパネルディカッションでは、事前ワークショップにも参加された3パネラーに鍵本教育長と浦崎教授が加わりました。
冒頭、これからの教育について教育長より発言。実際の社会や生活で役立つ知識、技能と思考力・判断力・表現力が求められると同時に、学びに向かう力・人間性、即ち学んだことを人生・社会で生かしていこうとする力の両方が必要とされているとの説明がありました。
矢掛高校からスタートした地域学は、今では、おかやま創生高校パワーアップ事業として、広く県内の高校で行われている。
教育を通して社会を作る、学校と社会が「必要な資質は何か」を共有すること、地域と連携しながら考えることが必要と説明がありました。小規模高校では、地元自治体、企業、NPOが地域コーディネイターにより学校と連携するモデルも取り組まれています。
現場の久常先生からは、前回と同じく津山東高校で行っている地域学習と津山市内の4校が連携している学習について紹介がありました。
中学・高校生と多世代の交流を支援するだっぴ 柏原代表は、第3者で関わる限界についての課題を挙げました。交流のきっかけを作ることはできるが、その先地域でどのように考えるかについては、現状できていない。地域のビジョンがあって、交流すればもっと価値があるはず。そのためには、地域のステークホルダーがどのような役割を果たせばよいかを考えることが必要。
このビジョンづくりには、中高生も一緒に関わるとよい。
経済界の代表であるとともに県の教育委員を務める立場の松田会頭からは、美作圏域3市5町2村の経済団体は連携ができており、岡山大学と教育経済について連携を図っていること。留学からの津山の町の課題の指摘などをしている事例が紹介されました。
パネラーの発表をもとにモデレーターが、以下の5つの課題として整理しました。
① コーディネイターの確保 ⓶(コーディネイターの)財源確保 ③(地域の)ビジョンを誰が作るか ④地域を支えるコンソーシアム(チーム)をどう作るか ⑤全県下の理解、動きをどう作るか
イメージできれば人は動けるが、イメージできないと動かない。対話でイメージを共有できるというアドバイスが浦崎教授よりありました。
この5つの課題に対して各パネラーの意見を出すことで、議論を深めました。
教育長からは、地域にはどういう人が必要か?それをもとに高校生のこんな力をつけたい!ということを考え、次に何を実施するかを考えないといけない、逆の順番になってはいけない。
財源については、企業との連携を強調されました。
浦崎教授からは、学校の教師はエネルギーが残っていない状態。企業とタッグを組むと欲しい人材や元気、アイデアなどが得られる。地域でそれぞれの立場の人が、授業外、業務時間外に話し合いを持つことが必要。 資金面、求められる人材像で双方にメリットがあると言われました。
コーディネイターは、地域のことがわかっている人が望ましい。地域学で生徒は、変化する、それを見守る大人を増やし、コーディイターになってもらう。将来的には、地域学を学んだ高校生が大人になることで優秀なコーディネイターにもなる。などの意見が出されました。
コンソーシアムについては、現場で動く人達が本音で地域を考えることが重要。 自治体組織は縦割りなので、横断的中間支援組織としてのコンソーシアムが望ましい。そこに人材をプールし、コーディネイターやスペシャリストを派遣する。
全県下の課題として、小中学校は市の管轄、高校は県の管轄この連携が今後重要。就学前の幼稚園からの連携も含めて考えたいと教育長からまとめがありました。
当日、総合司会を務めた 津山東高校3年生の 渡辺さんにも意見を求め、1年生の時のボランティア体験が運命を変え、高校生活性が豊かなものとなり、地域関しての問題意識が高まった。という発言がありました。
地域づくりは人づくり、地域で活躍する人材を育てるには、何が必要かを確認できたシンポジウムでした。
今回は、山陽新聞社が昨年より、「令和時代の地域をつくる」として実施してきた、 連続シンポジウム の最終回 第5回 地域学のススメの概要を紹介します。
同シンポジウムの概要は、すでに9月20日の新聞記事にて紹介されています。また、詳報は10月11日の同紙に掲載されますので、ここでは、このシンポジウム開催に協力して開催された(主催:SDGsネットワークおかやま)事前ワークショップと当日のシンポジウムのつながりや当日のパネラーの発言などを紹介します。
なお、このシンポジウムでは毎回終了後にテーマに関して宣言文を採択してアピールしています。
今回は、最終回であるため、前4回の議論も統合する形での宣言文が発表される予定です。こちらも10月11日の山陽新聞でご確認ください。
コロナウイルスの影響で本来2月に開催されるシンポジウムが半年近く延びました。この間山陽新聞社と当日のモデレーターを務めるSDGsネットワークおかやまでは、開催までに事前検討の場を持ちました。
直前のワークショップでは、当日登壇されたパネラーのうち3名が参加されました。
地域学の実践現場の津山東高校 久常主幹教諭、松田 津山商工会議所会頭、中学・高校生と多世代の交流を支援するNPO法人だっぴ 柏原代表。 モデレーターは、当日と同じく、SDGsネットワークおかやま 石原会長と山陽新聞社 岡山編集員室長です。
このイベントには、教育関係者や企業、医療福祉、学生、NPO法人など幅広い参加がありました。
最初に、「高校生が地域で学ぶ意義」と題して学生が地域に出向き社会に関わり合いながら地域課題を解決することで地域への愛着や地域づくりを次世代人材の育成につながるとのことが話されました。
次に松田氏より産業や教育を地域で循環させることの重要性や地域と企業、大学などを含めてつながることが地域の持続可能性につながることなどが話されました。
柏原氏からは、だっぴの取組から学校へ関わる大学生がいることや地域の大人が足りないこと、中間支援の団体の必要性などが話されました。
話題提供を踏まえて各市町で誰(どんな組織)が関わるべきなのか?それはなぜか?をグループごとに意見交換しました。地域コーディネイターの重要性やお互いの関係性で補える資金調達、地域の大人との連携などが話されました。最後に石原氏より第5回シンポジウムに向けての論点整理として地域での人材育成ビジョンの共有や継続するための資源やお金を含めた仕組みづくりなどがあるとのまとめがあり閉会しました。
このワークショップの参加者のアンケートでは、学校が地域の大人を必要としていると思わなかった。やコミュニティの重要性に気づき、地域コミュニティをつくりたいのでアドバイスや支援が欲しいとの意見がありました。
シンポジウム当日の構成は、
基調講演で大正大学 浦崎教授が、「次世代の育成は地元のチーム化から」というテーマで事例を交えながらお話になりました。
今は、社会発展段階を数字でいうならば、Society3.0の工業社会を経て、4.0の情報社会に位置付けられる。(一部5.0 に突入している部分もあります。)
※総務省の定義
Society 5.0で実現する社会は、IoT(Internet of Things)で全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、これらの課題や困難を克服します。また、人工知能(AI)により、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服されます。社会の変革(イノベーション)を通じて、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合あえる社会、一人一人が快適で活躍できる社会。※
日本が国として成功したのは、3.0工業社会 この時代は、規格品を大量に生産する分業社会であり、求められたのは、均一な規格。個性は封印された時代。
しかし、4.0ネット・情報社会の今は、新しい価値創造が求められる時代。多様性が重視され、自分らしく、流動性が大きく、対話性・協力性が大きく求められ、反対に公助依存は小さくなっている。
農耕社会は、2.0 これは、土地に縛られる先祖伝来の生き方、今はそれが大きく変化しつつある。これまでの生まれ育った地域で生きていくから、よそ者、若者、ばか者が集まって、新しく地域を作る傾向が強くなっている。3人集まれば文殊の知恵。そして、このような社会背景を受けて教育も新しくなった。
個々人が、個別に最適な学びをして、地域課題を解決する。 ふるさと学習を通して、自分らしく社会に参加する時代。どのように社会、世界と関わり、より良い人生を送るかである。
そのために、興味がある分野の「専門性を高める」教育・学習が全国様々な高校で始まっている。
事例1:札幌市立藻岩高校 https://www.moiwa-h.sapporo-c.ed.jp/
では、3年間で教育、カリキュラム改革を行った。結果、高校生自身が勝手に動き出し、署名を集め、小学校跡の体育館を存続させるような行動に結びついている。 思い付き、提案、仮設の検証など、課題を解決するために欠かせないステップを、体験を通して学んでいる。
※大正大学では、雑誌 「地域人」を毎月発行し、地域で活躍する多くの人々から得た、前向きで積極的な"生"の情報を新鮮なまま提供しています。また、さまざまな取り組みや先進事例を解説、論説を加え紹介しています。ビジネスや生活に役立つことはもちろん、地域創生のテキストとしても活用していただけるような情報提供を目指しています。
バックナンバーの概要ならびに購入は以下のサイトです。
https://chiikijin.chikouken.org/chiikijin
56号では、地域が作るみんなの小学校というテーマで その中に浦崎教授の「高校連携で始まる人材循環」という記事が掲載されています。
事例2:岐阜県飛騨市 飛騨市学園ビジョン:目指す未来の創り手像 「志を語り合いしなやかに挑み続ける飛騨びと」
飛騨市学園構想 SUPER COMMUNITY CAMPUS PROJECTは、保育園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・家庭・地域が総がかりで、予測困難な時代を生きる子どもたちに、「幸福な人生と持続可能な社会の創り手となる力」を育もうというものです。その「願いや目標」を共有するためにリーフレットを作成したとあります。思い、その背景とともに、期待する人間像が描かれています。
https://www.city.hida.gifu.jp/uploaded/life/20111_33176_misc.pdf
事例3:大学生による、「高校を人材流失装置にしないために」シンポジウム。
東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科の有志による学生団体「SCH東北(SCH = Super Community High schoolの略称)」が主催して毎年行っている、教育系のイベントです。
高校・行政・民間などのセクターを越えたネットワークを形成し、地域と高校生の未来を切り開くアイデアを、参加者の方々と一緒に考えるもので、今年で6年目を迎えました。
https://www.tuad.ac.jp/2020/01/84195/
このイベントでは、20~30年後の社会、地域を考え、それぞれに地域をどうしていけばよいかの意見を出し合います。多様な主体の参加があり、その結果「自分の役割が認識できる」そうです。
未来が見えてくるので、スクールミッション「新しい時代の高校像」も見える。
未来から現在を見て、分断・孤立している人々に社会的な包摂を考えます。
この3事例の紹介後に、岡山での地域や人づくりの現状はどうかとの分析をされました。
人づくりの土壌は全国トップクラス。地域づくりの土壌も上位クラス。ただ、人づくりと地域づくりのつながりが弱いのが弱点。
人づくりと地域づくりを連携した横浜市 青葉区では、学生たちがシニア世代(引きこもりがち)にスマホの操作講座を行い、大好評。それぞれに、助けられている取組となっているとのことです。
後半のパネルディカッションでは、事前ワークショップにも参加された3パネラーに鍵本教育長と浦崎教授が加わりました。
冒頭、これからの教育について教育長より発言。実際の社会や生活で役立つ知識、技能と思考力・判断力・表現力が求められると同時に、学びに向かう力・人間性、即ち学んだことを人生・社会で生かしていこうとする力の両方が必要とされているとの説明がありました。
矢掛高校からスタートした地域学は、今では、おかやま創生高校パワーアップ事業として、広く県内の高校で行われている。
教育を通して社会を作る、学校と社会が「必要な資質は何か」を共有すること、地域と連携しながら考えることが必要と説明がありました。小規模高校では、地元自治体、企業、NPOが地域コーディネイターにより学校と連携するモデルも取り組まれています。
現場の久常先生からは、前回と同じく津山東高校で行っている地域学習と津山市内の4校が連携している学習について紹介がありました。
中学・高校生と多世代の交流を支援するだっぴ 柏原代表は、第3者で関わる限界についての課題を挙げました。交流のきっかけを作ることはできるが、その先地域でどのように考えるかについては、現状できていない。地域のビジョンがあって、交流すればもっと価値があるはず。そのためには、地域のステークホルダーがどのような役割を果たせばよいかを考えることが必要。
このビジョンづくりには、中高生も一緒に関わるとよい。
経済界の代表であるとともに県の教育委員を務める立場の松田会頭からは、美作圏域3市5町2村の経済団体は連携ができており、岡山大学と教育経済について連携を図っていること。留学からの津山の町の課題の指摘などをしている事例が紹介されました。
パネラーの発表をもとにモデレーターが、以下の5つの課題として整理しました。
① コーディネイターの確保 ⓶(コーディネイターの)財源確保 ③(地域の)ビジョンを誰が作るか ④地域を支えるコンソーシアム(チーム)をどう作るか ⑤全県下の理解、動きをどう作るか
イメージできれば人は動けるが、イメージできないと動かない。対話でイメージを共有できるというアドバイスが浦崎教授よりありました。
この5つの課題に対して各パネラーの意見を出すことで、議論を深めました。
教育長からは、地域にはどういう人が必要か?それをもとに高校生のこんな力をつけたい!ということを考え、次に何を実施するかを考えないといけない、逆の順番になってはいけない。
財源については、企業との連携を強調されました。
浦崎教授からは、学校の教師はエネルギーが残っていない状態。企業とタッグを組むと欲しい人材や元気、アイデアなどが得られる。地域でそれぞれの立場の人が、授業外、業務時間外に話し合いを持つことが必要。 資金面、求められる人材像で双方にメリットがあると言われました。
コーディネイターは、地域のことがわかっている人が望ましい。地域学で生徒は、変化する、それを見守る大人を増やし、コーディイターになってもらう。将来的には、地域学を学んだ高校生が大人になることで優秀なコーディネイターにもなる。などの意見が出されました。
コンソーシアムについては、現場で動く人達が本音で地域を考えることが重要。 自治体組織は縦割りなので、横断的中間支援組織としてのコンソーシアムが望ましい。そこに人材をプールし、コーディネイターやスペシャリストを派遣する。
全県下の課題として、小中学校は市の管轄、高校は県の管轄この連携が今後重要。就学前の幼稚園からの連携も含めて考えたいと教育長からまとめがありました。
当日、総合司会を務めた 津山東高校3年生の 渡辺さんにも意見を求め、1年生の時のボランティア体験が運命を変え、高校生活性が豊かなものとなり、地域関しての問題意識が高まった。という発言がありました。
地域づくりは人づくり、地域で活躍する人材を育てるには、何が必要かを確認できたシンポジウムでした。
- 中山間地域の高齢化・人口減少について
- 私は岡山県高梁市の出身です。高梁市は岡山県内有数の高齢化率の中山間地域であり、それ故に多くの問題を抱..