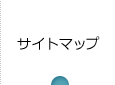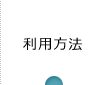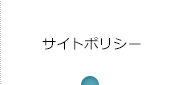タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
- 自分の“職能”を活かした新しいNPO支援。 「プロボノによるNPO等の情報発信・運営支援事業」
- なぜ今、NPOに情報開示が求められるのか。 「信頼できるNPO等を紹介するウェブサイトを活用した情報開示促進事業」
- 正しい理解が、NPOの力に。①「NPO新会計基準導入促進事業」
- 正しい理解が、NPOの力に。②「認定NPO法人取得促進事業」
- 気軽にはじめる社会貢献のすゝめ ~ガチャガチャリティと募金箱
- 割り勘で夢をかなえよう!第3期の募集がスタートしました。
- 施設送迎運転者講習会のレポート
- サマ★ボラキャンペーン!始めました!(ゆうあいセンター)
- 人と人をつなぐ「市(マルシェ)」 『備前福岡の市』編
- インターンシップ
「SDGsに関するグローバル・レポート 2019」の概要2-1
活動・取り組みその他
こんにちは、ゆうあいセンターCSR相談員 小桐です。
新型コロナウイルス感染による影響が世界的に広がりを見せ、日本も危機的な状況になりつつあることを切実に感じる今日この頃です。国民的コメディアンの志村けんさんがなくなり、ショックを受けた人も多いのではないでしょうか。岡山でも感染者が4人に増え、危機感が募ります。三菱自動車の休業は、県内の経済にも大きな打撃となりそうです。新学期はいつから始まるのか?くらし、経済についてとまどう日々です。
少し先の話になると思いますが、コロナウイルス収束後に、私たちは、どのような暮らしをすべきでしょうか?これまで以上に、くらし、経済、そして環境について「持続可能な、ありかた」を実践するようになるのではないかと考えています。
2015年から世界で取り組みの始まったSDGsですが、2019年までの取り組みがどうであったか、そして、今後私たちはどうあるべきかについて、客観的な証拠に基づいた「科学的知見」に基づいたレポート:「2030 アジェンダ」(SDGs)に関する「持続可能な開発に関するグローバル・レポート 2019」が発行されています。
今回は、その概要を紹介します。 1/3に内容を凝縮しましたがボリュームが多いので2回に分けています。
1回目は、レポートの位置づけや達成状況の報告。そして今後取るべき行動の項目を紹介します。 2回目はそれを受けて、具体的な取り組み6つのエントリーポイント(仕事)に関しての現状の紹介と解決のための行動について紹介します。今後、皆様が個人として、組織として取り組む業務や課題の参考としてお読みください。
アントニオ・グテーレス 国連事務総長はレポートの冒頭で下記のようにメッセージを世界に送っています。過去 4 年間の懸命な努力にもかかわらず、私たちは 2030 年までに「持続可能な開発目標」を達 成する軌道にはのっていない。私たちは 劇的に実施のペースを上げていかなければならない。
このレポートは、飢餓を終わらせ、気候変動に取り組み、不平等を是正し、「持続可能な開発目標」のすべてのゴールの進捗を加速させる科学の役割を強調しています。
また、私たちを支える自然システムが保護される一方、人間の福祉を公平かつ公正な方法で進め、誰一人取り 残さないという「2030 アジェンダ」(SDGs)のコンセプトも反映したものとなっています。
上記のことを実現するためには、「不平等」の現実を直視し、グローバルな開発アジェンダの中心に置いて考える必要があり、そうしないといつまでも問題は解決しない。貧困、差別、紛争、不平等 を生じさせている背後にある原因に取り組む政治的圧力が継続的に必要としています。
◆SDGsの達成の現状は下記のようになっています。
・世界は169 の殆どのターゲットを達成するための軌道にはのっていない。
・国際社会に強い懸念を引き起こし、警鐘を鳴らす。
・不平等の増大、気候変動、生物多様性の損失、及び処理能力を凌駕する廃棄物が増加。
・人間の福祉と健全な環境のバランスをとるという包括的な目標からは遠く離れている。
→相互関係を十分に理解していないか、 短期的な課題を不適切に優先させている。
・人間の福祉、社会的健康、環境に対して社会・環境・経済システムの緊急かつ意図的な変
革が必要。
・地球規模で持続可能なレベルでの資源利用で、基本的な人間のニーズを満たす国はまだ存
在していない。
・革新的な変化をもたらすために、さらに多く、迅速に達成する必要がある。障害となる政
策は早急に取り除くか修正されるべき。
・現行 のビジネス(business as usual)モデルから本質的かつ意図的に離脱するべき。
・最初に成長し、その後でクリーンアップするという現在の慣行から脱却し、それぞれの国
に特有の条件と優先課題に効果的に対応する必要がある。
そのためには、「SDGsを自分事とする」ことが重要だとレポートに記載されています。
そのためには、
◆すべての人が「人間活動と自然界の関係を裏付ける科学的現実を理解し、自らのものとする」こと。
◆「自分自身にも責任がある。人ごとではない、自分事として受けとめ、行動する」必要がある。(国や行政任せではいけない)すべての国家の首脳、すべての政府及びすべての市民が、「持続可能な開発目 標」の達成に責任を負っている
この2点は、絶対に覚えておかなければなりません。
◆では、何をすればよいのか
・不平等な秩序を維持しようとする政治的、ビジネス的、経済的な既得権益に立ち向かう勇気:「長いものに巻かれてはいけない。」→森友問題で自殺した赤木さん思いやその無念を晴らそうと事実の確認をしようとする奥さんの訴訟はまさに典型的な事例ではないでしょうか
・現在の不平等を是正するためには、低炭素経済への移行がもたらす機会を活かす必要
→化石燃料・資源に頼る限り、持つもの持たないものが存在し、不平等は解消しない。地球環境を破壊するこの産業・経済の在り方は破綻する、経済と環境は表裏一体ということを
自覚し、行動する必要がある。
・公共部門と民間部門の両方で、狭い自己利益ではなく、 共通の利益の実現に向け機能する政策を促進する必要。→今までの概念に縛られない、これまでにない協働を行う必要がある。
◆行動するときに気を付けておくべきこと
最も効率的な(または唯一の)方法は、他の目標とのプラスの相乗効果を利用し、さらに他の目標とのマイナスのトレードオフを解決または改善すること→我もよし、人も良しの視点が重要。多角度から見て、新しい発想で、必ずみんなが納得できる方法を考える。
◆今後取り組むべき仕事¬=「エントリーポイント」(これをすれば、個人、自社・自組織、社会も、地球も持続可能になる →これをしないと生き延びられない。
世界の政治家や政策立案者は、これらに十分留意する必要がある。
A.人間の福祉と能力(の強化)
B.持続可能で公正な経済(への移行)
C.(持続可能な)食料システムと健康的な栄養パターン(の構築)
D.エネルギーの脱炭素化とエネルギーへの普遍的アクセス
E.持続可能な都市及び都市周辺部の開発(の促進)
F.地球環境コモンズ(の確保) コモンズ:誰でも自由に利用できる状態にある共有資源
上記6つの仕事を行う際に、必要な変革をもたらすために一貫して展開する 4 つの手段
・ガバナンス(統治。支配。管理。また、そのための機構や方法)
・経済とファイナンス
・個別または共同の行動
・科学と技術を相互に関連付けさせる。
ここまでが第1回目の内容です。次回は、今後取り組むべき6つの仕事(エントリーポイント)はどんな状況にあるのか
「人間活動と自然界の関係を裏付ける科学的現実を理解し、自らのものとする」ために以下レポートに記載されている内容を紹介します。
新型コロナウイルス感染による影響が世界的に広がりを見せ、日本も危機的な状況になりつつあることを切実に感じる今日この頃です。国民的コメディアンの志村けんさんがなくなり、ショックを受けた人も多いのではないでしょうか。岡山でも感染者が4人に増え、危機感が募ります。三菱自動車の休業は、県内の経済にも大きな打撃となりそうです。新学期はいつから始まるのか?くらし、経済についてとまどう日々です。
少し先の話になると思いますが、コロナウイルス収束後に、私たちは、どのような暮らしをすべきでしょうか?これまで以上に、くらし、経済、そして環境について「持続可能な、ありかた」を実践するようになるのではないかと考えています。
2015年から世界で取り組みの始まったSDGsですが、2019年までの取り組みがどうであったか、そして、今後私たちはどうあるべきかについて、客観的な証拠に基づいた「科学的知見」に基づいたレポート:「2030 アジェンダ」(SDGs)に関する「持続可能な開発に関するグローバル・レポート 2019」が発行されています。
今回は、その概要を紹介します。 1/3に内容を凝縮しましたがボリュームが多いので2回に分けています。
1回目は、レポートの位置づけや達成状況の報告。そして今後取るべき行動の項目を紹介します。 2回目はそれを受けて、具体的な取り組み6つのエントリーポイント(仕事)に関しての現状の紹介と解決のための行動について紹介します。今後、皆様が個人として、組織として取り組む業務や課題の参考としてお読みください。
アントニオ・グテーレス 国連事務総長はレポートの冒頭で下記のようにメッセージを世界に送っています。過去 4 年間の懸命な努力にもかかわらず、私たちは 2030 年までに「持続可能な開発目標」を達 成する軌道にはのっていない。私たちは 劇的に実施のペースを上げていかなければならない。
このレポートは、飢餓を終わらせ、気候変動に取り組み、不平等を是正し、「持続可能な開発目標」のすべてのゴールの進捗を加速させる科学の役割を強調しています。
また、私たちを支える自然システムが保護される一方、人間の福祉を公平かつ公正な方法で進め、誰一人取り 残さないという「2030 アジェンダ」(SDGs)のコンセプトも反映したものとなっています。
上記のことを実現するためには、「不平等」の現実を直視し、グローバルな開発アジェンダの中心に置いて考える必要があり、そうしないといつまでも問題は解決しない。貧困、差別、紛争、不平等 を生じさせている背後にある原因に取り組む政治的圧力が継続的に必要としています。
◆SDGsの達成の現状は下記のようになっています。
・世界は169 の殆どのターゲットを達成するための軌道にはのっていない。
・国際社会に強い懸念を引き起こし、警鐘を鳴らす。
・不平等の増大、気候変動、生物多様性の損失、及び処理能力を凌駕する廃棄物が増加。
・人間の福祉と健全な環境のバランスをとるという包括的な目標からは遠く離れている。
→相互関係を十分に理解していないか、 短期的な課題を不適切に優先させている。
・人間の福祉、社会的健康、環境に対して社会・環境・経済システムの緊急かつ意図的な変
革が必要。
・地球規模で持続可能なレベルでの資源利用で、基本的な人間のニーズを満たす国はまだ存
在していない。
・革新的な変化をもたらすために、さらに多く、迅速に達成する必要がある。障害となる政
策は早急に取り除くか修正されるべき。
・現行 のビジネス(business as usual)モデルから本質的かつ意図的に離脱するべき。
・最初に成長し、その後でクリーンアップするという現在の慣行から脱却し、それぞれの国
に特有の条件と優先課題に効果的に対応する必要がある。
そのためには、「SDGsを自分事とする」ことが重要だとレポートに記載されています。
そのためには、
◆すべての人が「人間活動と自然界の関係を裏付ける科学的現実を理解し、自らのものとする」こと。
◆「自分自身にも責任がある。人ごとではない、自分事として受けとめ、行動する」必要がある。(国や行政任せではいけない)すべての国家の首脳、すべての政府及びすべての市民が、「持続可能な開発目 標」の達成に責任を負っている
この2点は、絶対に覚えておかなければなりません。
◆では、何をすればよいのか
・不平等な秩序を維持しようとする政治的、ビジネス的、経済的な既得権益に立ち向かう勇気:「長いものに巻かれてはいけない。」→森友問題で自殺した赤木さん思いやその無念を晴らそうと事実の確認をしようとする奥さんの訴訟はまさに典型的な事例ではないでしょうか
・現在の不平等を是正するためには、低炭素経済への移行がもたらす機会を活かす必要
→化石燃料・資源に頼る限り、持つもの持たないものが存在し、不平等は解消しない。地球環境を破壊するこの産業・経済の在り方は破綻する、経済と環境は表裏一体ということを
自覚し、行動する必要がある。
・公共部門と民間部門の両方で、狭い自己利益ではなく、 共通の利益の実現に向け機能する政策を促進する必要。→今までの概念に縛られない、これまでにない協働を行う必要がある。
◆行動するときに気を付けておくべきこと
最も効率的な(または唯一の)方法は、他の目標とのプラスの相乗効果を利用し、さらに他の目標とのマイナスのトレードオフを解決または改善すること→我もよし、人も良しの視点が重要。多角度から見て、新しい発想で、必ずみんなが納得できる方法を考える。
◆今後取り組むべき仕事¬=「エントリーポイント」(これをすれば、個人、自社・自組織、社会も、地球も持続可能になる →これをしないと生き延びられない。
世界の政治家や政策立案者は、これらに十分留意する必要がある。
A.人間の福祉と能力(の強化)
B.持続可能で公正な経済(への移行)
C.(持続可能な)食料システムと健康的な栄養パターン(の構築)
D.エネルギーの脱炭素化とエネルギーへの普遍的アクセス
E.持続可能な都市及び都市周辺部の開発(の促進)
F.地球環境コモンズ(の確保) コモンズ:誰でも自由に利用できる状態にある共有資源
上記6つの仕事を行う際に、必要な変革をもたらすために一貫して展開する 4 つの手段
・ガバナンス(統治。支配。管理。また、そのための機構や方法)
・経済とファイナンス
・個別または共同の行動
・科学と技術を相互に関連付けさせる。
ここまでが第1回目の内容です。次回は、今後取り組むべき6つの仕事(エントリーポイント)はどんな状況にあるのか
「人間活動と自然界の関係を裏付ける科学的現実を理解し、自らのものとする」ために以下レポートに記載されている内容を紹介します。

- 自分の“職能”を活かした新しいNPO支援。 「プロボノによるNPO等の情報発信・運営支援事業」
- プロボノとは、今までの “労働力を提供するボランティア” とは異なり、様々な分野のプロが自分たちの専..