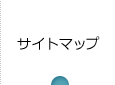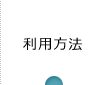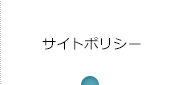タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
- 自分の“職能”を活かした新しいNPO支援。 「プロボノによるNPO等の情報発信・運営支援事業」
- なぜ今、NPOに情報開示が求められるのか。 「信頼できるNPO等を紹介するウェブサイトを活用した情報開示促進事業」
- 正しい理解が、NPOの力に。①「NPO新会計基準導入促進事業」
- 正しい理解が、NPOの力に。②「認定NPO法人取得促進事業」
- 気軽にはじめる社会貢献のすゝめ ~ガチャガチャリティと募金箱
- 割り勘で夢をかなえよう!第3期の募集がスタートしました。
- 施設送迎運転者講習会のレポート
- サマ★ボラキャンペーン!始めました!(ゆうあいセンター)
- 人と人をつなぐ「市(マルシェ)」 『備前福岡の市』編
- インターンシップ
「SDGsがまたまた身近に その2 高校生とSDGs」
活動・取り組み環境
こんにちは、ゆうあいセンターCSR相談員 小桐です。
2019年最初の投稿です。今回は、SDGsに関する、2つの話題提供です。
年始より、ゆうあいセンターの「SDGs情報コーナー」に地元岡山でのSDGsの取組情報ファイルを設置しました。企業・経済界、教育機関、NPO/NGO,自治体の取組について情報を提供するものです。
今年に入り、SDGsに関しての情報が地元山陽新聞でも数多くみられるようになりました。SDGsがお茶の間の話題になる日も近いと思われます。 今回は、身近な話題となるべく「高校生とSDGs」の取組について2つの話題を紹介します。
1.山陽女子中学・高校 地歴部が 第2回SDGsアワード特別賞受賞
国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)の取組みの普及に向け、2017年度よりSDGsアワードが開催されており、2018年度の受賞団体の一つとして、山陽女子中学・高校 地歴部が特別賞を受賞しました。12月21日に首相官邸で表彰式が開催され、生徒の代表2名が出席しました。初年度は、岡山大学が、特別賞を受賞しており、岡山の教育機関が2年連続で受賞したことになります。
同部の活動は、2008年から始まっており、10年の長い間の時間と地域を巻き込んだ活動として評価されました。
どの様な活動かというと今話題になっている「海ごみ問題」への取組です。閉鎖水域である瀬戸内海の岡山県沖で、島などに漂着したゴミを収集し、分別・分析を行っています。
特に食品関係のプラスチック容器は、そのラベル表示などを調べ、発生源や漂流経路などを明らかにして、これまで、その結果や成果を出前授業やシンポジウムで発表、紹介してきました。
私も昨年、その発表を聴き、ワークショップで今後どのようにして、海ごみを減らすかということを体験しました。
元々、海ごみは陸上のゴミ、川を通って海に流れます。瀬戸内の海ごみはまず、殆ど国産です。
ごみは、漂流して、岸に流れ着くものだけでなく、海底に沈んでしまうものも有ります。沈んだごみは、海底の環境に影響を与え、漁業関係者にも被害を与えます。漂着ゴミには軽いものが多く、プラスチック類が多いようです。これが波や風、太陽の影響で細かく分解されると、プランクトンが食べるまでのサイズにまでなります。食物連鎖の関係で、やがて人間の体内にまで取り込まれ、健康問題となることが、世界的に懸念され、欧米やアジアの各国は、使い捨てプラスチックを禁止する行動をとるようになっています。
彼女たちの活動は、SDGsの17の目標の内、「人や国の不平等をなくそう」「海の豊かさを守ろう」など5項目に関係するとされています。海ごみで一番多いのは、やはりレジ袋関係です。以前から矢掛高校の生徒たちが、笠岡市白石島で漂着ゴミを学ぶ活動を行っていて、マイバッグ普及の活動を展開していました。
私たちに出来る事は、まず、これ以上海にごみが流れつかないように、レジ袋利用やきちんとしたごみの持ち帰りを実行することではないでしょうか?
2.中学・高校生が考えるSDGs 18番目の目標
前回ご紹介した、12月初旬、東京で開催された「エコプロダク展」には数多くの学校が出展していました。その中で、目を引いたのが名古屋国際中・高ブースです。
「SUS-TEEN 持続可能な10代の若者らしい活動」 として、「フェアトレードペーパー」=公正な貿易によるバナナの茎から採った繊維から作った紙の普及をアピールしていました。アフリカのザンビアと日本で共同開発したものです。この紙を購入することで、ザンビアでの雇用とその収入による貧困からの脱出=子供たちの就学推進、ソーラーランプの購入(パナソニックコーナーで展示されていたものと類似)、マラリア予防につながるという活動です。
自分たちで名刺を作り、裏面には上記の説明内容を記載していました。若い世代に興味を持ってもらうために、ガチャガチャも準備していて、試してみるとカプセルの中からは次のような自分たちの活動を紹介する文面とメッセージが出ました。自分たちで地元の著名人にインタビューをしてまとめたものが数種類入っているとのことでした。
そのブースで一番感動したのは、SDGsの18番目の目標を自分たちで考え出してアピールしていたことでした。その発想とともに内容にも驚かされました。SDGsは17の目標と169のターゲットが設定されています。
この方式に則って、18番目の目標を考えていました。
「18 若者のアイデアが活かせる環境を」というものです。さらに、18.1~18.6までの6つのターゲットも考えていました。
18.1 若者が挑戦しようとする環境づくりをする。
18.2若者が学校以外で創造性のある知識を身につけられる機会をつくる。若者が積極的に外部にでようとする。
18.3 答えのない教育を重視する。1か2でなく、0から1を作り出せるようにする。批判的な思考を持ち新たなアイデアを生み出す。
18.4 純粋にやってみようという気持ちを持つ。人と違う場所へ行ったり、本を読むことを大切にする。人に興味を持ち、であったことのない人に会ってみる。
18.5 小・中・高・大生が中心となって、持続可能な社会をつくる。
18.6 世界共通の若者DAYをつくる。
顧問の先生に伺うと自分たちが考えて行動しているとのことで、自分は付き添いだけです。とおっしゃっていました。がその機会を提供しうる先生の環境づくりは立派です。
同校は、文科省に認定された、スパーグローバルハイスクールかつ、「平成28年度日本/ユネスコパートナーシップ事業」の一環として、ESD(持続開発教育)に取り組む全国の学校のうち、公募から選ばれた取り組む意欲のある学校である「サステナブルスクール」であり、ユネスコスクール(1地球規模の問題に対する国連システムの理解、2人権、民主主義の理解と促進、3異文化理解、4環境教育を積極的に学ぶ)でもあるために生徒たちの意識も高く、このレベルまで行動することができたと思われます。
岡山の学校でもユネスコスクールに加盟している学校もあり、今後この学校同じような活動が広がれば良いと強く思いました。ゆうあいセンターとしても協働の場づくりのハブとなるように努めていきたいと考えます。
2019年最初の投稿です。今回は、SDGsに関する、2つの話題提供です。
年始より、ゆうあいセンターの「SDGs情報コーナー」に地元岡山でのSDGsの取組情報ファイルを設置しました。企業・経済界、教育機関、NPO/NGO,自治体の取組について情報を提供するものです。
今年に入り、SDGsに関しての情報が地元山陽新聞でも数多くみられるようになりました。SDGsがお茶の間の話題になる日も近いと思われます。 今回は、身近な話題となるべく「高校生とSDGs」の取組について2つの話題を紹介します。
1.山陽女子中学・高校 地歴部が 第2回SDGsアワード特別賞受賞
国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)の取組みの普及に向け、2017年度よりSDGsアワードが開催されており、2018年度の受賞団体の一つとして、山陽女子中学・高校 地歴部が特別賞を受賞しました。12月21日に首相官邸で表彰式が開催され、生徒の代表2名が出席しました。初年度は、岡山大学が、特別賞を受賞しており、岡山の教育機関が2年連続で受賞したことになります。
同部の活動は、2008年から始まっており、10年の長い間の時間と地域を巻き込んだ活動として評価されました。
どの様な活動かというと今話題になっている「海ごみ問題」への取組です。閉鎖水域である瀬戸内海の岡山県沖で、島などに漂着したゴミを収集し、分別・分析を行っています。
特に食品関係のプラスチック容器は、そのラベル表示などを調べ、発生源や漂流経路などを明らかにして、これまで、その結果や成果を出前授業やシンポジウムで発表、紹介してきました。
私も昨年、その発表を聴き、ワークショップで今後どのようにして、海ごみを減らすかということを体験しました。
元々、海ごみは陸上のゴミ、川を通って海に流れます。瀬戸内の海ごみはまず、殆ど国産です。
ごみは、漂流して、岸に流れ着くものだけでなく、海底に沈んでしまうものも有ります。沈んだごみは、海底の環境に影響を与え、漁業関係者にも被害を与えます。漂着ゴミには軽いものが多く、プラスチック類が多いようです。これが波や風、太陽の影響で細かく分解されると、プランクトンが食べるまでのサイズにまでなります。食物連鎖の関係で、やがて人間の体内にまで取り込まれ、健康問題となることが、世界的に懸念され、欧米やアジアの各国は、使い捨てプラスチックを禁止する行動をとるようになっています。
彼女たちの活動は、SDGsの17の目標の内、「人や国の不平等をなくそう」「海の豊かさを守ろう」など5項目に関係するとされています。海ごみで一番多いのは、やはりレジ袋関係です。以前から矢掛高校の生徒たちが、笠岡市白石島で漂着ゴミを学ぶ活動を行っていて、マイバッグ普及の活動を展開していました。
私たちに出来る事は、まず、これ以上海にごみが流れつかないように、レジ袋利用やきちんとしたごみの持ち帰りを実行することではないでしょうか?
2.中学・高校生が考えるSDGs 18番目の目標
前回ご紹介した、12月初旬、東京で開催された「エコプロダク展」には数多くの学校が出展していました。その中で、目を引いたのが名古屋国際中・高ブースです。
「SUS-TEEN 持続可能な10代の若者らしい活動」 として、「フェアトレードペーパー」=公正な貿易によるバナナの茎から採った繊維から作った紙の普及をアピールしていました。アフリカのザンビアと日本で共同開発したものです。この紙を購入することで、ザンビアでの雇用とその収入による貧困からの脱出=子供たちの就学推進、ソーラーランプの購入(パナソニックコーナーで展示されていたものと類似)、マラリア予防につながるという活動です。
自分たちで名刺を作り、裏面には上記の説明内容を記載していました。若い世代に興味を持ってもらうために、ガチャガチャも準備していて、試してみるとカプセルの中からは次のような自分たちの活動を紹介する文面とメッセージが出ました。自分たちで地元の著名人にインタビューをしてまとめたものが数種類入っているとのことでした。
そのブースで一番感動したのは、SDGsの18番目の目標を自分たちで考え出してアピールしていたことでした。その発想とともに内容にも驚かされました。SDGsは17の目標と169のターゲットが設定されています。
この方式に則って、18番目の目標を考えていました。
「18 若者のアイデアが活かせる環境を」というものです。さらに、18.1~18.6までの6つのターゲットも考えていました。
18.1 若者が挑戦しようとする環境づくりをする。
18.2若者が学校以外で創造性のある知識を身につけられる機会をつくる。若者が積極的に外部にでようとする。
18.3 答えのない教育を重視する。1か2でなく、0から1を作り出せるようにする。批判的な思考を持ち新たなアイデアを生み出す。
18.4 純粋にやってみようという気持ちを持つ。人と違う場所へ行ったり、本を読むことを大切にする。人に興味を持ち、であったことのない人に会ってみる。
18.5 小・中・高・大生が中心となって、持続可能な社会をつくる。
18.6 世界共通の若者DAYをつくる。
顧問の先生に伺うと自分たちが考えて行動しているとのことで、自分は付き添いだけです。とおっしゃっていました。がその機会を提供しうる先生の環境づくりは立派です。
同校は、文科省に認定された、スパーグローバルハイスクールかつ、「平成28年度日本/ユネスコパートナーシップ事業」の一環として、ESD(持続開発教育)に取り組む全国の学校のうち、公募から選ばれた取り組む意欲のある学校である「サステナブルスクール」であり、ユネスコスクール(1地球規模の問題に対する国連システムの理解、2人権、民主主義の理解と促進、3異文化理解、4環境教育を積極的に学ぶ)でもあるために生徒たちの意識も高く、このレベルまで行動することができたと思われます。
岡山の学校でもユネスコスクールに加盟している学校もあり、今後この学校同じような活動が広がれば良いと強く思いました。ゆうあいセンターとしても協働の場づくりのハブとなるように努めていきたいと考えます。

- 自分の“職能”を活かした新しいNPO支援。 「プロボノによるNPO等の情報発信・運営支援事業」
- プロボノとは、今までの “労働力を提供するボランティア” とは異なり、様々な分野のプロが自分たちの専..