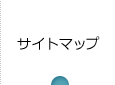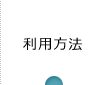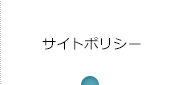タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
「仙台市 地元企業のCSRに関するニーズ調査報告」
地域課題・社会課題その他
こんにちは、ゆうあいセンターCSR相談員 小桐です。
新しい、CSRに関する情報が入りましたのでお知らせします。仙台市の社会福祉法人仙台社会福祉協議会・仙台市ボランティアセンターが行った「仙台市内の企業における社会貢献・CSR活動に関するアンケート」調査報告です。
仙台市といえば、東北地方で一番人口の多い都市で、文字通り経済・文化交流の中心都市です。人口は108万人を超え、岡山市の1.5倍の規模の年です。日本のユネスコ運動の発祥の地であり、岡山市と共にESDの取組の先進地の一つです。
東日本大震災では、多くの方が被害を受けられた一方、寄付をはじめ、ボランティアとしての人材、企業やその社員が持つ様々な専門スキルや技術が提供され、被災者の支援はもとより、被災地の復旧・復興に向けて大きな役割を担った方々が住む地域でもあります。ある意味での、今夏の水害で被害を受けた、岡山市や倉敷市の先輩的存在の面もあるように思います。
さて、その仙台市でも地域福祉の現状は、活動の担い手不足、人材不足が大きな課題となっているそうです。
これまでの住民中心の組織だけでは、地域の福祉活動を進める事難しい状況となっており、その課題の解決のために、多様な立場の人々が主体的に日常の地域福祉活動に継続的に参加していく意識を高める必要があり、その一環として、実態調査を行いました。
2018年2月中旬から末までにかけて、市内の企業1610社を対象に実施。327社の回答があり、回答率は20.3%でした。東北学院大学経営学部 矢口義教教授の助言・協力で実施されました。
業種的には、建設業が20.8%でトップ、次にサービス業、卸・商社が3番目でした。従業員数は、100人未満が全体の80%を占め、資本金1000万円以上3000万円未満が32.1%で一番多く、まさに地元の中小企業の意向が見える化された調査となりました。
「社会貢献・CSR活動」の認知度という点では、良く知っている45.6%、言葉だけ知っている33.6%で合計すると79.2%という高い認知率でした。2011年の震災で復旧・復興のために多くの企業や社員が活動や支援をされたことで「社会貢献・CSR(企業の社会的責任や対応)」ということと推測されます。
「社会貢献・CSR活動の取組状況」では、現在取り組んでいるが41.9%、今後取り組む予定が17.4%、現在はないか過去取り組んだ7.6%となっています。6割弱が取組の意志があるということです。
「活動分野」では、複数回答で、「地域イベント」39.2%が1位、「環境・自然保護」36.7%、「まちづくり」25.6%と続いています。地元密着型の活動が見えてきます。
今後の活動分野としては、「災害支援活動」57%「高齢者支援」13.1%となっています。福祉面での活動の意志が見られます。
活動の取組に関する記述式回答では、環境自然保護が一番多く、33.5% 「広瀬川流域一斉清掃」「被災した防風林の苗木購入資金積み立て」などありました。基本は地域清掃活動が一番多く取り組みやすさから考えられるものです。
地域のイベントに関する記述式回答では、「まちづくり基金の設立・助成」やチャリティーイベントの開催、子どもの虐待防止に関する活動、養護施設での子供との交流など地域に根差した支援活動に取り組んでいる事例回答が見られました。津波の被害を受けた方々が多くのその反映ということも考えられそうです。
今後、社会貢献・CSRの取組に必要な支援・環境についての回答では、104件の自由記述回答が有り、「活動環境の整備・支援」が54.8%で1位。「情報支援」が26%で2位でした。3位に「広報支援」がありました。
一番高いニーズの「環境整備支援」では、活動の始め方や継続するための相談支援、活動に使える助成金・補助金の制度紹介、税制優遇や社会貢献企業の優先発注などの意見・要望が寄せられました。
「情報支援」では、ボランティア募集情報や支援を必要とする個人、団体の要請情報、他社支援事例紹介などがありました。「広報支援」では、取り組み事例を第3者より広報、PRしてほしいという意見、公表制度、表彰制度等がありました。
短期間にこれだけのデータを収集され、分析されかつ、広報いただいた社会福祉法人仙台社会福祉協議会・仙台市ボランティアセンターには、心から感謝し、ゆうあいセンターの今後の活動の参考にさせて頂きたいと感じました。資料は、ゆうあいセンター 真ん中付近、CSR書籍コーナーに配架していますので、自由にご覧ください。
CSRの時流は、慈善活動:ボランティアや寄付、など企業・個人の持ち出しで行う活動がCSR1.0として
基本に有りながらもそれだけでは、持続性にリスクがあるため、企業の事業継続という観点から、事業活動と社会貢献を併せた寄付付き事業:コーズマーケティング(売り上げの1部を寄付する)等に拡がりを見せています。
CSR2.0という呼び方もあります。
若い世代を中心に、購入による社会貢献商品やサービスを認める傾向があります。企業の情報開示と共に、その姿勢・事業活動を購入行動で支援し、良い社会づくりに参加しようとするものです。
「買い物はその企業への投票」ということです。それだけに、企業の理念、事業を情報開示する「CSRレポート」への取組みが重要性を高めると共に、情報発信に時間を割きにくい企業は、表彰制度や公表制度を求めるということだと仙台市のアンケート結果を見ると考えられます。
これまで、CSR・社会貢献は、自社からの持ち出しという考えが支配的でしたが、今は大きく社会が変化しています。 国連加盟国全てが認めた「SDGs」(2030年までに世界で多様な人々が解決すべき17の目標)の取組が今後企業やNPOにおいても、より普及していくと考えられます。それにより、社会貢献の概念が持ち出しオンリーから「共有価値で双方の利益づくり」へと広がっていくと考えられます。
本業である事業活動と17の社会課題SDGsを結び付け、企業の経営の中心において、行こうとするCSR3.0の時代へと向かっています。NPOや地域課題の解決に取り組む団体や自治体とのコラボ(協働)によって、ハッピーハッピーの関係を築こうとするものです。
CSRは、「持ち出しの時代」から、利害関係者と組んで事業を行い、「儲けて社会を良くする(社会貢献)する時代」の普及に向け、NPOと企業のマッチングなどが出来るように、双方に対して、情報収集・発信、啓蒙活動をゆうあいセンターとしても今後注力していこうと考えます。
新しい、CSRに関する情報が入りましたのでお知らせします。仙台市の社会福祉法人仙台社会福祉協議会・仙台市ボランティアセンターが行った「仙台市内の企業における社会貢献・CSR活動に関するアンケート」調査報告です。
仙台市といえば、東北地方で一番人口の多い都市で、文字通り経済・文化交流の中心都市です。人口は108万人を超え、岡山市の1.5倍の規模の年です。日本のユネスコ運動の発祥の地であり、岡山市と共にESDの取組の先進地の一つです。
東日本大震災では、多くの方が被害を受けられた一方、寄付をはじめ、ボランティアとしての人材、企業やその社員が持つ様々な専門スキルや技術が提供され、被災者の支援はもとより、被災地の復旧・復興に向けて大きな役割を担った方々が住む地域でもあります。ある意味での、今夏の水害で被害を受けた、岡山市や倉敷市の先輩的存在の面もあるように思います。
さて、その仙台市でも地域福祉の現状は、活動の担い手不足、人材不足が大きな課題となっているそうです。
これまでの住民中心の組織だけでは、地域の福祉活動を進める事難しい状況となっており、その課題の解決のために、多様な立場の人々が主体的に日常の地域福祉活動に継続的に参加していく意識を高める必要があり、その一環として、実態調査を行いました。
2018年2月中旬から末までにかけて、市内の企業1610社を対象に実施。327社の回答があり、回答率は20.3%でした。東北学院大学経営学部 矢口義教教授の助言・協力で実施されました。
業種的には、建設業が20.8%でトップ、次にサービス業、卸・商社が3番目でした。従業員数は、100人未満が全体の80%を占め、資本金1000万円以上3000万円未満が32.1%で一番多く、まさに地元の中小企業の意向が見える化された調査となりました。
「社会貢献・CSR活動」の認知度という点では、良く知っている45.6%、言葉だけ知っている33.6%で合計すると79.2%という高い認知率でした。2011年の震災で復旧・復興のために多くの企業や社員が活動や支援をされたことで「社会貢献・CSR(企業の社会的責任や対応)」ということと推測されます。
「社会貢献・CSR活動の取組状況」では、現在取り組んでいるが41.9%、今後取り組む予定が17.4%、現在はないか過去取り組んだ7.6%となっています。6割弱が取組の意志があるということです。
「活動分野」では、複数回答で、「地域イベント」39.2%が1位、「環境・自然保護」36.7%、「まちづくり」25.6%と続いています。地元密着型の活動が見えてきます。
今後の活動分野としては、「災害支援活動」57%「高齢者支援」13.1%となっています。福祉面での活動の意志が見られます。
活動の取組に関する記述式回答では、環境自然保護が一番多く、33.5% 「広瀬川流域一斉清掃」「被災した防風林の苗木購入資金積み立て」などありました。基本は地域清掃活動が一番多く取り組みやすさから考えられるものです。
地域のイベントに関する記述式回答では、「まちづくり基金の設立・助成」やチャリティーイベントの開催、子どもの虐待防止に関する活動、養護施設での子供との交流など地域に根差した支援活動に取り組んでいる事例回答が見られました。津波の被害を受けた方々が多くのその反映ということも考えられそうです。
今後、社会貢献・CSRの取組に必要な支援・環境についての回答では、104件の自由記述回答が有り、「活動環境の整備・支援」が54.8%で1位。「情報支援」が26%で2位でした。3位に「広報支援」がありました。
一番高いニーズの「環境整備支援」では、活動の始め方や継続するための相談支援、活動に使える助成金・補助金の制度紹介、税制優遇や社会貢献企業の優先発注などの意見・要望が寄せられました。
「情報支援」では、ボランティア募集情報や支援を必要とする個人、団体の要請情報、他社支援事例紹介などがありました。「広報支援」では、取り組み事例を第3者より広報、PRしてほしいという意見、公表制度、表彰制度等がありました。
短期間にこれだけのデータを収集され、分析されかつ、広報いただいた社会福祉法人仙台社会福祉協議会・仙台市ボランティアセンターには、心から感謝し、ゆうあいセンターの今後の活動の参考にさせて頂きたいと感じました。資料は、ゆうあいセンター 真ん中付近、CSR書籍コーナーに配架していますので、自由にご覧ください。
CSRの時流は、慈善活動:ボランティアや寄付、など企業・個人の持ち出しで行う活動がCSR1.0として
基本に有りながらもそれだけでは、持続性にリスクがあるため、企業の事業継続という観点から、事業活動と社会貢献を併せた寄付付き事業:コーズマーケティング(売り上げの1部を寄付する)等に拡がりを見せています。
CSR2.0という呼び方もあります。
若い世代を中心に、購入による社会貢献商品やサービスを認める傾向があります。企業の情報開示と共に、その姿勢・事業活動を購入行動で支援し、良い社会づくりに参加しようとするものです。
「買い物はその企業への投票」ということです。それだけに、企業の理念、事業を情報開示する「CSRレポート」への取組みが重要性を高めると共に、情報発信に時間を割きにくい企業は、表彰制度や公表制度を求めるということだと仙台市のアンケート結果を見ると考えられます。
これまで、CSR・社会貢献は、自社からの持ち出しという考えが支配的でしたが、今は大きく社会が変化しています。 国連加盟国全てが認めた「SDGs」(2030年までに世界で多様な人々が解決すべき17の目標)の取組が今後企業やNPOにおいても、より普及していくと考えられます。それにより、社会貢献の概念が持ち出しオンリーから「共有価値で双方の利益づくり」へと広がっていくと考えられます。
本業である事業活動と17の社会課題SDGsを結び付け、企業の経営の中心において、行こうとするCSR3.0の時代へと向かっています。NPOや地域課題の解決に取り組む団体や自治体とのコラボ(協働)によって、ハッピーハッピーの関係を築こうとするものです。
CSRは、「持ち出しの時代」から、利害関係者と組んで事業を行い、「儲けて社会を良くする(社会貢献)する時代」の普及に向け、NPOと企業のマッチングなどが出来るように、双方に対して、情報収集・発信、啓蒙活動をゆうあいセンターとしても今後注力していこうと考えます。
- 中山間地域の高齢化・人口減少について
- 私は岡山県高梁市の出身です。高梁市は岡山県内有数の高齢化率の中山間地域であり、それ故に多くの問題を抱..