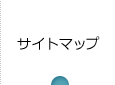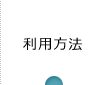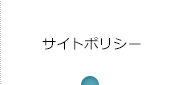タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
プラスチックから考えるSDGs
地域課題・社会課題環境
こんにちは、ゆうあいセンターCSR相談員 小桐です。
今回は、私達の日常生活でなくてはならないプラスチックをテーマにSDGsの事を考えてみたいと思います。少し前の山陽新聞にこんな記事が掲載されていました。
「海のプラごみ減へ新組織 国連 政策や代替品を検討」(以下記事一部抜粋・引用)
海のプラスチックごみとはレジ袋やペットボトルなど、人間活動から出るプラスチック製品が海に流れ出したもので、漁具や漁網も含まれる。世界で年に1千万ント前後が海に流入しているとみられており、海流で運ばれて大量に集まる海域が生まれているほか、海洋生物や海鳥が餌と間違えてのみ込む被害が出ている。世界の海に漂う量は今後も増え続け、2050年までに重量換算で魚の量を超すとの予測もあり、国際的な対策を求める声が高まっています。
このプラスチックは、塊のごみとしてだけでなく、小さく分解されることで微粒子(マイクロプラスチック)となり、直径5ミ リ以下のマイクロプラスチックによる汚染も深刻化.環境中の有害化学物質を吸着するため、誤ってのみ込んだ海鳥や魚などの体内に化学物質が蓄積する危険性が指摘されています。最後は私たち人間の食べ物の中にも戻って来ます。このように細かく分解されたプラスチックを海から回収することはきわめて困難です。
台湾は、2030年までにストロー、コップ、レジ袋などの使い捨てプラスチック製品を全面的に禁止する方針といいます。ケニア、ルワングなどの途上国が既に昨年の秋、ビニール袋の販売どころか、使用まで禁止する法律を施工しています。
欧州連合(EU)欧州委員会が、30年までにEU市場に出回るプラスチックの容器や包装の使い捨てをやめる方針を決定。 この戦略と呼応するように、前後して多くの海外企業が容器の完全リサイクル・プログラムを発表しています。
世界で少なくとも11の有名企業が2025年までにすべてのパッケージを再利用やリサイクル、あるいは堆肥化可能な素材に変更することを表明しているそうです。
その11の企業には、コカ・コーラ、ペプシコ、エビアンなどの飲料メーカー、ユニリーバ、ロレアル、マースなどの消費財メーカー、そしてウォルマートやマークス&スペンサーなどの流通チェーンが含まれています。たとえばコカ・コーラは、2030年までに自社製品のパッケージを100%回収してリサイクルする計画といいます。
もっとも過激なのは、イギリスの食品大手アイスランドフーズかもしれません。同社はなんと今から5年後の2023年までに、全商品でプラスチックのパッケージを廃止することを1月に発表しています。同社は冷凍食品を中心とした食品スーパーです。冷凍食品のパッケージからプラスチックを全廃するというのはかなりすごいことではないでしょうか。
これをSDGsの目標に当てはめてみると 12作る責任・使う責任 13海の豊かさを守ろうに当たります。人体への影響を考えるならば 3すべての人に健康と福祉を にも関係してきます。 上記の名前のある企業は当然この事を指揮していると思われます。
SDGsを経営戦略に組み込む例として考えられます。
また、95%のプラスチック・パッケージは1回使われただけで廃棄されており、これによる経済的損失は年間約9兆~14兆円に上るとの試算もあります。 だからこそ世界は本気でプラスチックを回収したり、使用を削減することに挑戦をはじめたのです。
これは、SDGs9産業と技術革新の基盤をつくろうにも関係してきます。現時点では、不便になるとか、コストがかかるとか、そんなことを言っていられる場合ではないということに気がついたのです。
ちなみに日本はプラスチックのリサイクル率が世界的に見ても非常に高く、83%という驚異的とも言える数値を誇っています。ただし、実はそのうち68%がサーマルリサイクル、つまり焼却処分されています。今後、 日本の進んだ回収システム、再生技術を活用して、今こそ世界に貢献するタイミングなのではないでしょうか
「地球および自然」と「企業の成長と利益」と「人間の幸せ」のトリレンマをいかに解決するか? そして、「四方よし! 」(売り手、買い手、世間、地球)の経営を「グリーンオーシャン」と呼び、これからの経営の方向という考え方があります。
グリーンオーシャンはSDGsの目標とリンクさせることで、多くの人に伝わり易くなります。
このグリーンオーシャン戦略を表彰する制度、「グリーンオーシャン大賞」が2年前から始まりました。主催オルタナ(ビジネスを通じて社会課題の解決を呼び掛ける雑誌)ほか、後援環境省他で52企業が応募し、10企業が表彰されました。
この中には、企業とNPOの共創を促進するプラットフォームを運営する事業もありました。
ゆうあいセンター CSR図書コーナーに配架しています。雑誌オルタナ52号に詳細が掲載されています。是非一度手に取ってご覧ください。新しい社会課題への取り組みのヒントを見つけることが出来ると思います。
今回は、私達の日常生活でなくてはならないプラスチックをテーマにSDGsの事を考えてみたいと思います。少し前の山陽新聞にこんな記事が掲載されていました。
「海のプラごみ減へ新組織 国連 政策や代替品を検討」(以下記事一部抜粋・引用)
海のプラスチックごみとはレジ袋やペットボトルなど、人間活動から出るプラスチック製品が海に流れ出したもので、漁具や漁網も含まれる。世界で年に1千万ント前後が海に流入しているとみられており、海流で運ばれて大量に集まる海域が生まれているほか、海洋生物や海鳥が餌と間違えてのみ込む被害が出ている。世界の海に漂う量は今後も増え続け、2050年までに重量換算で魚の量を超すとの予測もあり、国際的な対策を求める声が高まっています。
このプラスチックは、塊のごみとしてだけでなく、小さく分解されることで微粒子(マイクロプラスチック)となり、直径5ミ リ以下のマイクロプラスチックによる汚染も深刻化.環境中の有害化学物質を吸着するため、誤ってのみ込んだ海鳥や魚などの体内に化学物質が蓄積する危険性が指摘されています。最後は私たち人間の食べ物の中にも戻って来ます。このように細かく分解されたプラスチックを海から回収することはきわめて困難です。
台湾は、2030年までにストロー、コップ、レジ袋などの使い捨てプラスチック製品を全面的に禁止する方針といいます。ケニア、ルワングなどの途上国が既に昨年の秋、ビニール袋の販売どころか、使用まで禁止する法律を施工しています。
欧州連合(EU)欧州委員会が、30年までにEU市場に出回るプラスチックの容器や包装の使い捨てをやめる方針を決定。 この戦略と呼応するように、前後して多くの海外企業が容器の完全リサイクル・プログラムを発表しています。
世界で少なくとも11の有名企業が2025年までにすべてのパッケージを再利用やリサイクル、あるいは堆肥化可能な素材に変更することを表明しているそうです。
その11の企業には、コカ・コーラ、ペプシコ、エビアンなどの飲料メーカー、ユニリーバ、ロレアル、マースなどの消費財メーカー、そしてウォルマートやマークス&スペンサーなどの流通チェーンが含まれています。たとえばコカ・コーラは、2030年までに自社製品のパッケージを100%回収してリサイクルする計画といいます。
もっとも過激なのは、イギリスの食品大手アイスランドフーズかもしれません。同社はなんと今から5年後の2023年までに、全商品でプラスチックのパッケージを廃止することを1月に発表しています。同社は冷凍食品を中心とした食品スーパーです。冷凍食品のパッケージからプラスチックを全廃するというのはかなりすごいことではないでしょうか。
これをSDGsの目標に当てはめてみると 12作る責任・使う責任 13海の豊かさを守ろうに当たります。人体への影響を考えるならば 3すべての人に健康と福祉を にも関係してきます。 上記の名前のある企業は当然この事を指揮していると思われます。
SDGsを経営戦略に組み込む例として考えられます。
また、95%のプラスチック・パッケージは1回使われただけで廃棄されており、これによる経済的損失は年間約9兆~14兆円に上るとの試算もあります。 だからこそ世界は本気でプラスチックを回収したり、使用を削減することに挑戦をはじめたのです。
これは、SDGs9産業と技術革新の基盤をつくろうにも関係してきます。現時点では、不便になるとか、コストがかかるとか、そんなことを言っていられる場合ではないということに気がついたのです。
ちなみに日本はプラスチックのリサイクル率が世界的に見ても非常に高く、83%という驚異的とも言える数値を誇っています。ただし、実はそのうち68%がサーマルリサイクル、つまり焼却処分されています。今後、 日本の進んだ回収システム、再生技術を活用して、今こそ世界に貢献するタイミングなのではないでしょうか
「地球および自然」と「企業の成長と利益」と「人間の幸せ」のトリレンマをいかに解決するか? そして、「四方よし! 」(売り手、買い手、世間、地球)の経営を「グリーンオーシャン」と呼び、これからの経営の方向という考え方があります。
グリーンオーシャンはSDGsの目標とリンクさせることで、多くの人に伝わり易くなります。
このグリーンオーシャン戦略を表彰する制度、「グリーンオーシャン大賞」が2年前から始まりました。主催オルタナ(ビジネスを通じて社会課題の解決を呼び掛ける雑誌)ほか、後援環境省他で52企業が応募し、10企業が表彰されました。
この中には、企業とNPOの共創を促進するプラットフォームを運営する事業もありました。
ゆうあいセンター CSR図書コーナーに配架しています。雑誌オルタナ52号に詳細が掲載されています。是非一度手に取ってご覧ください。新しい社会課題への取り組みのヒントを見つけることが出来ると思います。
- 中山間地域の高齢化・人口減少について
- 私は岡山県高梁市の出身です。高梁市は岡山県内有数の高齢化率の中山間地域であり、それ故に多くの問題を抱..