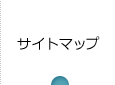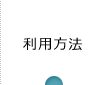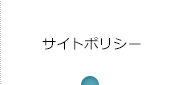タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
自分の組織の成果を振り返る
地域課題・社会課題その他
こんにちは、ゆうあいセンター CSR担当 小桐です。
今回はいつともと視点を変えて、NPOの事業の評価について考えたいと思います。
企業は、自組織の事業年度が終了すると株主総会を開催し、事業報告、成果の配分、翌年度以降の事業について報告し、株主に意見を求めます。NPOも同じように、事業報告、財産の増減の状況、翌年度以降の事業について報告し、正会員(法律上社員)に承認と意見を求めます。
NPOが新たに会員を増やしたり、支援をする企業や団体を増やすのに、事業の成果がどうであったのかを明らかにすると、客観的にそのNPOの事業やNPO自身の信頼性が高まり、新たな協力者を得やすい状況が生まれます。
これまで、ソーシャルグッド岡山への投稿で、CSR実践のために、企業がNPOと共有できる社会課題を見つけ、支援し、取り組む事で社会課題の解決による新しいビジネスチャンスが生まれるということを説明してきました。
企業がNPOと協働の取り組みをする為には、そのNPOの志以外に活動及びその成果がはっきりとわかるものでなければ、なかなか協働の取り組み(マッチング)は難しいと思われます。
企業は企業間の競争が激しくなると、必然的に、利潤を求めて競争が少ない市場開拓や、商品・サービスの事業展開を考えます。これを経済用語でブルーオーシャンと呼んでいます。そしてさらに、その新事業や商品・サービスが社会課題の解決に貢献できるものであれば、便益を享受する直接の人たち以外にも支持者は広がっていくでしょう。これが新しいビジネスの流れでグリーンオーシャンと呼ばれているもので、本業をとおしてのCSRの実践につながります。
新しい社会の価値を創ることにより、そこには競争よりも協働という考え方が支配的となります。安定した需要がそこに見込まれます。企業単独では、できない動きや考え方がNPOとの協働で実現可能となります。
その時に問題となるのは、パートナーとなるNPOがこれまで、どれだけの成果をあげてきたかです。
単なる数字の評価だけでなく、社会的な価値がどのように、どの程度実現できたかを評価することで、協働の相手である企業にとっては、パートナーとなるNPOを理解しやすくなります。
「事業や活動がどの程度成果をあげることができたのかを価値判断する」ことを社会的インパクト評価と言います。 「事業や活動の結果として生じた成果・結果」はどうであったのかを客観的に見られるようする評価のやり方です。
人、モノ、カネの投入(インプット)により 「アウトプット」(出力結果である製品やサービスなど)が生まれます。そして、アウトプットによって生まれた成果、変化、便益を 「アウトカム」と呼びます。
このアウトプットを一定の評価基準に従って評価するのが、社会的インパクト評価です。
そのメリットは、説明責任を果たすことができる。次なる改善のきっかけとなる、評価を実施することによる信頼性の向上です。
世界的には、G8社会的インパクト投資タスクフォースや様々なイニシアチブの設立が、また、日本でも社会的インパクト評価イニシアチブの設立や内閣府が2016年に発表した『骨太の方針』での言及など広がりを見せています。
そして、2016年6月14日に開催したSocial Impact Day2016にて、「社会的インパクト評価イニシアチブの発足」、「WEBサイト」、「社会的インパクト評価に関する実践マニュアル及び分野別(教育分野、就労支援分野、地域まちづくり分野)の評価ツールセット」が公開されました。
<Facebookページ>
https://www.facebook.com/社会的インパクト評価イニシアチブ-870556429722838/
<WEBサイト>
http://impactmeasurement.jp
<実践マニュアル及び分野別の評価ツールセット>
http://impactmeasurement.jp/about/guidance.html
この評価ツールセットはあくまで、ベースであり、NPOとしては、自組織の達成したい目標を元に、社会的インパクトを個々に定義し指標を設定する必要があります。その上で、定量、定性、貨幣化などの方法で評価します。指標が時間とともにどのくらい変化したかをモニタリングするだけでも、ある程度の評価ができます。
今後、NPOにおける社会的インパクト評価を実施し、公開する事で、企業との協働がしやすくなるでしょう。また、企業自身も社会的インパクト評価をすることで、自社の事業活動が、どれだけ社会に影響を与えているかを知る事も可能となります。
今後ゆうあいセンターでもNPOの社会的インパクト評価の実施について、研究をしていく予定です。準備ができた段階で勉強会の開催も考えます。興味のある方は一度上記サイトをご確認ください。
今回はいつともと視点を変えて、NPOの事業の評価について考えたいと思います。
企業は、自組織の事業年度が終了すると株主総会を開催し、事業報告、成果の配分、翌年度以降の事業について報告し、株主に意見を求めます。NPOも同じように、事業報告、財産の増減の状況、翌年度以降の事業について報告し、正会員(法律上社員)に承認と意見を求めます。
NPOが新たに会員を増やしたり、支援をする企業や団体を増やすのに、事業の成果がどうであったのかを明らかにすると、客観的にそのNPOの事業やNPO自身の信頼性が高まり、新たな協力者を得やすい状況が生まれます。
これまで、ソーシャルグッド岡山への投稿で、CSR実践のために、企業がNPOと共有できる社会課題を見つけ、支援し、取り組む事で社会課題の解決による新しいビジネスチャンスが生まれるということを説明してきました。
企業がNPOと協働の取り組みをする為には、そのNPOの志以外に活動及びその成果がはっきりとわかるものでなければ、なかなか協働の取り組み(マッチング)は難しいと思われます。
企業は企業間の競争が激しくなると、必然的に、利潤を求めて競争が少ない市場開拓や、商品・サービスの事業展開を考えます。これを経済用語でブルーオーシャンと呼んでいます。そしてさらに、その新事業や商品・サービスが社会課題の解決に貢献できるものであれば、便益を享受する直接の人たち以外にも支持者は広がっていくでしょう。これが新しいビジネスの流れでグリーンオーシャンと呼ばれているもので、本業をとおしてのCSRの実践につながります。
新しい社会の価値を創ることにより、そこには競争よりも協働という考え方が支配的となります。安定した需要がそこに見込まれます。企業単独では、できない動きや考え方がNPOとの協働で実現可能となります。
その時に問題となるのは、パートナーとなるNPOがこれまで、どれだけの成果をあげてきたかです。
単なる数字の評価だけでなく、社会的な価値がどのように、どの程度実現できたかを評価することで、協働の相手である企業にとっては、パートナーとなるNPOを理解しやすくなります。
「事業や活動がどの程度成果をあげることができたのかを価値判断する」ことを社会的インパクト評価と言います。 「事業や活動の結果として生じた成果・結果」はどうであったのかを客観的に見られるようする評価のやり方です。
人、モノ、カネの投入(インプット)により 「アウトプット」(出力結果である製品やサービスなど)が生まれます。そして、アウトプットによって生まれた成果、変化、便益を 「アウトカム」と呼びます。
このアウトプットを一定の評価基準に従って評価するのが、社会的インパクト評価です。
そのメリットは、説明責任を果たすことができる。次なる改善のきっかけとなる、評価を実施することによる信頼性の向上です。
世界的には、G8社会的インパクト投資タスクフォースや様々なイニシアチブの設立が、また、日本でも社会的インパクト評価イニシアチブの設立や内閣府が2016年に発表した『骨太の方針』での言及など広がりを見せています。
そして、2016年6月14日に開催したSocial Impact Day2016にて、「社会的インパクト評価イニシアチブの発足」、「WEBサイト」、「社会的インパクト評価に関する実践マニュアル及び分野別(教育分野、就労支援分野、地域まちづくり分野)の評価ツールセット」が公開されました。
<Facebookページ>
https://www.facebook.com/社会的インパクト評価イニシアチブ-870556429722838/
<WEBサイト>
http://impactmeasurement.jp
<実践マニュアル及び分野別の評価ツールセット>
http://impactmeasurement.jp/about/guidance.html
この評価ツールセットはあくまで、ベースであり、NPOとしては、自組織の達成したい目標を元に、社会的インパクトを個々に定義し指標を設定する必要があります。その上で、定量、定性、貨幣化などの方法で評価します。指標が時間とともにどのくらい変化したかをモニタリングするだけでも、ある程度の評価ができます。
今後、NPOにおける社会的インパクト評価を実施し、公開する事で、企業との協働がしやすくなるでしょう。また、企業自身も社会的インパクト評価をすることで、自社の事業活動が、どれだけ社会に影響を与えているかを知る事も可能となります。
今後ゆうあいセンターでもNPOの社会的インパクト評価の実施について、研究をしていく予定です。準備ができた段階で勉強会の開催も考えます。興味のある方は一度上記サイトをご確認ください。
- 中山間地域の高齢化・人口減少について
- 私は岡山県高梁市の出身です。高梁市は岡山県内有数の高齢化率の中山間地域であり、それ故に多くの問題を抱..