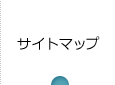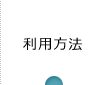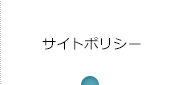タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
企業の社会的責任 環境と健康について3~消費の在り方から考える~
地域課題・社会課題環境
こんにちは、ゆうあいセンターCSR相談員 小桐です。
今週は、環境と健康について第3回目の情報提供です。
今回は、肉食について考えてみたいと思います。
若い人を中心に日常的に食べられているファーストフードのひとつハンバーガー。日本最大のチェーン店である日本マクドナルド社のホームページで原料調達についての情報をみると以下のような内容でした。
バンズと呼ばれるパンの原料小麦は、アメリカ、カナダ、オーストラリア産 ビーフパテの原料牛肉は、オーストラリ、ニュージーランド。 タマネギはアメリカ、ピクルスに使う きゅうりは、トルコ、スリランカ、インドでした。今更ながらですが外国産100%でした。 以前に輸入野菜や果物には輸送期間中に腐敗防止のために防腐剤や殺虫剤などの薬品がポストハーベストとしてかけられていることは説明した通りですので、環境面と健康面から考えるとあまりお勧めは出来ません。
牛肉に関する環境への悪影響はあまり知られていないのですが、温室効果ガスガスの一つメタンガスの大量発生に繋がるという事実があります。メタンガスはCO2と比べて温室効果は、10倍と言われています。 メタンガスの発生は牛のゲップがその元です。1頭で1日あたり300~500リットルのガスが胃袋で発生します。世界では、牛や羊、やぎなど31億頭が居るので、メタンガスの総排出量は1日1兆5,500億リットルが地球上で排出されていて、実に地球上の温室効果ガスの5%にあたると言われています。肉食をするために牛や羊の放牧をすることが、地球環境悪化に繋がっているのです。
さらに、ふん尿が発する亜(あ)酸化ちっそ素は、CO2素の300倍もの温室効果があり、紫外線により分解、一酸化窒素を生みだすため、オゾン層破壊の原因にもなっています。
牛肉1kgを得るために、穀物が10kg必要と言われており、牛肉食は環境面からもお勧めできない食材と言えます。
南米の貧困地域では、飼料用穀物が多く生産されているが、この穀物は農場の近辺に住む人々の手には入らず、遠い日本やヨーロッパの動物の餌になる。日本は多くの飼料用穀物をアメリカから輸入していますが、一部南米などからも輸入している。
日本が26万トンのとうもろこしを輸入しているアルゼンチンでは1000万人が飢餓にあえいでいるという報告があります。アフリカのサハラ砂漠以南では4人に1人以上が十分な食料を得られない状況も有り、牛が食べる穀物がアフリカや食料の不足する国に届けば食糧問題が解決されるのではないかと考えるのはわたしだけでしょうか?
じゃあどんな肉を食べれば良いのかとの疑問が湧いてきます。現在国内では、イノシシやシカによる獣害が増えています。岡山県内でもイノシシの被害は深刻です。
調査によると、イノシシは全県で生息し、奈義町~美作市北部、西粟倉村や和気町~備前市北部など一部で減少している地域もあるが全県的には、生息数は増えています。シカは、
オスは県全で見られ、メスは県東部に主に分布していて、県東部県北部の一部で被害が甚大化しているとのことです。
美作市では、市営の解体施設も稼働しており、年間にシカ1100頭あまり、イノシシ230頭(平成25年度)を解体し、ジビエ料理として提供されています。シカ肉は脂肪が少なくヘルシー、イノシシ肉も死後2時間以内に解体されれば匂いがなく美味しく食べられるとのことです。
吉備中央町でもイノシシ肉が特産物として販売されていて、今後県内に生息する有害獣の肉を如何にしておいしく食べるかが環境問題、獣害問題を解決する有効な手段になりそうです。
既に県内では、県内の食肉処理施設で安全に処理されたイノシシ・シカ肉を「おかやまジビエ」と名づけ、料理店での提供や家庭で気軽にジビエ料理を楽しめるよう普及・定着を進めていて、ジビエスタンプラリー(28年11月20日から29年2月28日まで実施)が実施されました。ジビエのレトルトカレーパックなども販売されています。地産地消の肉食が盛んになることが期待されます。
今週は、環境と健康について第3回目の情報提供です。
今回は、肉食について考えてみたいと思います。
若い人を中心に日常的に食べられているファーストフードのひとつハンバーガー。日本最大のチェーン店である日本マクドナルド社のホームページで原料調達についての情報をみると以下のような内容でした。
バンズと呼ばれるパンの原料小麦は、アメリカ、カナダ、オーストラリア産 ビーフパテの原料牛肉は、オーストラリ、ニュージーランド。 タマネギはアメリカ、ピクルスに使う きゅうりは、トルコ、スリランカ、インドでした。今更ながらですが外国産100%でした。 以前に輸入野菜や果物には輸送期間中に腐敗防止のために防腐剤や殺虫剤などの薬品がポストハーベストとしてかけられていることは説明した通りですので、環境面と健康面から考えるとあまりお勧めは出来ません。
牛肉に関する環境への悪影響はあまり知られていないのですが、温室効果ガスガスの一つメタンガスの大量発生に繋がるという事実があります。メタンガスはCO2と比べて温室効果は、10倍と言われています。 メタンガスの発生は牛のゲップがその元です。1頭で1日あたり300~500リットルのガスが胃袋で発生します。世界では、牛や羊、やぎなど31億頭が居るので、メタンガスの総排出量は1日1兆5,500億リットルが地球上で排出されていて、実に地球上の温室効果ガスの5%にあたると言われています。肉食をするために牛や羊の放牧をすることが、地球環境悪化に繋がっているのです。
さらに、ふん尿が発する亜(あ)酸化ちっそ素は、CO2素の300倍もの温室効果があり、紫外線により分解、一酸化窒素を生みだすため、オゾン層破壊の原因にもなっています。
牛肉1kgを得るために、穀物が10kg必要と言われており、牛肉食は環境面からもお勧めできない食材と言えます。
南米の貧困地域では、飼料用穀物が多く生産されているが、この穀物は農場の近辺に住む人々の手には入らず、遠い日本やヨーロッパの動物の餌になる。日本は多くの飼料用穀物をアメリカから輸入していますが、一部南米などからも輸入している。
日本が26万トンのとうもろこしを輸入しているアルゼンチンでは1000万人が飢餓にあえいでいるという報告があります。アフリカのサハラ砂漠以南では4人に1人以上が十分な食料を得られない状況も有り、牛が食べる穀物がアフリカや食料の不足する国に届けば食糧問題が解決されるのではないかと考えるのはわたしだけでしょうか?
じゃあどんな肉を食べれば良いのかとの疑問が湧いてきます。現在国内では、イノシシやシカによる獣害が増えています。岡山県内でもイノシシの被害は深刻です。
調査によると、イノシシは全県で生息し、奈義町~美作市北部、西粟倉村や和気町~備前市北部など一部で減少している地域もあるが全県的には、生息数は増えています。シカは、
オスは県全で見られ、メスは県東部に主に分布していて、県東部県北部の一部で被害が甚大化しているとのことです。
美作市では、市営の解体施設も稼働しており、年間にシカ1100頭あまり、イノシシ230頭(平成25年度)を解体し、ジビエ料理として提供されています。シカ肉は脂肪が少なくヘルシー、イノシシ肉も死後2時間以内に解体されれば匂いがなく美味しく食べられるとのことです。
吉備中央町でもイノシシ肉が特産物として販売されていて、今後県内に生息する有害獣の肉を如何にしておいしく食べるかが環境問題、獣害問題を解決する有効な手段になりそうです。
既に県内では、県内の食肉処理施設で安全に処理されたイノシシ・シカ肉を「おかやまジビエ」と名づけ、料理店での提供や家庭で気軽にジビエ料理を楽しめるよう普及・定着を進めていて、ジビエスタンプラリー(28年11月20日から29年2月28日まで実施)が実施されました。ジビエのレトルトカレーパックなども販売されています。地産地消の肉食が盛んになることが期待されます。
- 中山間地域の高齢化・人口減少について
- 私は岡山県高梁市の出身です。高梁市は岡山県内有数の高齢化率の中山間地域であり、それ故に多くの問題を抱..