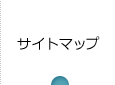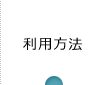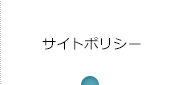タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
- 自分の“職能”を活かした新しいNPO支援。 「プロボノによるNPO等の情報発信・運営支援事業」
- なぜ今、NPOに情報開示が求められるのか。 「信頼できるNPO等を紹介するウェブサイトを活用した情報開示促進事業」
- 正しい理解が、NPOの力に。①「NPO新会計基準導入促進事業」
- 正しい理解が、NPOの力に。②「認定NPO法人取得促進事業」
- 気軽にはじめる社会貢献のすゝめ ~ガチャガチャリティと募金箱
- 割り勘で夢をかなえよう!第3期の募集がスタートしました。
- 施設送迎運転者講習会のレポート
- サマ★ボラキャンペーン!始めました!(ゆうあいセンター)
- 人と人をつなぐ「市(マルシェ)」 『備前福岡の市』編
- インターンシップ
CSRとISO26000
活動・取り組みその他
Noboru Ogiri
こんにちは、ゆうあいセンター CSR担当 小桐です。
今週は、先週もご紹介した 「全ての組織に共通な社会的な責任についての国際規格ISO26000」について先週より少し突っ込んで、説明させて頂きます。
国際規格ISOというと品質に関する9000シリーズや環境に関する14000シリーズなどが浮かぶのではないでしょうか?どれも規格に適合する認証システムがあり、認証及び継続にはそれなりの覚悟つまり、一定量のヒト、モノ、カネの投入が必要です。
それだけに、ある程度の規模の企業でなくては、取り組むメリットが少ないので、認証取得後も、3年の継続に負担が大きいと考える企業では、更新をしないケースも見られます。
「ISO26000組織の社会的責任に関する国際規格」は、他の国際規格と大きく違う点があります。
それは、「手引書(ガイダンス)」であって、要求事項(〇〇しなければならない)を示した認証のための規格ではないということです。
「〇〇しなければならない」 ではなく、「組織が自主的に取り組むための手引き」としてしか活用できないということです。それだけに、それぞれの組織の特徴を生かして、「身の丈にあった」取り組みが出来るというメリットがあります。もちろん、利用可能な経営資源の範囲でやっていけば良いということです。一度にすべての規格に取り組まなければならないというものではありません。
この規格では、7つの中核課題にそれぞれにガイドラインを設定しています。
①組織統治 ②人権 ③労働慣行 ④公正な事業慣行 ⑤消費者課題 ⑥環境 ⑦コミュニティへの参画およびコミュニティへの発展
このガイドラインは、ISO 国際標準化機構が5年の歳月をかけ、世界の政府関係者、産業界、労働界、消費者、NGO,その他有識者が集まって多様な視点で検討した国際規格であり、それは、企業と言う組織形態の為だけではなく、様々な組織に適用が可能な規格です。
根底には、持続可能な発展への組織の貢献を最大にするという思想が流れています。現世界に起きている様々な矛盾や問題を放置していては、持続可能ではないと、持続可能な世界をつくる為に作成された国際的な標準です。
それだけに、各組織では、自組織をさらに発展させるツールとして取り組まれると、良いです。
国際的な視点に立っているので、ガイドラインに従った行動であれば、組織の行動に誤りがありません。今は未だ、この規格を知っている人々は多くは有りませんが、今後SDG‘Sの目標とも連携して、理解者が広まると、取り組み具合が直接組織の評価に繋がってきます。
今だけ、ここだけ、自分だけ、自分のグループだけでは、誰も安定して生きていける時代ではありません。
一度ISO26000について、どんなものかを確認されると良いと思います。下記サイトをご覧ください。
ゆうあいセンターでは、ISO26000を自組織にどのように適用していけばよいかについてもご相談いただけるように準備をしています。遠慮なくご相談にいらしてください。
今週は、先週もご紹介した 「全ての組織に共通な社会的な責任についての国際規格ISO26000」について先週より少し突っ込んで、説明させて頂きます。
国際規格ISOというと品質に関する9000シリーズや環境に関する14000シリーズなどが浮かぶのではないでしょうか?どれも規格に適合する認証システムがあり、認証及び継続にはそれなりの覚悟つまり、一定量のヒト、モノ、カネの投入が必要です。
それだけに、ある程度の規模の企業でなくては、取り組むメリットが少ないので、認証取得後も、3年の継続に負担が大きいと考える企業では、更新をしないケースも見られます。
「ISO26000組織の社会的責任に関する国際規格」は、他の国際規格と大きく違う点があります。
それは、「手引書(ガイダンス)」であって、要求事項(〇〇しなければならない)を示した認証のための規格ではないということです。
「〇〇しなければならない」 ではなく、「組織が自主的に取り組むための手引き」としてしか活用できないということです。それだけに、それぞれの組織の特徴を生かして、「身の丈にあった」取り組みが出来るというメリットがあります。もちろん、利用可能な経営資源の範囲でやっていけば良いということです。一度にすべての規格に取り組まなければならないというものではありません。
この規格では、7つの中核課題にそれぞれにガイドラインを設定しています。
①組織統治 ②人権 ③労働慣行 ④公正な事業慣行 ⑤消費者課題 ⑥環境 ⑦コミュニティへの参画およびコミュニティへの発展
このガイドラインは、ISO 国際標準化機構が5年の歳月をかけ、世界の政府関係者、産業界、労働界、消費者、NGO,その他有識者が集まって多様な視点で検討した国際規格であり、それは、企業と言う組織形態の為だけではなく、様々な組織に適用が可能な規格です。
根底には、持続可能な発展への組織の貢献を最大にするという思想が流れています。現世界に起きている様々な矛盾や問題を放置していては、持続可能ではないと、持続可能な世界をつくる為に作成された国際的な標準です。
それだけに、各組織では、自組織をさらに発展させるツールとして取り組まれると、良いです。
国際的な視点に立っているので、ガイドラインに従った行動であれば、組織の行動に誤りがありません。今は未だ、この規格を知っている人々は多くは有りませんが、今後SDG‘Sの目標とも連携して、理解者が広まると、取り組み具合が直接組織の評価に繋がってきます。
今だけ、ここだけ、自分だけ、自分のグループだけでは、誰も安定して生きていける時代ではありません。
一度ISO26000について、どんなものかを確認されると良いと思います。下記サイトをご覧ください。
ゆうあいセンターでは、ISO26000を自組織にどのように適用していけばよいかについてもご相談いただけるように準備をしています。遠慮なくご相談にいらしてください。

- 自分の“職能”を活かした新しいNPO支援。 「プロボノによるNPO等の情報発信・運営支援事業」
- プロボノとは、今までの “労働力を提供するボランティア” とは異なり、様々な分野のプロが自分たちの専..