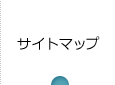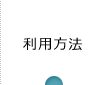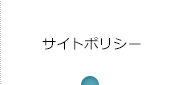タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
持続可能な社会を考える 「栄養たっぷりサステナブルな食材」
地域課題・社会課題その他
今日は、こんにちは、ゆうあいセンターSDGs&CSR相談員 小桐です。
先日の土用の丑の日は、スーパーマーケットやコンビニ、回転寿司など 夏の暑い時期に精をつける食べ物 「うなぎ」がやたらと店頭に並んでいました。 食べられた方も多いと思います。今回は持続可能な「食材」について考えて見たいと思います。
岡山県では、このうなぎ 20cm以下のシラスウナギ(幼魚)は禁漁となっているのですが、密漁が多いと新聞に記事が掲載されていました。
実はニホンウナギは、2014年に「近い将来、野生での絶滅の危険性が高い」とされる「絶滅危惧1B種」として国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストに掲載されています。
絶滅危惧1B種は、複数ある絶滅危惧種のランクの中でも、ラッコやトキ、ジャイアントパンダなどと同じ2番目に危機度の高いランクです。しかも 卵から孵化させることが出来ない魚だそうです。
ニホンウナギはマリアナ海溝付近で産卵し、孵化します。その後北上してくる稚魚を捕獲して養殖する方法しかないそうです。現在は、稚魚の漁獲高もきめられているので漁獲高が増えることはまず無いようです。 冒頭ウナギの話題でしたが、次は、サステナブルを考える食材に関する新たな情報を提供させていただきます。
8月2日山陽新聞に「香ばしく干しエビのよう」 吉備中央町で食用コオロギ養殖 という記事がありました。 少し前に地元テレビのニュースで見たような気もして、関連記事を調べてみました。
同記事では、 倉庫の2階を転用した養殖場 プラスチック製のコンテナ 100個が3段に並べられている。ヨーロッパイエコオロギ 体長2cmほどエンマコオロギよりやや小さい。
記者の食レポでは、干したサクラエビのようでパリッとした食感、香ばしい風味が。広がったとあります。
1袋 11匹入り216円で近くの道の駅で販売しているほか、地ビールや菓子、おつまみを共同開発した。
養殖は、25~30℃を保ち通年行う。とあり、「陸えびJAPAN」(OKAEBI) という会社が養殖をしています。
コオロギは食べられるんだ 知らなかったからスタートです。昆虫食の盛んな国としてはアジアではタイが有名。 スーパーマーケットでは、冷凍のタガメやカイコガのサナギ、ヨーロッパイエコウロギ、バッタ、タケットガの幼虫などが売られている光景を目にする。 屋台ではこれら虫の佃煮が軒を飾っている。 さらに食用昆虫の養殖が広がっている。とネットの記事を見つけました。
日本では、長野県 伊那市には川魚や山菜とともに、ハチの子、ざざ虫、蚕のさなぎ、イナゴという4種類の昆虫の佃煮を作り続ける「塚原信州珍味(店舗名:つかはら)」。があります。 この地域の人たちは、イナゴは家庭の味・弁当のおかずで、日常生活に浸透した、昔ながらの家庭料理という事が分かりました。
なぜ、昆虫なのでしょうか?
きっかけは2013年に国際連合食糧農業機関(FAO)が発表した報告書がきっかけです。
FAOによると、2050年には世界人口が90億人を超え、食糧危機が深刻化するとしており、昆虫は、タンパク質などの栄養素を豊富に含むこと、養殖に必要とされる土地や飼料が家畜などに比べ大幅に少なく環境負荷が小さいことから、「飼育変換率」と「環境負荷」に優れた効果があると報告されたことで、『食品としての昆虫の活用が動物性たんぱく質の配給源として世界的に注目を集めた』のです。
FAOの発表を受け、健康意識・環境意識が高い欧米の消費者を中心に昆虫食への関心が高まり、2010年代半ばから昆虫食の市場に新規参入するベンチャー企業が増加しているとのこと。これらの企業は、コオロギやミールワーム(甲虫)などの昆虫の粉末を原材料に使った、昆虫の原型をとどめない加工食品を発売。伝統食とは異なる新しい昆虫食の市場を形成し始めているそうです。
製品の主な事例としては、プロテインバー、チップスなどのスナック菓子、パン、ハンバーグなどがあり、消費者にとって抵抗感の少ない形態で商品展開されています。
2018年には、欧州連合(EU)が昆虫を食品として認可し自由な取引を承認したことから、今後市場が大きく拡大することが期待されるとあります。
昆虫を原材料とする食品は通常の食品に比べ価格が高いことが市場拡大の阻害要因となっていたが、食用昆虫の養殖に力を入れる企業が増加。今後、原材料としての昆虫の供給量が増えることで、製品価格の低下が進むと予想され、それに伴い、昆虫食の開発や普及が更に進み、市場は拡大していくと見込まれるとのことです。
この昆虫食の流れが、日本でもそして、地元岡山でも少しずつ見られ始めています。2020年のネットの投稿では、全国で53か所に昆虫食自動販売機 が設置されているとあります。
コオロギ、タガメ、タランチュラ、イモムシ、サソリ、カブトムシ――昆虫食を売る自販機には、これら食用昆虫を詰めた容器が整然と並ぶ。
「バッタやコオロギは、素揚げし、塩を振ってパッケージに詰める。この手順はポテトチップスと同じ。
香りは居酒屋で食べる川エビの唐揚げに近い。昆虫もエビも硬い殻を高温で揚げるのでどちらも香ばしい。とはいえ、味は虫の種類によって異なる」とコインロッカーや自販機、ATMなどの設置・管理を手掛けるティ・アイ・エス(東京・台東)の営業担当者。2020年に入ってから、同社は都内3カ所に昆虫食の自販機を新しく設置し、運営を始めたとあります。
では、岡山では、どうなのでしょうか?
昆虫食の自販機が2022年6月時点で2か所設置されています。1件は鷲羽山ハイランドに、もう1件は
岡山市北区妹尾のジーンズファクトリー駐車場裏に設置されています。
商品ラインナップはすと、コオロギ、バッタ、サソリ、タガメ、ゲンゴロウ、セミやワームなどなどとネットで紹介されています。値段は、流通量が少ないので、高め コオロギのお試し価格は800円
https://www.youtube.com/watch?v=zvhVr3XEuM8
昆虫は嫌いという方は多いと思います。ましてはそれを食べるなんて、とても考えられない。
そんな方のためにか 無印良品では、これからの地球のことを考えて、コオロギのパウダー入りのせんべいを作りました。エビのような香ばしい風味が特長です。『コオロギせんべい』 55g 消費税込みで190円。コオロギチョコも販売しています。お菓子だけでなく、コオロギを練りこんだうどんを発売している企業もあります。
「bugoom(バグーム)」は、コオロギが練り込まれた業界初の「カップうどん」を発売しました。
(https://bugoom.jp/?AC=b9)
製法にこだわったコオロギ麺を使用。吟味した小麦粉とコオロギパウダーを本来の味を損なわないように、清水で練り上げ熟成させることで上質なコオロギ麺に仕上げました。
こだわり製法のコオロギ麺には、1食分につき約100匹分のコオロギパウダーを練り込まれています。
「昆虫食には抵抗がある」という方でも美味しく味わっていただけるように、姿が残った虫を一切入れておりません。これまで昆虫食に抱いていた先入観にとらわれることなく、素材本来の味わいをご堪能いただけます。」あります。
かつお・さば・しいたけ・昆布など旨味たっぷりの素材を使ったお出汁が、コオロギ麺の味わいをぐっと引き立ててくれるそんな一品。お湯を注いでレンジで調理、簡単に調理できる業界初のカップうどんです。
商品名:「コオロギうどん」 内容量:120g(めん90g) 小売希望価格:810円(税込)
商品URL:https://bugoom.jp/cricket/item_5727.php?child=5729&AC=b9
とあります。流通量が少ないだけに価格は高いと感じます。たべるとおいしいのではないかとの期待もあります。
では、なぜ昆虫食 なかでもコオロギなのでしょうか?
先述の無印良品のHPには、以下の事が書かれてあります。コオロギが地球を救う
https://www.muji.com/jp/ja/feature/food/460936
やがて来るだろう世界の食糧危機への対策として、昆虫食が注目を集めています。
栄養価が高く環境への負荷も少ないことから、国連食糧農業機関(FAO)も推奨。
まだ抵抗感をもつ人も多い食材ですが、無印良品は徳島大学と連携してコオロギ粉末入りのチョコとせんべいを開発しました。地球にやさしい未来食です。
☆人口増加と食糧の確保
2050年には世界人口が100億人になることが予想されています。そのため、重要な栄養素であるたんぱく質を確保することが重要な課題とされています。そこで、家畜の代替えとしての昆虫食が注目され始めています。
☆昆虫食と栄養素
昆虫は主な動物性たんぱく資源の家畜と同じく、主要な栄養素を多く体内に含むため、栄養素を効率よく摂取することができます。
以下は、私達が食べる食肉との比較データです。
① 100gあたりのたんぱく質量
コオロギ:60.0g 鶏:23.3g 豚:22.1g 牛:21.2g
(※コオロギ:パウダー、鶏:むね肉、豚:もも肉、牛:もも肉にて算出、※コオロギの数値:日本食品分析センターにて分析 / 牛・豚・鶏の数値:文部科学省 食品成分データベースより算出)
☆環境への負荷
昆虫を生育する際の温室効果ガス排出量や必要な水やエサの量は、一般的な家畜と比べて圧倒的に少なく、環境負荷も軽減されると言われています。
② えさの必要量 コオロギ:1.7kg 鶏:2.5kg 豚:5kg :牛10kg
③ 水の必要量 コオロギ:4L 鶏:2300L 豚:3500L 牛:22000L
④ 温室効果ガス排出量 コオロギ:0.1kg 鶏:0.3kg 豚:1.1kg :牛2.8kg
(※たんぱく質1kgを生産する際の数値です ※出典元:2013年 FAO報告書) 牛や羊は、ゲップをします。そのメタンガスは1年間に排出される温室効果ガスの5%を占めており、CO2の10倍以上の温室効果があると言われています。この数字を見ると一目瞭然です。
また、食べた人の感想も掲載されています。
https://www.muji.com/jp/ja/feature/food/460936
「陸えびJAPAN」のHPには、コオロギの栄養についてこんなことも書いてありました。
タンパク質やオメガ3・必須アミノ酸BCAAを豊富にバランスよく含み、ビタミン・ミネラル・亜鉛、鉄分、カルシウム、マグネシウム腸内環境の改善とデトックスに効果があると言われるキチン質という食物繊維も含まれ、体に必要な栄養素がバランスよく含有されています。可食部分はほぼ100%。
省スペースでの飼育が可能で、成長が早い為、出荷までのサイクルが40日前後と生産効率が良く、雑食性でもある為、「フードロス」の食品残渣も利用して生産が可能です。
同社は、生産へのこだわり として 「生産者の人間性」 生産者の想いは昆虫や商品にまで影響すると考えております。命を扱う職業である事を自覚し、重んじ、昆虫への敬意は忘れません。生産における日々のストレス軽減・衛生管理など最善の配慮・改善を続けています。安定した、栄養豊富で美味しい昆虫食をお届けいたします。 アニマルウェルフェアならぬ、インセクトウェルフェアにも配慮していることが分かりました。
また、「環境配慮」として、魚粉を利用せずに、米ぬかを主原料とした配合飼料を食べて育っています。
ここまで、読んでくると、環境や将来世代の事を考えると昆虫食にもチャレンジしないといけないかなぁという気持ちにはなります。でもなんとなくまだ、自信がないという方には、ビールをお薦めします。
『コオロギをグツグツ煮込んだエキスを原料にした地ビールを、岡山市内の醸造所がつくった。湯気は生臭かったものの、熟成を経ると、マイルドでこくのある飲み口に。』330ミリリットル入りで800円と高めの価格設定だが、意外と人気で、新たなラインアップも準備しているという。
コオロギビールをつくったのは吉備土手下麦酒醸造所(岡山市北区)。これまでも季節の果実やショウガ、カモミールを使ったビールなど、独自の商品展開を進めてきた。新たに目を付けたのは虫だった。
「昆虫食」は地球温暖化に伴う食糧危機の解決策の一つとされる。昆虫は牛や豚などの家畜より圧倒的に少ないエサや水、エネルギーで効率的に育てることができ、たんぱく質の含有量も肉と比べて遜色はないという。 同醸造所は2月、吉備中央町産の米ぬかで育てられた生の食用コオロギ2キロを煮込んで「だし」を取り、麦汁にブレンド。200リットルのビールを造った。
今年に入り 「陸えびJAPAN」にはコオロギ養殖の取材が新聞やTVなどで7件あったといいます。今後コオロギに関する話題に注目です。
先日の土用の丑の日は、スーパーマーケットやコンビニ、回転寿司など 夏の暑い時期に精をつける食べ物 「うなぎ」がやたらと店頭に並んでいました。 食べられた方も多いと思います。今回は持続可能な「食材」について考えて見たいと思います。
岡山県では、このうなぎ 20cm以下のシラスウナギ(幼魚)は禁漁となっているのですが、密漁が多いと新聞に記事が掲載されていました。
実はニホンウナギは、2014年に「近い将来、野生での絶滅の危険性が高い」とされる「絶滅危惧1B種」として国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストに掲載されています。
絶滅危惧1B種は、複数ある絶滅危惧種のランクの中でも、ラッコやトキ、ジャイアントパンダなどと同じ2番目に危機度の高いランクです。しかも 卵から孵化させることが出来ない魚だそうです。
ニホンウナギはマリアナ海溝付近で産卵し、孵化します。その後北上してくる稚魚を捕獲して養殖する方法しかないそうです。現在は、稚魚の漁獲高もきめられているので漁獲高が増えることはまず無いようです。 冒頭ウナギの話題でしたが、次は、サステナブルを考える食材に関する新たな情報を提供させていただきます。
8月2日山陽新聞に「香ばしく干しエビのよう」 吉備中央町で食用コオロギ養殖 という記事がありました。 少し前に地元テレビのニュースで見たような気もして、関連記事を調べてみました。
同記事では、 倉庫の2階を転用した養殖場 プラスチック製のコンテナ 100個が3段に並べられている。ヨーロッパイエコオロギ 体長2cmほどエンマコオロギよりやや小さい。
記者の食レポでは、干したサクラエビのようでパリッとした食感、香ばしい風味が。広がったとあります。
1袋 11匹入り216円で近くの道の駅で販売しているほか、地ビールや菓子、おつまみを共同開発した。
養殖は、25~30℃を保ち通年行う。とあり、「陸えびJAPAN」(OKAEBI) という会社が養殖をしています。
コオロギは食べられるんだ 知らなかったからスタートです。昆虫食の盛んな国としてはアジアではタイが有名。 スーパーマーケットでは、冷凍のタガメやカイコガのサナギ、ヨーロッパイエコウロギ、バッタ、タケットガの幼虫などが売られている光景を目にする。 屋台ではこれら虫の佃煮が軒を飾っている。 さらに食用昆虫の養殖が広がっている。とネットの記事を見つけました。
日本では、長野県 伊那市には川魚や山菜とともに、ハチの子、ざざ虫、蚕のさなぎ、イナゴという4種類の昆虫の佃煮を作り続ける「塚原信州珍味(店舗名:つかはら)」。があります。 この地域の人たちは、イナゴは家庭の味・弁当のおかずで、日常生活に浸透した、昔ながらの家庭料理という事が分かりました。
なぜ、昆虫なのでしょうか?
きっかけは2013年に国際連合食糧農業機関(FAO)が発表した報告書がきっかけです。
FAOによると、2050年には世界人口が90億人を超え、食糧危機が深刻化するとしており、昆虫は、タンパク質などの栄養素を豊富に含むこと、養殖に必要とされる土地や飼料が家畜などに比べ大幅に少なく環境負荷が小さいことから、「飼育変換率」と「環境負荷」に優れた効果があると報告されたことで、『食品としての昆虫の活用が動物性たんぱく質の配給源として世界的に注目を集めた』のです。
FAOの発表を受け、健康意識・環境意識が高い欧米の消費者を中心に昆虫食への関心が高まり、2010年代半ばから昆虫食の市場に新規参入するベンチャー企業が増加しているとのこと。これらの企業は、コオロギやミールワーム(甲虫)などの昆虫の粉末を原材料に使った、昆虫の原型をとどめない加工食品を発売。伝統食とは異なる新しい昆虫食の市場を形成し始めているそうです。
製品の主な事例としては、プロテインバー、チップスなどのスナック菓子、パン、ハンバーグなどがあり、消費者にとって抵抗感の少ない形態で商品展開されています。
2018年には、欧州連合(EU)が昆虫を食品として認可し自由な取引を承認したことから、今後市場が大きく拡大することが期待されるとあります。
昆虫を原材料とする食品は通常の食品に比べ価格が高いことが市場拡大の阻害要因となっていたが、食用昆虫の養殖に力を入れる企業が増加。今後、原材料としての昆虫の供給量が増えることで、製品価格の低下が進むと予想され、それに伴い、昆虫食の開発や普及が更に進み、市場は拡大していくと見込まれるとのことです。
この昆虫食の流れが、日本でもそして、地元岡山でも少しずつ見られ始めています。2020年のネットの投稿では、全国で53か所に昆虫食自動販売機 が設置されているとあります。
コオロギ、タガメ、タランチュラ、イモムシ、サソリ、カブトムシ――昆虫食を売る自販機には、これら食用昆虫を詰めた容器が整然と並ぶ。
「バッタやコオロギは、素揚げし、塩を振ってパッケージに詰める。この手順はポテトチップスと同じ。
香りは居酒屋で食べる川エビの唐揚げに近い。昆虫もエビも硬い殻を高温で揚げるのでどちらも香ばしい。とはいえ、味は虫の種類によって異なる」とコインロッカーや自販機、ATMなどの設置・管理を手掛けるティ・アイ・エス(東京・台東)の営業担当者。2020年に入ってから、同社は都内3カ所に昆虫食の自販機を新しく設置し、運営を始めたとあります。
では、岡山では、どうなのでしょうか?
昆虫食の自販機が2022年6月時点で2か所設置されています。1件は鷲羽山ハイランドに、もう1件は
岡山市北区妹尾のジーンズファクトリー駐車場裏に設置されています。
商品ラインナップはすと、コオロギ、バッタ、サソリ、タガメ、ゲンゴロウ、セミやワームなどなどとネットで紹介されています。値段は、流通量が少ないので、高め コオロギのお試し価格は800円
https://www.youtube.com/watch?v=zvhVr3XEuM8
昆虫は嫌いという方は多いと思います。ましてはそれを食べるなんて、とても考えられない。
そんな方のためにか 無印良品では、これからの地球のことを考えて、コオロギのパウダー入りのせんべいを作りました。エビのような香ばしい風味が特長です。『コオロギせんべい』 55g 消費税込みで190円。コオロギチョコも販売しています。お菓子だけでなく、コオロギを練りこんだうどんを発売している企業もあります。
「bugoom(バグーム)」は、コオロギが練り込まれた業界初の「カップうどん」を発売しました。
(https://bugoom.jp/?AC=b9)
製法にこだわったコオロギ麺を使用。吟味した小麦粉とコオロギパウダーを本来の味を損なわないように、清水で練り上げ熟成させることで上質なコオロギ麺に仕上げました。
こだわり製法のコオロギ麺には、1食分につき約100匹分のコオロギパウダーを練り込まれています。
「昆虫食には抵抗がある」という方でも美味しく味わっていただけるように、姿が残った虫を一切入れておりません。これまで昆虫食に抱いていた先入観にとらわれることなく、素材本来の味わいをご堪能いただけます。」あります。
かつお・さば・しいたけ・昆布など旨味たっぷりの素材を使ったお出汁が、コオロギ麺の味わいをぐっと引き立ててくれるそんな一品。お湯を注いでレンジで調理、簡単に調理できる業界初のカップうどんです。
商品名:「コオロギうどん」 内容量:120g(めん90g) 小売希望価格:810円(税込)
商品URL:https://bugoom.jp/cricket/item_5727.php?child=5729&AC=b9
とあります。流通量が少ないだけに価格は高いと感じます。たべるとおいしいのではないかとの期待もあります。
では、なぜ昆虫食 なかでもコオロギなのでしょうか?
先述の無印良品のHPには、以下の事が書かれてあります。コオロギが地球を救う
https://www.muji.com/jp/ja/feature/food/460936
やがて来るだろう世界の食糧危機への対策として、昆虫食が注目を集めています。
栄養価が高く環境への負荷も少ないことから、国連食糧農業機関(FAO)も推奨。
まだ抵抗感をもつ人も多い食材ですが、無印良品は徳島大学と連携してコオロギ粉末入りのチョコとせんべいを開発しました。地球にやさしい未来食です。
☆人口増加と食糧の確保
2050年には世界人口が100億人になることが予想されています。そのため、重要な栄養素であるたんぱく質を確保することが重要な課題とされています。そこで、家畜の代替えとしての昆虫食が注目され始めています。
☆昆虫食と栄養素
昆虫は主な動物性たんぱく資源の家畜と同じく、主要な栄養素を多く体内に含むため、栄養素を効率よく摂取することができます。
以下は、私達が食べる食肉との比較データです。
① 100gあたりのたんぱく質量
コオロギ:60.0g 鶏:23.3g 豚:22.1g 牛:21.2g
(※コオロギ:パウダー、鶏:むね肉、豚:もも肉、牛:もも肉にて算出、※コオロギの数値:日本食品分析センターにて分析 / 牛・豚・鶏の数値:文部科学省 食品成分データベースより算出)
☆環境への負荷
昆虫を生育する際の温室効果ガス排出量や必要な水やエサの量は、一般的な家畜と比べて圧倒的に少なく、環境負荷も軽減されると言われています。
② えさの必要量 コオロギ:1.7kg 鶏:2.5kg 豚:5kg :牛10kg
③ 水の必要量 コオロギ:4L 鶏:2300L 豚:3500L 牛:22000L
④ 温室効果ガス排出量 コオロギ:0.1kg 鶏:0.3kg 豚:1.1kg :牛2.8kg
(※たんぱく質1kgを生産する際の数値です ※出典元:2013年 FAO報告書) 牛や羊は、ゲップをします。そのメタンガスは1年間に排出される温室効果ガスの5%を占めており、CO2の10倍以上の温室効果があると言われています。この数字を見ると一目瞭然です。
また、食べた人の感想も掲載されています。
https://www.muji.com/jp/ja/feature/food/460936
「陸えびJAPAN」のHPには、コオロギの栄養についてこんなことも書いてありました。
タンパク質やオメガ3・必須アミノ酸BCAAを豊富にバランスよく含み、ビタミン・ミネラル・亜鉛、鉄分、カルシウム、マグネシウム腸内環境の改善とデトックスに効果があると言われるキチン質という食物繊維も含まれ、体に必要な栄養素がバランスよく含有されています。可食部分はほぼ100%。
省スペースでの飼育が可能で、成長が早い為、出荷までのサイクルが40日前後と生産効率が良く、雑食性でもある為、「フードロス」の食品残渣も利用して生産が可能です。
同社は、生産へのこだわり として 「生産者の人間性」 生産者の想いは昆虫や商品にまで影響すると考えております。命を扱う職業である事を自覚し、重んじ、昆虫への敬意は忘れません。生産における日々のストレス軽減・衛生管理など最善の配慮・改善を続けています。安定した、栄養豊富で美味しい昆虫食をお届けいたします。 アニマルウェルフェアならぬ、インセクトウェルフェアにも配慮していることが分かりました。
また、「環境配慮」として、魚粉を利用せずに、米ぬかを主原料とした配合飼料を食べて育っています。
ここまで、読んでくると、環境や将来世代の事を考えると昆虫食にもチャレンジしないといけないかなぁという気持ちにはなります。でもなんとなくまだ、自信がないという方には、ビールをお薦めします。
『コオロギをグツグツ煮込んだエキスを原料にした地ビールを、岡山市内の醸造所がつくった。湯気は生臭かったものの、熟成を経ると、マイルドでこくのある飲み口に。』330ミリリットル入りで800円と高めの価格設定だが、意外と人気で、新たなラインアップも準備しているという。
コオロギビールをつくったのは吉備土手下麦酒醸造所(岡山市北区)。これまでも季節の果実やショウガ、カモミールを使ったビールなど、独自の商品展開を進めてきた。新たに目を付けたのは虫だった。
「昆虫食」は地球温暖化に伴う食糧危機の解決策の一つとされる。昆虫は牛や豚などの家畜より圧倒的に少ないエサや水、エネルギーで効率的に育てることができ、たんぱく質の含有量も肉と比べて遜色はないという。 同醸造所は2月、吉備中央町産の米ぬかで育てられた生の食用コオロギ2キロを煮込んで「だし」を取り、麦汁にブレンド。200リットルのビールを造った。
今年に入り 「陸えびJAPAN」にはコオロギ養殖の取材が新聞やTVなどで7件あったといいます。今後コオロギに関する話題に注目です。
- 中山間地域の高齢化・人口減少について
- 私は岡山県高梁市の出身です。高梁市は岡山県内有数の高齢化率の中山間地域であり、それ故に多くの問題を抱..