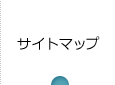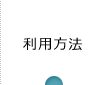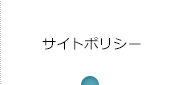タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
持続可能な社会を考える 「エシカルファッション:ファッションロスをなくす」
地域課題・社会課題環境
今日は、こんにちは、ゆうあいセンターSDGs&CSR相談員 小桐です。
先日、新暦の七夕を迎え、 暑さが本格的と思ったら各地での大雨、セミは晴れ間では元気に残り少ない命を次に伝えようと盛んに鳴いています。明日は大暑そして、土用の丑の日でもあります。
夏休みも始まり、本格的な夏の到来のようです。
今回の雨では、岡山県では大きな被害はなかったと思いますが、地球温暖化により、豪雨災害、台風の被害が大きくなったり、あるいは、干ばつ、渇水となったり、これまでとは、違う気象の変化が起こると専門家からは言われています。 欧州では熱波で大規模な山火事が起きています。
一見、今回のテーマとは無縁のように思えるかも知れせんが、ファッションロスは、地球温暖化と関わりがあるのです。
皆さんは「フードロス」の事はもちろんご存知ですよね。このフードロスを減らそうと様々な取り組みが行われています。食品廃棄で焼却すると生ごみだと1kgを燃やすのに2kgのCO2が発生してしまいます。
日本全体では、2015年(平成27年)に646万トンあったのが2020年(令和2年)には、522万トンまで下がっています。(2022年6月9日 農林水産省) 推移データは 下記をご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/attach/pdf/220609-5.pdf
まだ、フードロスは多いですが、社会的な関心が高まり、国、企業、団体や個人などが意識し、努力することによって減少傾向にあります。
「ファッションロス」 着なくなった服
まずは、ファッションロスのデータです。2018年に日本国内市場に出回った衣料品約29億点のうち、
15億点が売れ残っていると推測されています。(小島ファッションマーケティングの調査)その15億着は売れ残りとなり廃棄されているといわれています。バーゲンで売ればブランドイメージの低下につながるのでそれを避けるための廃棄という事のようです。
直近では、日本での新品の生産数は年間40~50億着で、国内で10億~30億着が捨てられている(PULSE OF THE FASHION INDUSTRY 2017)ということなので、新品以外の中古衣料も多く捨てられていると推測されます。これは、衣料品の購入単価や輸入単価が、1991年を基準とすると、現在はその6割程度の価格にまで下落した影響もあるのかもしれません。
環境省のデータでは、年間一人当たり18枚の服を買い、毎年12枚の服を手放し、着られない服が25枚あるというのです。
「衣料品のライフサイクルの短命化」により無駄に捨てられる衣料品の現状、捨てられた衣料がごみ問題となっています。 アメリカやヨーロッパ、アジアで不要になった約5万9000トンの服が毎年チリの港に届き、このうち3万9000トンはアタカマ砂漠の廃棄場に運ばれる。砂漠に運ばれた大量の使用済みの服は一帯を覆うほどで"ファストファッションの墓場"となっています。
製造する際に膨大なエネルギーや水資源を使い、環境負荷が大きい産業であるだけでなく、(全産業中ワースト2位の環境破壊)未着用や着用後の廃棄も環境負荷を与えている現状では、ファッションでの持続可能性を考えないわけにはいきません。
このような状況を憂慮し、フランスでは、2019年8月、フランス政府の呼びかけによって「ファッションパクト(ファッション協定)」がスタートしました。 フランスで開催されたG7サミットで欧米を中心とするファッションおよびテキスタイル企業32社が、環境保護などを定めた協定(気候変動、生物多様性、海洋保護の3分野で共通の具体的な目標に向かって取り組むことを誓約したもの)です。
協定の発足をリードしたケリング(KERING)を筆頭に、シャネルやH&Mなどの有力企業が数多く参加。21年7月末時点までに71社以上のブランドが加盟し、日本からは、アシックス1社が 2020年12月10日に加盟を表明しています。
さらに、フランスで2020年2月10日、在庫や売れ残り品の廃棄を禁止する新たな法律が採択されました。施行は2022年1月1日からです。
これは、「廃棄禁止及びサーキュラーエコノミーに関する法律(“売れ残り品廃棄禁止”法」)です。
同法律には、商品が環境に与える影響を明示する表示義務、食品以外の売れ残り品の廃棄を原則として禁止するといった内容が定められており、売れ残った新品のアパレル製品を廃棄(焼却や埋め立て)することを禁ずるものです。違反した場合は1万5000ユーロ(約195万円)の罰金が科されます。
この旗振り役を務めるのがブリュヌ・ポワルソン=フランス環境連帯移行大臣付副大臣。「“廃棄禁止”は第一ステップにすぎない」とし、さらなるサステナビリティ加速をしていく予定です。同女史は、『ファッション業界は世界で2番目に環境を汚染しているにもかかわらず、数年前まで、環境問題やサステナビリティについて話すブランドやメーカーは殆どなかった。』
『ファッション業界は海洋プラスチックごみの3分の1に責任がある。まず、プラスチックごみが出ないようにすることが重要なので、洗濯機にフィルターを付ければいいのです。マイクロプラスチックごみが川に、そして海に直接流れ込むのを食い止めたい。そのために、洗濯機にフィルターを付けることを義務付ける。』フランスでは、年間250万台の洗濯機が販売されており、業務用の洗濯機にもフィルターを付けることを義務付ける。というものです。これが2つ目のステップです。
『3つ目のステップ。最近の消費者は、自分が着ている服がどこでどのように作られたのかを知りたいと思っている。誰がデザインしたのか、誰がどのように製造したのかを知りたいのです。ですから、その情報を消費者に提供するタグを衣服に付けます。フランスで販売される全ての衣料に、環境や社会的な問題への影響に関する情報が含まれているタグを付けるよう、現在急ピッチで開発を進めています。』
さすが、ファッションを世界でリードするフランスです。トップランナーと世界廃棄の現状についてどう考えますか? SDGs視点でとらえるとどちらの行動になるのが良いのでしょうか?
日本でもフランスの動きを取り入れたい時期もありました。2020年8月26日に当時の小泉進次郎・環境大臣は、NPO団体ファッション レボリューション ジャパンの提言を受け、伊藤忠商事や豊島、ファーストリテイリング、H&Mジャパン、アダストリア、帝人フロンティアなど9社のファッション企業との意見交換会を行いました。ファッション企業による自社の取り組みの説明を聞き、小泉大臣は欧米の有力企業・ブランドが入っている『ファッション協定(The Fashion Pact)』にも日本企業が一つも入っていない。多くの素晴らしい取り組みをしているからこそ、まずは加盟することで向こうの土俵に乗り、その上で取り組みをアピールしてほしい」と逆提案を行いました。
意見交換会には、上記の伊藤忠などのほか、日本環境設計、クラボウ、東レ、アダストリアが自社のサステナブルの取り組みを紹介。
その後は環境省の「森里川海プロジェクト」アンバサダーで意見交換会のファシリテーターを務めた鎌田安里紗さんのほか、クルックの江良慶介氏、モデルのトラウデン直美、森摂「オルタナ」編集長、渡辺三津子「ヴォーグジャパン」編集長も交えたディスカッションを行いました。
そして、その結果アシックスが1社参加しました。
とは言え、大手アパレルがファッションロスに関して動きを見せているという情報はなかなか入ってきません。 国内で先進的な取り組みをする企業が動くまで私たちは、何も出来ないのでしょうか?
個々のメーカーや個人で出来る行動は無いのでしょうか?
・前回ご紹介したエシカルファッションの定義の中の最後⑧は、「ウェイストレス:ゴミを減らす仕組みづくり」
です。商品の製造段階では、以下のような対策が考えられます。
① 製造ロスをなくす:生地などの原材料の残りを副資材の余分をなくす
② 不良品を減らす・無くす
③ 売れ残りを減らす・無くす(そもそも捨てる計画で作らない)
この3点について、岡山県内外で行われている取り組みをご紹介します。
① 生地を裁断して縫製する服では、生地ロスをゼロにすることは無理です。できるだけ捨てる部分が出ないようにパーツを組みあわせてカットすることが求められます。 岡山県では、制服を製造する多くのアパレルが端切れは捨てずに業者に渡し、反毛(はんもう)といって、自動車や住宅の内装のフェルト(断熱材等)や紡毛衣料の糸などに再利用しています。コットンがはいったものは、ウエスという工業用雑巾として使われたりもします。
糸から編立をするニット製品では、無縫製で立体的にニット製品をつくる編立機(ホールガーメント)があり、材料の一切の無駄がありません。 https://www.shimaseiki.co.jp/wholegarment/business/
残ったボタンやスナップなどの副資材を有効活用してジーンズ製造を行っているのが、ベティスミス。
「エコベティプロジェクト」として、オーダージーンズやカスタム製品に活用しています。
② 不良品を減らす・無くす 破れたジーンズをエプロンに作り替えアップサイクルとして別な商品を作り、新しい価値を与える1点もの生産もベティスミスでは取り組んでいます。
③ 売れ残りを減らす・無くす、そもそも捨てる計画で作らない
これに取り組んでいる事例を紹介します。
2021年9月15日にNHKで放映された 未来へ17ACTION☆TV 「服を売ろうとしない服屋さん」
Enter the Eの代表植月 友美さんは、完全受注生産のエシカルファッションブランド「E」を立ち上げました
「服には物語がある」原料の栽培から糸、布となり、デザインされ、縫製され一つの商品になるまで、それに関わる多くの人たちの思いがあるのです。そして購入者が服と出会う。出会いの際に何が伝わるか
少しの期間だけ、何回か着て捨てられる服をなくしたい、ずっと自分を表現する服として服の物語を共有できる服作りをおこなっています。 その形が エシカル + 受注生産 クラウドファンディングで思いを同じにする人が協力して顔が見える服作りをするというものです。
地元岡山では、ITONNAMI(旧エブリデニム)さんがデニムの工場をめぐるツアーで、作り手との対話や思いが伝わる服作りをしています。そのために、宿泊施設FLOATとショップが一体化した施設をオープンしました。同社は、着られなくなったデニムを回収し、粉砕し再生糸からデニムの再生布をつくるリサイクルブランドFUKKOKU、もう一度染め直して着るfukuen、さらに自分で栽培した綿花を生地にいれてデニム製品をつくる服のたね という取り組みを行っています。 愛着のあるものならばずっと着続ける、どうしても着られなくなったらリサイクル、リメイクという考え方です。
服といえば今は買うものですが、江戸時代は、綿の種をまき、収穫後糸を紡ぎ、布を織り、服を作っていました。服はおさがり、着られなくなったら端切れにして布団へさらにおしめやぞうきんに最後は燃やして灰にして、畑に肥料として撒く。完全な循環社会だったのです。
伝統的なライフスタイルを今、若い世代を中心にアップデートしていこうという流れが世界に広がってきつつあるという事ではないでしょうか?
出来た服をできるだけ長く着ようとうリユースの取り組みを学生服の分野で行っているのが岡山市東区
西大寺の五福通りにある古着屋ループさん 小・中・高の服を色々と取り揃えています。
もともと学校制服はポリエステルとウールで作られているので結構丈夫です。
私事で申し訳ありませんが、息子のブレザーは知り合いから譲っていただき、3年着た後、いとこに譲りました。最低でも9年間は切られたことになります。かなり前の愛媛県での話ですが、知り合いから譲ってもらった娘さんのセーラー服の名前を見たらその母親のものだったという驚くべき事実もあります。制服は丁寧に着てメンテナンスをきちんとすれば20年ほどは着られるのです。
先日ネットで見つけたのはファッションのサブスクでした。月額一定料金を払うと最低3着のセットが送られてきて、着続けられます。ただし、全て中古品 しかしプロのコーディネイターがその人の好みの調査えーたから選ぶというものです。気に入らなければ返品はできるそれは次の誰かに送られるというものです。
個人単位では、メルカリなどフリマアプリの利用で服を捨てずに売って次の人に託すというものもあります。
これからは、たくさんの服を所有する時代ではなく、自分の好みや服が出来るまでのストーリーに心をはせ、服を大切にして、リペア(修理)したり、リメイク(作り直し)をして愛着を持って着ることが重要になってくるのではないでしょうか?
衣類を購入する側が「吟味して商品を選ぶ」 =リデュース(減らす=捨てるものを選ばない)がまず一歩。
出来れば、ミシンとアイロン、裁縫箱を持って簡単な修理やリメイクをできるようになりたいものです。
男女の関係はありません。
筆者も愛用のボタンダウンシャツがあります。グリーンのギンガムチェックです。最初は長袖でした。長く着ると袖口が破れたので取り外し、裏返しにして左右変えて着ました、そうするうちに襟が破れそうになったのでこれも上衿を取り外し、裏返しに取り付けて着ました。2回目の袖口が破れたので、半袖に切り落としました。今も愛用していますが、襟が破れてきました。20年ほど着ていますので、色もかなり薄くなった気がします。今度はどのようなリメイクをしようかと思案中です。
気に入ったものは自分で修理すると愛着も湧きます。人生の何に時間を使うのか、使いたいのかを考え直すタイミングではないでしょうか? キャンプが流行っていますがわざわざ不便や手間をかけて自分で作る、工夫をして時間を楽しむというところは共通しているようにも感じます。
自然はありがとうのつながりで成り立っています。私たちもまた、自然の一部であり、ありがとうのつながりの中で暮らしているように感じます。ありがとうのつながりが途絶えたり、見えなかったりする様々な不具合やトラブルが生まれるのではないでしょうか。 ファッションロスを生み出さない工夫をしていきたいものです。
先日、新暦の七夕を迎え、 暑さが本格的と思ったら各地での大雨、セミは晴れ間では元気に残り少ない命を次に伝えようと盛んに鳴いています。明日は大暑そして、土用の丑の日でもあります。
夏休みも始まり、本格的な夏の到来のようです。
今回の雨では、岡山県では大きな被害はなかったと思いますが、地球温暖化により、豪雨災害、台風の被害が大きくなったり、あるいは、干ばつ、渇水となったり、これまでとは、違う気象の変化が起こると専門家からは言われています。 欧州では熱波で大規模な山火事が起きています。
一見、今回のテーマとは無縁のように思えるかも知れせんが、ファッションロスは、地球温暖化と関わりがあるのです。
皆さんは「フードロス」の事はもちろんご存知ですよね。このフードロスを減らそうと様々な取り組みが行われています。食品廃棄で焼却すると生ごみだと1kgを燃やすのに2kgのCO2が発生してしまいます。
日本全体では、2015年(平成27年)に646万トンあったのが2020年(令和2年)には、522万トンまで下がっています。(2022年6月9日 農林水産省) 推移データは 下記をご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/attach/pdf/220609-5.pdf
まだ、フードロスは多いですが、社会的な関心が高まり、国、企業、団体や個人などが意識し、努力することによって減少傾向にあります。
「ファッションロス」 着なくなった服
まずは、ファッションロスのデータです。2018年に日本国内市場に出回った衣料品約29億点のうち、
15億点が売れ残っていると推測されています。(小島ファッションマーケティングの調査)その15億着は売れ残りとなり廃棄されているといわれています。バーゲンで売ればブランドイメージの低下につながるのでそれを避けるための廃棄という事のようです。
直近では、日本での新品の生産数は年間40~50億着で、国内で10億~30億着が捨てられている(PULSE OF THE FASHION INDUSTRY 2017)ということなので、新品以外の中古衣料も多く捨てられていると推測されます。これは、衣料品の購入単価や輸入単価が、1991年を基準とすると、現在はその6割程度の価格にまで下落した影響もあるのかもしれません。
環境省のデータでは、年間一人当たり18枚の服を買い、毎年12枚の服を手放し、着られない服が25枚あるというのです。
「衣料品のライフサイクルの短命化」により無駄に捨てられる衣料品の現状、捨てられた衣料がごみ問題となっています。 アメリカやヨーロッパ、アジアで不要になった約5万9000トンの服が毎年チリの港に届き、このうち3万9000トンはアタカマ砂漠の廃棄場に運ばれる。砂漠に運ばれた大量の使用済みの服は一帯を覆うほどで"ファストファッションの墓場"となっています。
製造する際に膨大なエネルギーや水資源を使い、環境負荷が大きい産業であるだけでなく、(全産業中ワースト2位の環境破壊)未着用や着用後の廃棄も環境負荷を与えている現状では、ファッションでの持続可能性を考えないわけにはいきません。
このような状況を憂慮し、フランスでは、2019年8月、フランス政府の呼びかけによって「ファッションパクト(ファッション協定)」がスタートしました。 フランスで開催されたG7サミットで欧米を中心とするファッションおよびテキスタイル企業32社が、環境保護などを定めた協定(気候変動、生物多様性、海洋保護の3分野で共通の具体的な目標に向かって取り組むことを誓約したもの)です。
協定の発足をリードしたケリング(KERING)を筆頭に、シャネルやH&Mなどの有力企業が数多く参加。21年7月末時点までに71社以上のブランドが加盟し、日本からは、アシックス1社が 2020年12月10日に加盟を表明しています。
さらに、フランスで2020年2月10日、在庫や売れ残り品の廃棄を禁止する新たな法律が採択されました。施行は2022年1月1日からです。
これは、「廃棄禁止及びサーキュラーエコノミーに関する法律(“売れ残り品廃棄禁止”法」)です。
同法律には、商品が環境に与える影響を明示する表示義務、食品以外の売れ残り品の廃棄を原則として禁止するといった内容が定められており、売れ残った新品のアパレル製品を廃棄(焼却や埋め立て)することを禁ずるものです。違反した場合は1万5000ユーロ(約195万円)の罰金が科されます。
この旗振り役を務めるのがブリュヌ・ポワルソン=フランス環境連帯移行大臣付副大臣。「“廃棄禁止”は第一ステップにすぎない」とし、さらなるサステナビリティ加速をしていく予定です。同女史は、『ファッション業界は世界で2番目に環境を汚染しているにもかかわらず、数年前まで、環境問題やサステナビリティについて話すブランドやメーカーは殆どなかった。』
『ファッション業界は海洋プラスチックごみの3分の1に責任がある。まず、プラスチックごみが出ないようにすることが重要なので、洗濯機にフィルターを付ければいいのです。マイクロプラスチックごみが川に、そして海に直接流れ込むのを食い止めたい。そのために、洗濯機にフィルターを付けることを義務付ける。』フランスでは、年間250万台の洗濯機が販売されており、業務用の洗濯機にもフィルターを付けることを義務付ける。というものです。これが2つ目のステップです。
『3つ目のステップ。最近の消費者は、自分が着ている服がどこでどのように作られたのかを知りたいと思っている。誰がデザインしたのか、誰がどのように製造したのかを知りたいのです。ですから、その情報を消費者に提供するタグを衣服に付けます。フランスで販売される全ての衣料に、環境や社会的な問題への影響に関する情報が含まれているタグを付けるよう、現在急ピッチで開発を進めています。』
さすが、ファッションを世界でリードするフランスです。トップランナーと世界廃棄の現状についてどう考えますか? SDGs視点でとらえるとどちらの行動になるのが良いのでしょうか?
日本でもフランスの動きを取り入れたい時期もありました。2020年8月26日に当時の小泉進次郎・環境大臣は、NPO団体ファッション レボリューション ジャパンの提言を受け、伊藤忠商事や豊島、ファーストリテイリング、H&Mジャパン、アダストリア、帝人フロンティアなど9社のファッション企業との意見交換会を行いました。ファッション企業による自社の取り組みの説明を聞き、小泉大臣は欧米の有力企業・ブランドが入っている『ファッション協定(The Fashion Pact)』にも日本企業が一つも入っていない。多くの素晴らしい取り組みをしているからこそ、まずは加盟することで向こうの土俵に乗り、その上で取り組みをアピールしてほしい」と逆提案を行いました。
意見交換会には、上記の伊藤忠などのほか、日本環境設計、クラボウ、東レ、アダストリアが自社のサステナブルの取り組みを紹介。
その後は環境省の「森里川海プロジェクト」アンバサダーで意見交換会のファシリテーターを務めた鎌田安里紗さんのほか、クルックの江良慶介氏、モデルのトラウデン直美、森摂「オルタナ」編集長、渡辺三津子「ヴォーグジャパン」編集長も交えたディスカッションを行いました。
そして、その結果アシックスが1社参加しました。
とは言え、大手アパレルがファッションロスに関して動きを見せているという情報はなかなか入ってきません。 国内で先進的な取り組みをする企業が動くまで私たちは、何も出来ないのでしょうか?
個々のメーカーや個人で出来る行動は無いのでしょうか?
・前回ご紹介したエシカルファッションの定義の中の最後⑧は、「ウェイストレス:ゴミを減らす仕組みづくり」
です。商品の製造段階では、以下のような対策が考えられます。
① 製造ロスをなくす:生地などの原材料の残りを副資材の余分をなくす
② 不良品を減らす・無くす
③ 売れ残りを減らす・無くす(そもそも捨てる計画で作らない)
この3点について、岡山県内外で行われている取り組みをご紹介します。
① 生地を裁断して縫製する服では、生地ロスをゼロにすることは無理です。できるだけ捨てる部分が出ないようにパーツを組みあわせてカットすることが求められます。 岡山県では、制服を製造する多くのアパレルが端切れは捨てずに業者に渡し、反毛(はんもう)といって、自動車や住宅の内装のフェルト(断熱材等)や紡毛衣料の糸などに再利用しています。コットンがはいったものは、ウエスという工業用雑巾として使われたりもします。
糸から編立をするニット製品では、無縫製で立体的にニット製品をつくる編立機(ホールガーメント)があり、材料の一切の無駄がありません。 https://www.shimaseiki.co.jp/wholegarment/business/
残ったボタンやスナップなどの副資材を有効活用してジーンズ製造を行っているのが、ベティスミス。
「エコベティプロジェクト」として、オーダージーンズやカスタム製品に活用しています。
② 不良品を減らす・無くす 破れたジーンズをエプロンに作り替えアップサイクルとして別な商品を作り、新しい価値を与える1点もの生産もベティスミスでは取り組んでいます。
③ 売れ残りを減らす・無くす、そもそも捨てる計画で作らない
これに取り組んでいる事例を紹介します。
2021年9月15日にNHKで放映された 未来へ17ACTION☆TV 「服を売ろうとしない服屋さん」
Enter the Eの代表植月 友美さんは、完全受注生産のエシカルファッションブランド「E」を立ち上げました
「服には物語がある」原料の栽培から糸、布となり、デザインされ、縫製され一つの商品になるまで、それに関わる多くの人たちの思いがあるのです。そして購入者が服と出会う。出会いの際に何が伝わるか
少しの期間だけ、何回か着て捨てられる服をなくしたい、ずっと自分を表現する服として服の物語を共有できる服作りをおこなっています。 その形が エシカル + 受注生産 クラウドファンディングで思いを同じにする人が協力して顔が見える服作りをするというものです。
地元岡山では、ITONNAMI(旧エブリデニム)さんがデニムの工場をめぐるツアーで、作り手との対話や思いが伝わる服作りをしています。そのために、宿泊施設FLOATとショップが一体化した施設をオープンしました。同社は、着られなくなったデニムを回収し、粉砕し再生糸からデニムの再生布をつくるリサイクルブランドFUKKOKU、もう一度染め直して着るfukuen、さらに自分で栽培した綿花を生地にいれてデニム製品をつくる服のたね という取り組みを行っています。 愛着のあるものならばずっと着続ける、どうしても着られなくなったらリサイクル、リメイクという考え方です。
服といえば今は買うものですが、江戸時代は、綿の種をまき、収穫後糸を紡ぎ、布を織り、服を作っていました。服はおさがり、着られなくなったら端切れにして布団へさらにおしめやぞうきんに最後は燃やして灰にして、畑に肥料として撒く。完全な循環社会だったのです。
伝統的なライフスタイルを今、若い世代を中心にアップデートしていこうという流れが世界に広がってきつつあるという事ではないでしょうか?
出来た服をできるだけ長く着ようとうリユースの取り組みを学生服の分野で行っているのが岡山市東区
西大寺の五福通りにある古着屋ループさん 小・中・高の服を色々と取り揃えています。
もともと学校制服はポリエステルとウールで作られているので結構丈夫です。
私事で申し訳ありませんが、息子のブレザーは知り合いから譲っていただき、3年着た後、いとこに譲りました。最低でも9年間は切られたことになります。かなり前の愛媛県での話ですが、知り合いから譲ってもらった娘さんのセーラー服の名前を見たらその母親のものだったという驚くべき事実もあります。制服は丁寧に着てメンテナンスをきちんとすれば20年ほどは着られるのです。
先日ネットで見つけたのはファッションのサブスクでした。月額一定料金を払うと最低3着のセットが送られてきて、着続けられます。ただし、全て中古品 しかしプロのコーディネイターがその人の好みの調査えーたから選ぶというものです。気に入らなければ返品はできるそれは次の誰かに送られるというものです。
個人単位では、メルカリなどフリマアプリの利用で服を捨てずに売って次の人に託すというものもあります。
これからは、たくさんの服を所有する時代ではなく、自分の好みや服が出来るまでのストーリーに心をはせ、服を大切にして、リペア(修理)したり、リメイク(作り直し)をして愛着を持って着ることが重要になってくるのではないでしょうか?
衣類を購入する側が「吟味して商品を選ぶ」 =リデュース(減らす=捨てるものを選ばない)がまず一歩。
出来れば、ミシンとアイロン、裁縫箱を持って簡単な修理やリメイクをできるようになりたいものです。
男女の関係はありません。
筆者も愛用のボタンダウンシャツがあります。グリーンのギンガムチェックです。最初は長袖でした。長く着ると袖口が破れたので取り外し、裏返しにして左右変えて着ました、そうするうちに襟が破れそうになったのでこれも上衿を取り外し、裏返しに取り付けて着ました。2回目の袖口が破れたので、半袖に切り落としました。今も愛用していますが、襟が破れてきました。20年ほど着ていますので、色もかなり薄くなった気がします。今度はどのようなリメイクをしようかと思案中です。
気に入ったものは自分で修理すると愛着も湧きます。人生の何に時間を使うのか、使いたいのかを考え直すタイミングではないでしょうか? キャンプが流行っていますがわざわざ不便や手間をかけて自分で作る、工夫をして時間を楽しむというところは共通しているようにも感じます。
自然はありがとうのつながりで成り立っています。私たちもまた、自然の一部であり、ありがとうのつながりの中で暮らしているように感じます。ありがとうのつながりが途絶えたり、見えなかったりする様々な不具合やトラブルが生まれるのではないでしょうか。 ファッションロスを生み出さない工夫をしていきたいものです。
- 中山間地域の高齢化・人口減少について
- 私は岡山県高梁市の出身です。高梁市は岡山県内有数の高齢化率の中山間地域であり、それ故に多くの問題を抱..