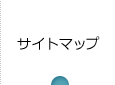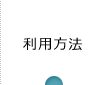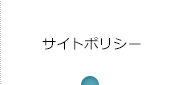タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
持続可能な地域づくり・・・地域の大人と若者の新たな行動力が社会を変える
地域課題・社会課題まち・むら
今日は、こんにちは、ゆうあいセンターCSR相談員 小桐です。
コロナウイルスデルタ株による感染拡大で、岡山県は第2回目の緊急事態宣言が8月25日に発せられました。
新学期を前に子どもの感染が夏休み前と比べ5倍ほどになっているとのこと。家庭内感染も広がりを見せ、ワクチンを打てない世代には、大変な状況です。今一度大人の行動を見直したいものです。
今回は、持続可能な地域をつくるために、岡山県内の各地で行われている学校教育と地域の関りや、その学校教育に県の南北で差があることを前提にそれを埋めるためにどのようなことが行われているのかをご紹介し、今後の地域や教育の変化について情報提供をさせていただきます。
SDGsネットワークおかやまが山陽新聞社と連携して行っている連続シンポジウム 「持続可能で活力ある地域づくりを考える」(4回シリーズ)では、第3回「教育の環境」、第4回「若者、政治、未来」というテーマで開催されています。それぞれのシンポジウムの前に、SDGsネットワークおかやま主催で、ワークショップを事前開催し、当日の深堀ができるように進めており、現時点では、第4回目の事前ワークショップが終了し、9月4日の最終回を迎える段階です。
第3回と4回のテーマは一見すると関係がないように感じますが、今後の岡山県の各地域の持続可能性や学校教育と地域、家庭のあり方について重要なキーワードでつながっていると感じています。
既に、山陽新聞では様々な取り組みやシンポジウムの内容が公表されていますが、山陽新聞記事や事前ワークショップにご参加いただいた皆様方の発言を引用しながら、少し視点を変えて地域や教育の持続可能性について書かせていただきます。
新見市は、平成17年に近隣4町と合併し新しい市となりました。その際に人と地域が元気なまちを創るという地域共生社会構築計画を立案。岡山県の西北に位置する同市は、人口減少、少子高齢化という地方都市に共通の課題を抱えています。同市では、学校連携コーディネーターを配置、7月12日の第3回事前ワークショップでは、同職の後藤秀則さんが、新見高(同市)の取り組みについて説明されました。
新見高生徒による小中学校への出前授業や、地域の人らが講師となったキャリア教育などで地元とのつながりを強めている。主権者教育として生徒が地元団体からアドバイスを得て地域活性化への提言をまとめた事例を挙げ、「高校生が地域に関わり、地域を変えていくことで肯定感や有用感が得られ、郷土愛を育むことにつながる」。 岡山県では、2023年度以降に1年生の生徒数が2年続けて100人を下回れば、高校再編の対象となる。基準があり、このままでは、過疎や少子化で子どもが減る中で、学校存続に危機が迫る。それだけに地域と連携した高校魅力化を進めているということでした。 県南県北の人口格差が広がる中、数だけでの基準がどうなのかを考えさせられる情報でもありました。
8月25日の第4回事前ワークショップでは、同校の水島先生が、主権者教育の一環で2017年度から取り組む新見市議会への陳情活動を紹介。通学路への街灯設置など陳情が施策に採用されており、「地域課題を自分事と捉えるようになり、政治参加への意識が育まれている」と話されました。
このほか、新見駅を中心としたまちづくりの提案を議会に陳情しており、市として検討中とのことです。
同校のOGである岡山大学生からは、自身が陳情したゴミ削減に関する提案は採用されなかったが、大学に入って陳情経験があることが貴重な学びであったこと、自身のゴミに関する行動にも変化があったことなどを語ってくれました。
自分が地域の一因である自覚に目覚めるとともに、自身の手で街を変えていくことができる経験は有意義だったようです。
同校のOGで岡山大学4年生の真壁さんが新見市の中学で、教育実習を重ねています。同氏は教育学部の「県北地域教育プログラム」の1期生。「岡山県北の小中学校に勤務しながら、地域づくりに貢献できる教員の育成を目指す取り組み」で、来春、1期生19人が巣立つ。学校を拠点に地方創生の起爆剤としての活躍が期待されるとともに、地域に根差す若手教員の確保という使命も担うものです。 (10年県北勤務が最低条件)これまで、力をつけたら、県南へ戻るという教育の悪循環を解消する目的もあります。 自分の住む町で学び、地域に育ててもらった若者は、新たな地域づくりに貢献できる人材となり得ることが期待されるのではないでしょうか?
若者の中には、自発的に行動する人たちの存在も見逃せません。第3回と4回のワークショップ、第3回シンポジウムで司会も務めてくれた鏡野町在住、津山高校3年生の福寺君は、2年生の時に「高校生として面白いことをやりたい。県北という立地を超えてできることを始めたい」と鏡野ユースサークルを4人の高校生で立ち上げました。オンラインイベントを活用し、遠隔地の大学の先生から学んだり、自分たちで主催した鏡野町長選立候補予定者の公開討論会を実施したりしています。さらに町総合計画への意見提示を通じて「自分たちが町の変化を担う一員であると実感できた」と話しました。
第3回シンポジウムでは、「県北地域教育プログラム」を岡山大学服部徳仁教授が説明されました。県北での教師経験が長かった山下陽子 語らい座大原本邸(前倉敷南高校長) は県北と県南の教育環境の差を認識しつつも、県北の生徒は自分のまちに愛着を感じる生徒が多い、社会や自然の中で生かされていることを学ぶ機会が多い。一方、県南の生徒は、キャリア教育を考えると多くの産業があり、ビジネスモデルを学べるが地域との関りは薄い。倉敷南高では、地域との関りを学ぶ機会ができるようにと、倉敷町衆プロジェクト(地域の人と進路や祖ごとについて話す機会などを提供)を始めたと話されました。その中で、生徒、教師、保護者、地域がチームを作って教育を支えることが大切と感じたと発言されました。
第4回の事前ワークショップで、岡山市と倉敷市に挟まれたベッドタウン早島町の徳山順子教育長は、早島町は、小学校、中学校共に一つ。幼・保園生から中学生までを対象に様々な地域での体験や学習をする機会を作っている事。毎年、中学生らが探求したことを地域に提案する「子ども議会」「子どもフォーラム」「熟議」といった町の取り組みを説明されました。「地域の一員として子どもたちの提案を施策に生かすことで、地元へ愛着を持ち、社会の担い手を育てることにもつながる」とした。早島町はその立地もあり、少子高齢化の中、人口が増えている町です。
大人が、子供が育つ環境づくり、仕組みづくりをきちんとすれば、若者は、その土地を愛し、自分が地域の一員であることに誇りを持ち、新しいまちづくりの提案も積極的にできるように育つと感じられた事例紹介でした。
2回のワークショップとシンポジウムに参加した梶谷俊介 県教育委員・岡山経済同友会代表幹事は「行政の各種審議会に地域を担う高校生が参加すれば、若い世代の声を反映できる」と発言されています。
現状では、残念ながら教育面では成果を上げていても、「県内を見ると、高校の魅力向上対策が必ずしも定員割れ改善につながっていないケースもある」などの意見が出ました。 教育と持続可能性は密接な関係にあります。地域の事を自分事として考えられる教育が、県内の多くの高校で始まっています。地域学を学ぶ高校生たちが新たな未来を切り開いてくれるのだという感じたの2回の事前ワークショップ、1シンポジウムです。
最終回9月4日の最終シンポジウムはWEBでも配信され、その後も1週間程度視聴可能ですので是非、ご参加ください。
コロナウイルスデルタ株による感染拡大で、岡山県は第2回目の緊急事態宣言が8月25日に発せられました。
新学期を前に子どもの感染が夏休み前と比べ5倍ほどになっているとのこと。家庭内感染も広がりを見せ、ワクチンを打てない世代には、大変な状況です。今一度大人の行動を見直したいものです。
今回は、持続可能な地域をつくるために、岡山県内の各地で行われている学校教育と地域の関りや、その学校教育に県の南北で差があることを前提にそれを埋めるためにどのようなことが行われているのかをご紹介し、今後の地域や教育の変化について情報提供をさせていただきます。
SDGsネットワークおかやまが山陽新聞社と連携して行っている連続シンポジウム 「持続可能で活力ある地域づくりを考える」(4回シリーズ)では、第3回「教育の環境」、第4回「若者、政治、未来」というテーマで開催されています。それぞれのシンポジウムの前に、SDGsネットワークおかやま主催で、ワークショップを事前開催し、当日の深堀ができるように進めており、現時点では、第4回目の事前ワークショップが終了し、9月4日の最終回を迎える段階です。
第3回と4回のテーマは一見すると関係がないように感じますが、今後の岡山県の各地域の持続可能性や学校教育と地域、家庭のあり方について重要なキーワードでつながっていると感じています。
既に、山陽新聞では様々な取り組みやシンポジウムの内容が公表されていますが、山陽新聞記事や事前ワークショップにご参加いただいた皆様方の発言を引用しながら、少し視点を変えて地域や教育の持続可能性について書かせていただきます。
新見市は、平成17年に近隣4町と合併し新しい市となりました。その際に人と地域が元気なまちを創るという地域共生社会構築計画を立案。岡山県の西北に位置する同市は、人口減少、少子高齢化という地方都市に共通の課題を抱えています。同市では、学校連携コーディネーターを配置、7月12日の第3回事前ワークショップでは、同職の後藤秀則さんが、新見高(同市)の取り組みについて説明されました。
新見高生徒による小中学校への出前授業や、地域の人らが講師となったキャリア教育などで地元とのつながりを強めている。主権者教育として生徒が地元団体からアドバイスを得て地域活性化への提言をまとめた事例を挙げ、「高校生が地域に関わり、地域を変えていくことで肯定感や有用感が得られ、郷土愛を育むことにつながる」。 岡山県では、2023年度以降に1年生の生徒数が2年続けて100人を下回れば、高校再編の対象となる。基準があり、このままでは、過疎や少子化で子どもが減る中で、学校存続に危機が迫る。それだけに地域と連携した高校魅力化を進めているということでした。 県南県北の人口格差が広がる中、数だけでの基準がどうなのかを考えさせられる情報でもありました。
8月25日の第4回事前ワークショップでは、同校の水島先生が、主権者教育の一環で2017年度から取り組む新見市議会への陳情活動を紹介。通学路への街灯設置など陳情が施策に採用されており、「地域課題を自分事と捉えるようになり、政治参加への意識が育まれている」と話されました。
このほか、新見駅を中心としたまちづくりの提案を議会に陳情しており、市として検討中とのことです。
同校のOGである岡山大学生からは、自身が陳情したゴミ削減に関する提案は採用されなかったが、大学に入って陳情経験があることが貴重な学びであったこと、自身のゴミに関する行動にも変化があったことなどを語ってくれました。
自分が地域の一因である自覚に目覚めるとともに、自身の手で街を変えていくことができる経験は有意義だったようです。
同校のOGで岡山大学4年生の真壁さんが新見市の中学で、教育実習を重ねています。同氏は教育学部の「県北地域教育プログラム」の1期生。「岡山県北の小中学校に勤務しながら、地域づくりに貢献できる教員の育成を目指す取り組み」で、来春、1期生19人が巣立つ。学校を拠点に地方創生の起爆剤としての活躍が期待されるとともに、地域に根差す若手教員の確保という使命も担うものです。 (10年県北勤務が最低条件)これまで、力をつけたら、県南へ戻るという教育の悪循環を解消する目的もあります。 自分の住む町で学び、地域に育ててもらった若者は、新たな地域づくりに貢献できる人材となり得ることが期待されるのではないでしょうか?
若者の中には、自発的に行動する人たちの存在も見逃せません。第3回と4回のワークショップ、第3回シンポジウムで司会も務めてくれた鏡野町在住、津山高校3年生の福寺君は、2年生の時に「高校生として面白いことをやりたい。県北という立地を超えてできることを始めたい」と鏡野ユースサークルを4人の高校生で立ち上げました。オンラインイベントを活用し、遠隔地の大学の先生から学んだり、自分たちで主催した鏡野町長選立候補予定者の公開討論会を実施したりしています。さらに町総合計画への意見提示を通じて「自分たちが町の変化を担う一員であると実感できた」と話しました。
第3回シンポジウムでは、「県北地域教育プログラム」を岡山大学服部徳仁教授が説明されました。県北での教師経験が長かった山下陽子 語らい座大原本邸(前倉敷南高校長) は県北と県南の教育環境の差を認識しつつも、県北の生徒は自分のまちに愛着を感じる生徒が多い、社会や自然の中で生かされていることを学ぶ機会が多い。一方、県南の生徒は、キャリア教育を考えると多くの産業があり、ビジネスモデルを学べるが地域との関りは薄い。倉敷南高では、地域との関りを学ぶ機会ができるようにと、倉敷町衆プロジェクト(地域の人と進路や祖ごとについて話す機会などを提供)を始めたと話されました。その中で、生徒、教師、保護者、地域がチームを作って教育を支えることが大切と感じたと発言されました。
第4回の事前ワークショップで、岡山市と倉敷市に挟まれたベッドタウン早島町の徳山順子教育長は、早島町は、小学校、中学校共に一つ。幼・保園生から中学生までを対象に様々な地域での体験や学習をする機会を作っている事。毎年、中学生らが探求したことを地域に提案する「子ども議会」「子どもフォーラム」「熟議」といった町の取り組みを説明されました。「地域の一員として子どもたちの提案を施策に生かすことで、地元へ愛着を持ち、社会の担い手を育てることにもつながる」とした。早島町はその立地もあり、少子高齢化の中、人口が増えている町です。
大人が、子供が育つ環境づくり、仕組みづくりをきちんとすれば、若者は、その土地を愛し、自分が地域の一員であることに誇りを持ち、新しいまちづくりの提案も積極的にできるように育つと感じられた事例紹介でした。
2回のワークショップとシンポジウムに参加した梶谷俊介 県教育委員・岡山経済同友会代表幹事は「行政の各種審議会に地域を担う高校生が参加すれば、若い世代の声を反映できる」と発言されています。
現状では、残念ながら教育面では成果を上げていても、「県内を見ると、高校の魅力向上対策が必ずしも定員割れ改善につながっていないケースもある」などの意見が出ました。 教育と持続可能性は密接な関係にあります。地域の事を自分事として考えられる教育が、県内の多くの高校で始まっています。地域学を学ぶ高校生たちが新たな未来を切り開いてくれるのだという感じたの2回の事前ワークショップ、1シンポジウムです。
最終回9月4日の最終シンポジウムはWEBでも配信され、その後も1週間程度視聴可能ですので是非、ご参加ください。
- 中山間地域の高齢化・人口減少について
- 私は岡山県高梁市の出身です。高梁市は岡山県内有数の高齢化率の中山間地域であり、それ故に多くの問題を抱..