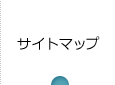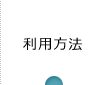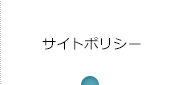タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
企業の社会的責任 環境と食について8~調達と廃棄について考える~
地域課題・社会課題環境岡山市
こんにちは、ゆうあいセンターCSR相談員 小桐です。
今週は、環境と食の中でも、調達と廃棄について考えます。第8回目の情報提供です。
入梅しましたが、岡山県は今の所、雨降らず状態、畑の作物は、雨を期待しているのではないでしょうか? 梅雨が明けると暑い夏がやってきます。暑さに負けないように土用の鰻が待ち遠しい方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回調達に関する話は、鰻にまつわるものです。 6月14日のRSKの夜の番組「VOICE LOVE」で紹介された鰻専門店は、自社の水槽で鰻を養殖していて、それを提供しているとの事です。
その種類は、絶滅が心配されるニホンウナギではなく、外来の鰻でした。自社の水槽なので、外来魚による環境影響の問題はなく、安定した国産ウナギが食べられる私たちにとっては、うれしい話です。
実は、倉敷市は鰻の養殖が盛んです。千葉県から稚魚を運び、倉敷アクアファームという企業が、閉鎖循環方式陸上養殖という方法で養殖した国産遺伝子を持つ国産のうなぎも数年前から養殖されています。トレーサビリティもしっかりしているので、岡山ではうなぎは安心して食べられそうです。本日6月15日の山陽新聞には、これと真逆の残念な記事が掲載されています。
昨年11月から今年4月にかけて採捕されたニホンウナギの幼魚シラスウナギの45.45%が密漁など違法取引に疑いがあることが共同通信の集計で分かりました。
ニホンウナギは2014年に国際自然保護連合と環境省により、近い将来における野生での絶滅の危険性が高い「絶滅危惧1B類」に指定されています。我が国は、中国、台湾、韓国との合意で資源管理の協定を結んでおり、国内の養殖池に入れるシラスを21.7トンまでに制限しています。国内でのシラス採捕は各自治体の知事の許可事項となっています。
しかし、19.4トンの池入れのうち、輸入物を除いた国内での採捕は15.5トン、許可申請をしているものは、8.4トンで7トンが無報告か密漁となっています。目先の利益だけを追うこの採捕の在り方には大いに疑問が残ります。鰻を食べる時にはトレーサビリティがしっかりした表示がなされる鰻を食べたいものです。
今後は、海のエコラベル「MSC(Marine Stewardship Council、海洋管理協議会)」
(:海洋の自然環境や水産資源を守って獲られた水産物(シーフード)に与えられる認証エコラベル)やASC:養殖版海のエコラベルの「ASC(Aquaculture Stewardship Council:水産養殖管理協議会)」の認証制度が広まることが期待されます。
温暖化防止対策を講じなければ、2100年頃には日本の海産物漁獲量が70%も減ると予測されており、自然資源は限りあるものとして大切にする業者への指導や消費者教育が求められる昨今です。
続いて、食品廃棄に関しての情報です。
世界で一番食べ物を輸入して、一番捨てている国はどこか 残念ながら日本です。
国内で消費する食品の量は9100万t、輸入食料は5800万tになります。そして、食べられない部位を含む食品くずや食べ残し、はたまた賞味期限により廃棄される食品の量は、1900万tにもなります。
食べ残し、賞味期限、過剰除去で食べられるのに捨てる「食品ロス」は年間620~630万tという量です。これは、世界中の食糧支援量390万tの2倍近い量なのです。世界では9億人が飢餓状態にあると言われており、お金の力で、他国から食べ物を搾取する行為は、人道的に許されません。
農水省でも、この食品ロスを減らすために 宴会の最初の30分と最後の10分は自席で食べようという「3010運動」を年末年始にかけて実施したり、ドギーバッグ普及委員会では、食べ残しを持ち帰る「ドギーバッグ」持参と自己責任持ち帰りカードの発行を進めるなどしています。ご存知でしたか? 残念ながら岡山では、かわいいデザインのドギーバッグは販売されていないようです。昔の食べ残しは折詰めで持ち帰りは日常的でしたが何時からそれが減っていったのでしょう?
今後、外食産業での食べ残し持ち帰りが広がることを個人的には期待します。
NPO法人岡山エコマインドネットワークと備前県民局では、6月25日 岡山シティミュージアムで 食のもったいないを考えるドイツのドキュメンタリー映画を上映します。
午前10時と午後2時からの2回上映(2時間10分)で定員は各回70名です。
当日は、食について活動するNPO法人フードバンク岡山への食品提供も受け付けます。
賞味期限が1か月以上あり、未開封の食品でアルコールや生ものは除きます。
食から考える環境イベントへ参加されませんか?
今週は、環境と食の中でも、調達と廃棄について考えます。第8回目の情報提供です。
入梅しましたが、岡山県は今の所、雨降らず状態、畑の作物は、雨を期待しているのではないでしょうか? 梅雨が明けると暑い夏がやってきます。暑さに負けないように土用の鰻が待ち遠しい方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回調達に関する話は、鰻にまつわるものです。 6月14日のRSKの夜の番組「VOICE LOVE」で紹介された鰻専門店は、自社の水槽で鰻を養殖していて、それを提供しているとの事です。
その種類は、絶滅が心配されるニホンウナギではなく、外来の鰻でした。自社の水槽なので、外来魚による環境影響の問題はなく、安定した国産ウナギが食べられる私たちにとっては、うれしい話です。
実は、倉敷市は鰻の養殖が盛んです。千葉県から稚魚を運び、倉敷アクアファームという企業が、閉鎖循環方式陸上養殖という方法で養殖した国産遺伝子を持つ国産のうなぎも数年前から養殖されています。トレーサビリティもしっかりしているので、岡山ではうなぎは安心して食べられそうです。本日6月15日の山陽新聞には、これと真逆の残念な記事が掲載されています。
昨年11月から今年4月にかけて採捕されたニホンウナギの幼魚シラスウナギの45.45%が密漁など違法取引に疑いがあることが共同通信の集計で分かりました。
ニホンウナギは2014年に国際自然保護連合と環境省により、近い将来における野生での絶滅の危険性が高い「絶滅危惧1B類」に指定されています。我が国は、中国、台湾、韓国との合意で資源管理の協定を結んでおり、国内の養殖池に入れるシラスを21.7トンまでに制限しています。国内でのシラス採捕は各自治体の知事の許可事項となっています。
しかし、19.4トンの池入れのうち、輸入物を除いた国内での採捕は15.5トン、許可申請をしているものは、8.4トンで7トンが無報告か密漁となっています。目先の利益だけを追うこの採捕の在り方には大いに疑問が残ります。鰻を食べる時にはトレーサビリティがしっかりした表示がなされる鰻を食べたいものです。
今後は、海のエコラベル「MSC(Marine Stewardship Council、海洋管理協議会)」
(:海洋の自然環境や水産資源を守って獲られた水産物(シーフード)に与えられる認証エコラベル)やASC:養殖版海のエコラベルの「ASC(Aquaculture Stewardship Council:水産養殖管理協議会)」の認証制度が広まることが期待されます。
温暖化防止対策を講じなければ、2100年頃には日本の海産物漁獲量が70%も減ると予測されており、自然資源は限りあるものとして大切にする業者への指導や消費者教育が求められる昨今です。
続いて、食品廃棄に関しての情報です。
世界で一番食べ物を輸入して、一番捨てている国はどこか 残念ながら日本です。
国内で消費する食品の量は9100万t、輸入食料は5800万tになります。そして、食べられない部位を含む食品くずや食べ残し、はたまた賞味期限により廃棄される食品の量は、1900万tにもなります。
食べ残し、賞味期限、過剰除去で食べられるのに捨てる「食品ロス」は年間620~630万tという量です。これは、世界中の食糧支援量390万tの2倍近い量なのです。世界では9億人が飢餓状態にあると言われており、お金の力で、他国から食べ物を搾取する行為は、人道的に許されません。
農水省でも、この食品ロスを減らすために 宴会の最初の30分と最後の10分は自席で食べようという「3010運動」を年末年始にかけて実施したり、ドギーバッグ普及委員会では、食べ残しを持ち帰る「ドギーバッグ」持参と自己責任持ち帰りカードの発行を進めるなどしています。ご存知でしたか? 残念ながら岡山では、かわいいデザインのドギーバッグは販売されていないようです。昔の食べ残しは折詰めで持ち帰りは日常的でしたが何時からそれが減っていったのでしょう?
今後、外食産業での食べ残し持ち帰りが広がることを個人的には期待します。
NPO法人岡山エコマインドネットワークと備前県民局では、6月25日 岡山シティミュージアムで 食のもったいないを考えるドイツのドキュメンタリー映画を上映します。
午前10時と午後2時からの2回上映(2時間10分)で定員は各回70名です。
当日は、食について活動するNPO法人フードバンク岡山への食品提供も受け付けます。
賞味期限が1か月以上あり、未開封の食品でアルコールや生ものは除きます。
食から考える環境イベントへ参加されませんか?
- 中山間地域の高齢化・人口減少について
- 私は岡山県高梁市の出身です。高梁市は岡山県内有数の高齢化率の中山間地域であり、それ故に多くの問題を抱..