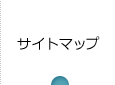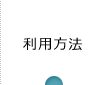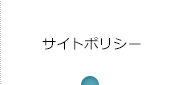タグ検索
市町村検索
同一タグの記事
- 自分の“職能”を活かした新しいNPO支援。 「プロボノによるNPO等の情報発信・運営支援事業」
- なぜ今、NPOに情報開示が求められるのか。 「信頼できるNPO等を紹介するウェブサイトを活用した情報開示促進事業」
- 正しい理解が、NPOの力に。①「NPO新会計基準導入促進事業」
- 正しい理解が、NPOの力に。②「認定NPO法人取得促進事業」
- 気軽にはじめる社会貢献のすゝめ ~ガチャガチャリティと募金箱
- 割り勘で夢をかなえよう!第3期の募集がスタートしました。
- 施設送迎運転者講習会のレポート
- サマ★ボラキャンペーン!始めました!(ゆうあいセンター)
- 人と人をつなぐ「市(マルシェ)」 『備前福岡の市』編
- インターンシップ
企業とNPOの活動を持続可能にするために
活動・取り組みその他
Noboru Ogiri
こんにちは、ゆうあいセンターCSR相談員 小桐です。
今回は、企業とNPOの活動を持続可能にする活動について考えてみたいと思います。
■持続可能性を高めるには
企業やNPOは、それぞれの団体の目的を達成するために、色々な事業を展開しています。しかし、社会は、動いており、団体を取り巻く環境が変われば、おのずとそこで展開する事業は変化しなくてはならないはずです。
どんな企業やNPOでも影響を受けるのは、まず地球環境の変化、自団体を取り巻く社会環境の変化です。ここで私たちを取り巻く地球と社会の環境の変化について列記します。
■地球環境の変化と変化への対応
・地球温暖化が進行していることは、皆さんが普段の生活をしてお分かりだと思います。この温暖化を阻止するために、世界、日本では社会の大きな変化が起きていることをご存知でしょうか?
それは、温暖化防止に関するCOP21 パリ協定の発効と日本の批准です。
2030年までに、日本は、2013年比26%のCO2削減を達成しないといけません。企業・団体の事務所と家庭では、40%の削減を求められることになります。あと14年しかありません。
2100年には、温暖化0を掲げており、「化石燃料を使わない事業活動、生活」を求められます。
エネルギーを化石燃料から、再生可能な自然エネルギーにシフトしなくてはなりません。
また、そこに企業では、ビジネスチャンス、NPOでは、新たな社会課題の解決のチャンスがあります。
日本で取れない石油でなく、バイオマスや、太陽・風・地熱などの自然エネルギーへのシフト、水素自動車など新技術の開発が求められます。例えばトヨタ自動車は昨年、「トヨタ環境チャレンジ2050」を発表。
①2050年グローバル新車平均走行時CO2排出量を90%削減(2010年比)
②ライフサイクル視点で、材料・部品・モノづくりを含めたトータルでのCO2排出ゼロ
③050年グローバル工場CO2排出ゼロ
④各国地域事情に応じた水使用量の最小化と排水の管理
⑤循環型社会・システム構築チャレンジ
⑥人と自然が共生する未来づくりへのチャレンジ の6項目に取り組み始めています。
これらの目標の達成には、今までの積み重ねではなく、「パラダイムシフト」が必要です。
つまり、維持や継続でなく、進化をしていかないといけないということです。
■社会環境の変化
1)昨年国連の会議で地球と社会を持続可能なものとするための世界全体の取り組み「SDGS(サステナブル ディベロップメント ゴールズ=持続可能な開発目標)」の実施が採択されました。世界を変えるための17の目標と具体的に実践するための169のターゲットがあります。 「気候変動に具体的な対策を」、「エネルギーをみんなに・そしてクリーンに」、「海の豊かさ・陸の豊かさを守る」と言う環境の目標や世界から「貧困をなくす」、「全ての人に健康と福祉を」という社会的な目標などが上げられています。今後、国内においても具体的な取組が開始されるようになります。そんな中、「パートナーシップで目標を達成しよう」という目標も挙げられています。持続可能な社会をつくる為には、立場の異なる多様な主体の連携・協働による様々な取組が必要だということではないでしょうか?
2)すべての組織の社会的責任を果たすためのガイドラインISO26000とISO20400
2010年11月1日に発行した、すべての組織の社会的責任に関する国際規ISO26000は、国際標準化機構が3年以上の歳月を掛け、世界の政府、企業、市民団体など様々なステークホルダーの話し合いの結果合意した「ガイドライン」です。他のISO規格と異なる点は、認証取得る規格ではなく、ガイドライン(手引き)として自らが取り組むものという点です。
組織が持続的に活動するためのツールとして有効なものと言えます。内容は組織が取り組むべき7つの中核課題と7つの原則として整理されています。
7つの課題は、組織統治、人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行、消費者課題、コミュニティへの参画。そして、7つの原則は、説明責任、透明性、倫理的な行動、ステークホルダーの利害の尊重
法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重です。
このISO26000ガイドラインを活用して、企業がCSRレポートや統合報告書などの形で事業活動の報告書を発行する企業が増加し2015年1038社となっています。これまでは、大企業が殆どでしたが、中小企業でも制作数が徐々に増えてきています。
自社の本業を含む事業活動がどれだけ、社会的な責任を果たしているかを対外的に公表することが、企業の安定的な事業継続と社会的信頼を増加させるものと理解されているという理由です。企業が社会市民であるという自覚なしには、今後社会から必要とされなくなるという自らを客観的に見る姿勢の表れと考える事もできるのではないでしょうか?
来年2017年には、ISO20400が発行予定です。「持続可能な調達」についてのガイドラインとして、法・倫理・環境・人権などの社会的責任の観点も含め、将来にわたって持続可能である調達活動を可能とするガイドラインとして整備されようとしています。これまで以上に調達についても配慮すべき点が増加します。取り組めばリスク低減となりますが、放置すれば企業にとっての足元をすくわれることになる可能性もあります。
■企業とNPOとの協働で互いの安定を高める
そして、さらに企業活動を持続可能なものにする取り組みとして、NPOとの協働の取り組みが上げられます。その一つの形として、これまでのマーケティングに社会課題の解決も目指しながら、利益を上げるスタイルとして、CRM(コーズマーケティング)と言うものがあげられます。コーズ(大義、目標、理想、良き事)を全面に出したマーケティング活動です。経済学者のコトラーは「企業が製品の売り上げや取引に応じて得られた利益の一定割合を何らかの組織に寄付すること」で「時間的限定で、特定製品を対象に、特定のコーズ」と共に行うマーケティングであると言っています。
CRMは「社会的問題解決型マーケティング」とも言われていて、利益獲得(販売増)を中心目的としている所、あるいは貢献の水準が製品の売り上げと結びついている点が特徴となっています。
■企業とNPO双方のCRMのメリット
①企業にとってのメリット
1販売促進効果
社会性のあるメッセージを付与することで製品の差別化が起き、消費者の購買意識を後押しする事によって、売り上げ増加、収益増が期待できます。
2ブランディング効果
CSR意識の高い企業であるという好ましい企業イメージ「ブランド・アイデンティティ」の構築に大いに役立ちます。CRMの対象となる商品・サービスやその広報媒体に、社会貢献に取り組む 企業理念、社会的メッセージ、さらに活動内容についての説明などを付与することで、企業情報及び商品の社会的ブランド価値を高めることができます。
3新市場開拓効果
CRMによって新しい顧客をでき、ニッチ市場への展開が可能となります。特にコーズに共感する人々の市場と言う新たなセグメントに食い込むことが出来ます。
4ステークホルダー効果
顧客を超えて社会全体、より広がりのあるステークホルダーへのメッセージ性を持つことで、ステークホルダーからの)評価が期待でき、また実際に顧客とのコミュニケーションにも大きくかつ良い影響を与えます。
5CSR経営効果
CRMはCSR活動と事業(経済)成果との両立を図ることが出来ることによって、マーケティング部門とCSR部門(組織)との協調が発生する。そのためCSR経営に対して必ずしも協調的でなかったマーケティング部門とCSR推進担当部門との連携が可能となり、全社的にCSR経営への理解が進みます。
②NPOにとってのメリット
1知名度・認知度・信頼性の向上
信頼できる企業との共同広報を通して、NGO事態の知名度と共に、その解決されるべき社会課題(コーズ)とその取り組みキャンペーンの認知度、さらに一般の人々からの)信頼も大きく向上する可能性を持つ。コーズが広報され、そのコーズの意味・問題・児たちを多くの人が知る事になり、NGOの活動の達成度を拡大させることが出来ます。
2資金源の多様化・安定化
NGOにとって活動の展開の為には、収入の安定化と収入源の多様化は欠かせません。その点で、CRMはNGOにとって安定的な収入を得るための重要な企業パートナーシップ(協働)の形態の一つであると言えます。(状況によってはより大きな資金調達が出来る可能性を持っている)
CRMから得た資金によって。より広く深くコーズへの対応が可能となります。
3従業員の協力・寄付の上乗せ
CRMによって企業とのつながりが強くなることによって当該企業の社員のボランティア参加や寄付の上乗せなどが可能となります。さらに、企業がボランティア休暇制度を持っている場合などには、ボランティア派遣、プロボノの制度がある場合は社員の専門的な職業スキルなども可能となります。
4対等な協働関係へ
企業との関係性を一時的な関係から長期的・戦略的な関係へと真の意味で対等な協働関係へ移行できる可能性があります。企業は従来のドナー(寄付者)から「パートナー」へ変化するということです。
コーズマケーティングマーケティング以外にも企業とNPOの取り組みの方法はありますが、今後持続可能な社会をつくる為には、企業、NPO共にマーケティング、事業活動に置いて、従来型の単独の活動スタイルでなく、互いに共通する社会課題を見つけ、協働によって課題解決を図る方法がより求められるようになると思われます。
今回は、企業とNPOの活動を持続可能にする活動について考えてみたいと思います。
■持続可能性を高めるには
企業やNPOは、それぞれの団体の目的を達成するために、色々な事業を展開しています。しかし、社会は、動いており、団体を取り巻く環境が変われば、おのずとそこで展開する事業は変化しなくてはならないはずです。
どんな企業やNPOでも影響を受けるのは、まず地球環境の変化、自団体を取り巻く社会環境の変化です。ここで私たちを取り巻く地球と社会の環境の変化について列記します。
■地球環境の変化と変化への対応
・地球温暖化が進行していることは、皆さんが普段の生活をしてお分かりだと思います。この温暖化を阻止するために、世界、日本では社会の大きな変化が起きていることをご存知でしょうか?
それは、温暖化防止に関するCOP21 パリ協定の発効と日本の批准です。
2030年までに、日本は、2013年比26%のCO2削減を達成しないといけません。企業・団体の事務所と家庭では、40%の削減を求められることになります。あと14年しかありません。
2100年には、温暖化0を掲げており、「化石燃料を使わない事業活動、生活」を求められます。
エネルギーを化石燃料から、再生可能な自然エネルギーにシフトしなくてはなりません。
また、そこに企業では、ビジネスチャンス、NPOでは、新たな社会課題の解決のチャンスがあります。
日本で取れない石油でなく、バイオマスや、太陽・風・地熱などの自然エネルギーへのシフト、水素自動車など新技術の開発が求められます。例えばトヨタ自動車は昨年、「トヨタ環境チャレンジ2050」を発表。
①2050年グローバル新車平均走行時CO2排出量を90%削減(2010年比)
②ライフサイクル視点で、材料・部品・モノづくりを含めたトータルでのCO2排出ゼロ
③050年グローバル工場CO2排出ゼロ
④各国地域事情に応じた水使用量の最小化と排水の管理
⑤循環型社会・システム構築チャレンジ
⑥人と自然が共生する未来づくりへのチャレンジ の6項目に取り組み始めています。
これらの目標の達成には、今までの積み重ねではなく、「パラダイムシフト」が必要です。
つまり、維持や継続でなく、進化をしていかないといけないということです。
■社会環境の変化
1)昨年国連の会議で地球と社会を持続可能なものとするための世界全体の取り組み「SDGS(サステナブル ディベロップメント ゴールズ=持続可能な開発目標)」の実施が採択されました。世界を変えるための17の目標と具体的に実践するための169のターゲットがあります。 「気候変動に具体的な対策を」、「エネルギーをみんなに・そしてクリーンに」、「海の豊かさ・陸の豊かさを守る」と言う環境の目標や世界から「貧困をなくす」、「全ての人に健康と福祉を」という社会的な目標などが上げられています。今後、国内においても具体的な取組が開始されるようになります。そんな中、「パートナーシップで目標を達成しよう」という目標も挙げられています。持続可能な社会をつくる為には、立場の異なる多様な主体の連携・協働による様々な取組が必要だということではないでしょうか?
2)すべての組織の社会的責任を果たすためのガイドラインISO26000とISO20400
2010年11月1日に発行した、すべての組織の社会的責任に関する国際規ISO26000は、国際標準化機構が3年以上の歳月を掛け、世界の政府、企業、市民団体など様々なステークホルダーの話し合いの結果合意した「ガイドライン」です。他のISO規格と異なる点は、認証取得る規格ではなく、ガイドライン(手引き)として自らが取り組むものという点です。
組織が持続的に活動するためのツールとして有効なものと言えます。内容は組織が取り組むべき7つの中核課題と7つの原則として整理されています。
7つの課題は、組織統治、人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行、消費者課題、コミュニティへの参画。そして、7つの原則は、説明責任、透明性、倫理的な行動、ステークホルダーの利害の尊重
法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重です。
このISO26000ガイドラインを活用して、企業がCSRレポートや統合報告書などの形で事業活動の報告書を発行する企業が増加し2015年1038社となっています。これまでは、大企業が殆どでしたが、中小企業でも制作数が徐々に増えてきています。
自社の本業を含む事業活動がどれだけ、社会的な責任を果たしているかを対外的に公表することが、企業の安定的な事業継続と社会的信頼を増加させるものと理解されているという理由です。企業が社会市民であるという自覚なしには、今後社会から必要とされなくなるという自らを客観的に見る姿勢の表れと考える事もできるのではないでしょうか?
来年2017年には、ISO20400が発行予定です。「持続可能な調達」についてのガイドラインとして、法・倫理・環境・人権などの社会的責任の観点も含め、将来にわたって持続可能である調達活動を可能とするガイドラインとして整備されようとしています。これまで以上に調達についても配慮すべき点が増加します。取り組めばリスク低減となりますが、放置すれば企業にとっての足元をすくわれることになる可能性もあります。
■企業とNPOとの協働で互いの安定を高める
そして、さらに企業活動を持続可能なものにする取り組みとして、NPOとの協働の取り組みが上げられます。その一つの形として、これまでのマーケティングに社会課題の解決も目指しながら、利益を上げるスタイルとして、CRM(コーズマーケティング)と言うものがあげられます。コーズ(大義、目標、理想、良き事)を全面に出したマーケティング活動です。経済学者のコトラーは「企業が製品の売り上げや取引に応じて得られた利益の一定割合を何らかの組織に寄付すること」で「時間的限定で、特定製品を対象に、特定のコーズ」と共に行うマーケティングであると言っています。
CRMは「社会的問題解決型マーケティング」とも言われていて、利益獲得(販売増)を中心目的としている所、あるいは貢献の水準が製品の売り上げと結びついている点が特徴となっています。
■企業とNPO双方のCRMのメリット
①企業にとってのメリット
1販売促進効果
社会性のあるメッセージを付与することで製品の差別化が起き、消費者の購買意識を後押しする事によって、売り上げ増加、収益増が期待できます。
2ブランディング効果
CSR意識の高い企業であるという好ましい企業イメージ「ブランド・アイデンティティ」の構築に大いに役立ちます。CRMの対象となる商品・サービスやその広報媒体に、社会貢献に取り組む 企業理念、社会的メッセージ、さらに活動内容についての説明などを付与することで、企業情報及び商品の社会的ブランド価値を高めることができます。
3新市場開拓効果
CRMによって新しい顧客をでき、ニッチ市場への展開が可能となります。特にコーズに共感する人々の市場と言う新たなセグメントに食い込むことが出来ます。
4ステークホルダー効果
顧客を超えて社会全体、より広がりのあるステークホルダーへのメッセージ性を持つことで、ステークホルダーからの)評価が期待でき、また実際に顧客とのコミュニケーションにも大きくかつ良い影響を与えます。
5CSR経営効果
CRMはCSR活動と事業(経済)成果との両立を図ることが出来ることによって、マーケティング部門とCSR部門(組織)との協調が発生する。そのためCSR経営に対して必ずしも協調的でなかったマーケティング部門とCSR推進担当部門との連携が可能となり、全社的にCSR経営への理解が進みます。
②NPOにとってのメリット
1知名度・認知度・信頼性の向上
信頼できる企業との共同広報を通して、NGO事態の知名度と共に、その解決されるべき社会課題(コーズ)とその取り組みキャンペーンの認知度、さらに一般の人々からの)信頼も大きく向上する可能性を持つ。コーズが広報され、そのコーズの意味・問題・児たちを多くの人が知る事になり、NGOの活動の達成度を拡大させることが出来ます。
2資金源の多様化・安定化
NGOにとって活動の展開の為には、収入の安定化と収入源の多様化は欠かせません。その点で、CRMはNGOにとって安定的な収入を得るための重要な企業パートナーシップ(協働)の形態の一つであると言えます。(状況によってはより大きな資金調達が出来る可能性を持っている)
CRMから得た資金によって。より広く深くコーズへの対応が可能となります。
3従業員の協力・寄付の上乗せ
CRMによって企業とのつながりが強くなることによって当該企業の社員のボランティア参加や寄付の上乗せなどが可能となります。さらに、企業がボランティア休暇制度を持っている場合などには、ボランティア派遣、プロボノの制度がある場合は社員の専門的な職業スキルなども可能となります。
4対等な協働関係へ
企業との関係性を一時的な関係から長期的・戦略的な関係へと真の意味で対等な協働関係へ移行できる可能性があります。企業は従来のドナー(寄付者)から「パートナー」へ変化するということです。
コーズマケーティングマーケティング以外にも企業とNPOの取り組みの方法はありますが、今後持続可能な社会をつくる為には、企業、NPO共にマーケティング、事業活動に置いて、従来型の単独の活動スタイルでなく、互いに共通する社会課題を見つけ、協働によって課題解決を図る方法がより求められるようになると思われます。

- 自分の“職能”を活かした新しいNPO支援。 「プロボノによるNPO等の情報発信・運営支援事業」
- プロボノとは、今までの “労働力を提供するボランティア” とは異なり、様々な分野のプロが自分たちの専..